【霊告月記】第四十九回 『悪の華』&『源氏物語』ダブル批評
】霊告【 映画「 LORO 欲望のイタリア」:ヴェロニカへの愛を証明すべくベルルスコーニが彼女に思い出の歌「Domenica Bestiale」をサプライズする場面。ファビオ・コンカート本人が登場して歌う。
◇ボードレール『悪の華』批評 
Charles Baudelaire, 1821 – 1867
『悪の華』中の93番目の詩「A UNE PASSATE」を、福永武彦は「通り過ぎた女」と訳し、安藤元雄は「通りすがりの女(ひと)に」と訳している。
「A UNE PASSATE」は四連から成っている。その第三連目の訳をまず双方から引用しておく。
1)安藤元雄訳「通りすがりの女(ひと)に」第四連
一瞬の稲妻……あとは闇!
――消え去った美しい人
そのまなざしが私をいきなり生き返らせたひとよ
君にはもはや永遠の中でしか会えないのか?
2)福永武彦訳「通り過ぎた女」第四連
稲妻のように……そして夜!
――束(つか)の間の美しい人よ、
その眼差(まなざし)は一瞬に僕を生へと呼び戻したのに、
もはや永遠の中でしか、お前に会うことは出来ないのか?
詩は複雑微妙な感情を詳しく長く説明するのではなく短く数語で圧縮するところにその妙味がある。 その観点からは、一行目の訳は安藤の訳に軍配が上がるだろう。 「一瞬の稲妻……あとは闇!」。翻訳されたボードレールの日本語としてこれ以上すばらしい訳は想像することすらできない。この一行でボードレールの全詩を象徴していると言っていいほどだ。芥川龍之介が「人生は一行のボードレールに如かない」と述べた。その一行は芥川の研究者にも不詳のようだが、「これだ! これがその一行だ」ともし誰かが述べたとしても、私はその主張に反対はしないだろう。 ただ原詩が圧縮された表現であり、それを直訳すると原詩に含まれたニュアンスがうまく伝わらないことがある。その時、些少の説明的要素を加えて訳することは許される。許されるというより、当の詩人に対する敬意という観点からすれば必須の義務とも言えよう。福永武彦の第二行から第三行へかけての日本語訳は分かりやすい。しかも美しい。日本語の詩として安藤の訳詩を上回っていると言うことは許されるだろう。
安藤元雄と福永武彦はボードレールの詩を外国語(=この場合は日本語)に翻訳するするという苦行を実践した。日本人に日本語訳というかたちでボードレールの価値を伝えた。双方で補い合うことによって彼ら(安藤と福永)は「翻訳者の使命」を立派に果たした。読み比べてみて初めて見えてくるボードレールの偉大さ。ボードレールの詩作品を翻訳する試みは、ベンヤミン云うところの「純粋言語」に到達しようとする希求に添うことができるのだ。そのように私は考えている。
※この「悪の華」批評は次の「源氏物語」批評と共に、『翻訳されたベンヤミンについて』(宇波彰現代哲学研究所2019年10月21日掲載) の補論です。 ☛ 翻訳されたベンヤミンについて
◇紫式部『源氏物語』批評
本居宣長は源氏物語の本質を『紫文要領』の中において次のように指摘している。
「この物語の外に歌道なく、この歌道の外に物語なし。歌道とこの物語とは、まったくその趣き同じことなり」(本居宣長『紫文要領』)
源氏物語は単に物語というだけでない。歌道の書でもあると宣長は述べる。単に歌を読むだけではわからないことが、源氏物語を読むと分かってくる。上古の人がいかなる気持ちで歌を作ったか、その作りざま、歌を詠む際の彼らの心ばえが手に取るように分かってくるのだと宣長は指摘する。この意味において源氏物語は歌道の書なのである。
源氏物語の中で私が最も愛するのは篝火(かがりび)の巻であった。源氏全五十四帖の中でおそらく最も短い巻だが、ここには歌物語としてのエッセンスが縮凝されているやに思えて私は好きなのである。篝火が燃えている情景の中で、光源氏が玉鬘に一つの歌を贈り、玉鬘の返歌がなされる。「篝火」の巻からその部分を原文と現代訳で引証しておく。
★渋谷栄一による現代語訳と紫式部の原文★
「篝火とともに立ち上る恋の煙は永遠に消えることのないわたしの思いなのです。いつまで待てとおっしゃるのですか。くすぶる火ではないが、苦しい思いでいるのです」と申し上げなさる。女君は、「奇妙な仲だわ」とお思いになると、「果てしない空に消して下さいませ。篝火とともに立ち上る煙とおっしゃるならば。人が変だと思うことでございますわ」とお困りになるので、「さあて」と言って、お出になると、東の対の方に美しい笛の音が、箏と合奏していた。
「篝火にたちそふ恋の煙こそ世には絶えせぬ炎なりけれ。いつまでとかや。ふすぶるならでも、苦しき下燃えなりけり」と聞こえたまふ。女君、「あやしのありさまや」と思すに、「行方なき空に消ちてよ篝火のたよりにたぐふ煙とならば。人のあやしと思ひはべらむこと」とわびたまへば、「くはや」とて、出でたまふに、東の対の方に、おもしろき笛の音、箏に吹きあはせたり。
結論。たしかに源氏物語の巻々は、歌の交換の場面において白熱する。源氏物語は単に長編小説というだけではない。言葉の美しさをその極限まで究めた詩的対話の書でもある。源氏物語はいまなお我々にとって〈みやび〉の源泉なのである。
★Fabio Concato - DOMENICA BESTIALE

















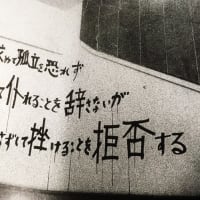


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます