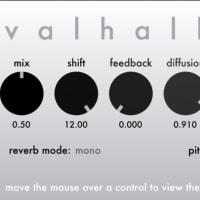実はこの9月上旬は、去年のような猛残暑が無ければ、本来は年間で最も多種のトンボを見ることが出来る時期だ。

これはトンボの仲間ごとの大まかな季節的消長の概念図である。
あくまで大まかな概念なので、細かい突っ込みは勘弁して欲しいところだが、グラフをみると
夏の終わりから秋の初めにかけて全体のピークがあるように見える。
夏のトンボはこれから9月一杯にかけてゆっくりと衰退していき、涼しくなってくるとアカネ類が
台頭してくる。大型ヤンマ類の大半は概ね8~9月にピークを迎えるので、盛夏から初秋に多くなる。
アカネ類は彼岸過ぎ頃をピークに衰退していき、それと共にトンボのシーズンは終わりを告げる。
自分がかつて一箇所のフィールドで一日に観察した最多種類数は18年前の9月10日に記録した28種である。
一日でおよそ30種を観察できてしまうのはある意味すごいことだ。春には春のピークがあるが、種類数は
意外と少なく10種を越える程度である。初秋に観察できる種類が多いのは主にアカネ類の種類の多さに起因
しているとも言える。
各地のフィールドに於いて環境変化により徐々に観察できるトンボが減ってきている今日では、いったいどのくらいの
トンボを一度に観察できるのだろうか?正味二時間の枠を設けて一カ所の良好な環境で試してみた。

イトトンボ類は夏にピークがあるが、この時期は徐々に衰退していく種類が多い。
一番探し出すのに苦労したのは意外にもクロイトトンボだった。

この時期はアオイトトンボの最盛期でもある。
市街地の池で見かけることもあり、移動性の大きい種類なのかもしれない。

トンボ科のトンボ類は徐々に衰退しつつもまだまだ健在である。林間の暗い茂みを探すと、オオアオイトトンボも見られた。

飛翔個体撮影は時間もないのでいい加減になってしまい恐縮だがオニヤンマ、オオルリボシヤンマ、ギンヤンマといった大型種、
この時期に最大のピークを迎えるウスバキトンボ・そしてアキアカネが空中を賑わせていた。

ナツアカネ、ノシメトンボ、マユタテアカネは未だ控えめな感じで水辺の周囲に陣取っていた。

水辺で隆盛を誇っていたのはアキアカネ、ネキトンボ、リスアカネ。成熟してきたヒメアカネも水辺の下草で見られた。
結局、正味二時間で冒頭のオナガサナエを含めて21種のトンボを撮影出来た。
18年前の28種は正味五時間の観察だったので、粘れば少なくともあと2~3種は見られただろう。
観察したトンボを制限時間内ですべて写すのはなかなか難しいかと思われたが、見つければ大概撮影動作に
入るので、とりあえず写すだけなら何とかなる。