新説百物語巻之二 1、相撲取荒碇魔に出合ひし事
相撲取りの荒碇(あらいかり)が魔物にであった事
上京に荷物を運んで暮らしていた夫婦がいた。平生から相撲を好んで、荒碇(あらいかり)と名のっていたが、すこし訳があって、後には楯石(たていし)と名を変えた。
荷物をはこぶのに、常に、大津又は伏見鳥羽より馬の一駄分の荷物を軽々と一まとめにして持ち運んでいた。
それで、他の人よりも賃銭を多く取って、夫婦は楽々と毎日を送っていた。
ある時、又々いつもの様に大津へ荷物を持って行き、帰りには、石の井筒の四枚にしたのを二枚づつにした。おおよそ一荷の重さは七拾四五貫目位あったのを持ち帰ろうとした。日の岡を越えて、一息ついて思った事は、この街道をおおくの荷物を運ぶ人は多い。しかし、七拾貫目余りの荷物を運べる者は、自分以外はいないであろう、と思った。休んでいる所に、何国(どこ)より来たのかはわからないが、四十ばかりの女が、同じようにそばに休んでいた。荒碇は、声をかけて、「どちらに行かれるのですか?
たばこの火をお貸ししましょう。」といった。
すると、彼の女が「それはありがたいね。」と答えて、懐中よりキセルを取り出した。荒碇も荷をおろして話を始めた。すると、女が「その荷物は、どの位の重さなのかい?」と尋ねた。
荒碇は、「大体七拾貫目余りもあるね。この街道でこの位重い荷を持って通う者は、ワシ外はいないだろうね。」と、自慢げに答えた。
この女は少しも驚く様子もなく、「それなら、この風呂敷包を持ってみなよ。」と言って、小さい風呂敷をさし出した。
「これは簡単な事」と言って、手をさしのばし、手の上にのせた。その重さが何百貫目あるかも判らない位であった。
重さに耐えきれず、下に置いて、大いに驚いた。
女は、「この風呂敷さへ持てないのに、力自慢をするのは、おかしいことだね。」と言っている内に、顔の様子が変わった。色は青ざめて、目は光輝き、口は耳の根まできれ、すっくと立ったありさまは、さしもの剛の男も、恐ろしくて震えるばかりであった。が、俄に雨風が激しくなり、空はかき曇って、真っ暗闇となった。
荒碇はなすすべもなく、常に信心していた天満宮の御名を唱え、目を塞いで、打ちふしていた。しばらくすると雨風もやみ、彼の女も見えなくなっていた。
あたりを見渡すと、そこは往還の人たちが大勢通っている海道の側であった。
この者の高慢の鼻をへし折ろうと、魔物がこんなことをしたのであろうか?。
その後は、かの男は相撲もやめ、力事もしなかったとのことであった。














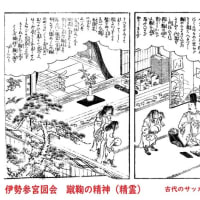




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます