2025年2月12日歴史探偵で名君と呼ばれた9代目米沢藩主上杉鷹山の特集をしていました。
米沢城はまだ登っていませんが、続100名城ですしいつか必ず行ってみたいと思っています。
さて上杉鷹山ですが、彼は日向高鍋藩秋月種美さんの息子として、母は秋月藩秋月藩黒田氏の娘から江戸で生まれました。
紆余曲折あって米沢上杉家の養子となります。
もちろん上杉家は謙信以来の名家ではあるのですが、景勝の時に石田三成に組して120万石から30万石に領地が減らされてしまいました。
それだけでもピンチなのに基本的に家臣を解雇しなかったので、生活は厳しいものとなります。
更に3代目の綱勝さんが26歳の若さで子供もいないまま急死してしまい、お家断絶の大ピンチ。
ここで親戚の会津藩主保科正之(2代将軍秀忠の子ですもんね!)が活躍して、末期養子を取ります。
それが何と吉良上野介義央の息子が4代目綱憲として跡を継ぐのです。
以来、吉良家への肩入れや赤穂浪士討入り事件の影響や、代々の藩主が借金を増やしていくことになります。
更に領地を減らされて15万石になってしまいました(´・ω・`)
ここで9代目上杉鷹山治憲が登場し、質素倹約をモットーに殖産興業に注力して、藩政改革を成功させます。
家臣老臣との軋轢はあったのですが、遂には死後のことですが借金をすべて返済するのです。
とんでもない名君だったのですねえ。
奥様(第8代藩主重定)の娘を娶ったのですが、発育障害があったと言われ、わずか30歳で亡くなってしまいます。
鷹山は、奥様とおままごとや人形遊びのお相手を真剣に務めたそうですよ。
私はそれを聞いて泣きそうになりました( ;∀;)また奥様存命中は側室を置かなったんですって(つд⊂)エーン
上杉鷹山さんの素晴らしい業績は他の方も書いているし、ご存じの方も多いでしょう。
今回、私はある逸話についてだけ触れたいと思っています。
1778年安永6年12月6日にヒデヨというお婆さんが娘のおかのさんに書いた手紙が残っています。
原文はこちら。
一トフデ申シ上ゲマイラセ候アレカラオトサタナク候アイダ
タツシヤデカセキオルモノトオモイオリ候
オラエモタッシャデオルアンシンナサレタク候
アキエネノザンギリボシシマイユーダチガキソウデキヲモンデイタラ
ニタリノオサムライトリカカツテオテツダイウケテ
カエリニカリアゲモチアゲモウスドコヘオトドケスルカトキイタラ
オカミヤシキキタノゴモンカライウテオクトノコト
ソレデフクデモチ三十三マルメテモツテユキ候トコロ
オサムライドコロカオトノサマデアッタノデコシガヌケルバカリデタマゲハテ申シ候
ソシテゴホウビニギン五マイヲイタタキ候
ソレデカナイヂウトマゴコノコラズニタビくレヤリ候
オマイノコマツノニモヤルカラオトノサマヨリハイヨーモノトシテダイシニハカセラレベク候
ソシテマメニソタテラルベククレグレモネガイアゲ候
十二かつ六か
トウベイ
ヒデヨ
おかのどの
ナホ申シアケ候マツノアシニアワヌトキワダイジニシマイオカルベク候
イサイショガツニオイデノトキハナスベク候
全然分からんでしょ?(笑)
八犬伝に挑戦している身なので、超意訳してみます。
間違っていたらすいません。
-------------------------------------------------------------------------------
一筆申し上げます。
あれから音沙汰がありませんが、達者で農作業に精を出しておられると思っております。
私も達者ですので、安心なさって下さい。
秋稲の散切り干しを片づけていると、夕立ちが来そうで気を揉んでおりました。
そこへ二人のお侍が通りかかって、片づけのお手伝いをして下さいました。
お帰りになる際に、お礼として刈上げ餅を差し上げたいので、どこへお届けいたしましょうかとお尋ねしましたら、
お上屋敷北の御門に申し付けておくから、とのこと。
さっそく福田餅を三十三個、丸めて持って行ったところ、
相手様はお侍どころかお殿様でございましたので、腰が抜けるばかりで、たまげ果ててしまいました。
そしてご褒美として銀五枚をいただきました。
家内中と子供、孫たちに残らず足袋を差し上げます。
そちらの小松にも送りますので、お殿様からの拝領物として大事にお履き下さい。
子供たちを心を込めて大切にお育ていただきます様、くれぐれもお願いいたします。
トウベイ
十二月六日 ヒデヨ
おかの殿
尚、申し上げますが、まつの足に合わない時は大事におしまい置き下さい。
委細、お正月にお出での時にお話いたします。
※散切り干し……藁かな?
※刈上げ餅……新米でついたお餅。五穀豊穣を祈願します
※福田餅……丸く作ったお供え餅
※小松……米沢の北西に小松という地名があります。JR羽前小松駅というところもありました
※トウベイ……ヒデヨさんの住所か屋敷名
この手紙から分かることは、
①27歳のお殿様は領内をお忍びで回っていた。
地味に良民を助けた!!水戸黄門みたいなお話です。
②当時のお百姓は字を書けた
当時の識字率が伺われます。
もちろんヒデヨさん直筆ではなくても、ヒデヨさんの一族、或いは近在に字をカタカナで候文を書くことができる人がいたということが想像できるのです。
(名主かお坊さんかもしれませんけどね)
このお手紙と足袋の現物が残っています。

宮坂考古館|山形県米沢市にて前田慶次、上杉謙信、直江兼続の縁の品を展示中
ふと通りかかったお殿様がお婆さんを手伝うとか、良いお話だと思うのです。
少し心が暖かくなったのでこんな話をご紹介いたしました。
米沢牛弁当ど真ん中を食べながら新幹線に乗って、米沢城に登城してみたいですね、でわ。










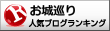

















江戸の頃の字というと、古文書、高札、手紙、、、崩し字のようなのを思っていました。
一般的にはカタカナが使われていたのですね
なんだか、電報文のようでござ候
2人の侍が来て手伝ってもらって、、餅あげたら、お殿様で、、、
たまげて腰が抜けて歩けなくなった
というのはわかりました(笑)
暖かそうな足袋ですね。
候と数字以外は全部カナですから、私たち現代人にも読みづらい。
でも素朴な感じが伝わってきました。
腰が抜けるばかりでたまげた、本当に魂消たんでしょうねえ。
お殿様が出て来れば、それは(笑)
この後天明の大飢饉が東北地方を襲うのですが、ヒデヨさん一族は大丈夫だったのかしら?
心配です。