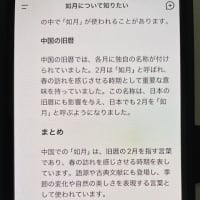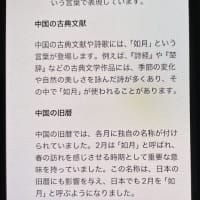現代日本語文法文章論 題材は、タイトルが、スリランカで“文庫”を思う とある。エッセイである。日本経済新聞の文化面、20141019 付けである。執筆者は、佐伯泰英氏である。なお、有料会員サイトであり、著作の全文をこのように言語分析に資料としているので、そのことをお断りするとともに、ここにお礼を申したい。
冒頭の文は、次である。
> インド洋に突き出たスリランカ南部、港町ゴールのホテルで、持参した北欧系作家のミステリーの文庫を読んでいた
末尾の文は、次である。
> (読み手を暗い気持ちに陥らせる時代小説だけは書くまい) と思いながら、また夜明け前に起きての執筆暮らしに戻った。
書き出しの文段は、次のようである。
> インド洋に突き出たスリランカ南部、港町ゴールのホテルで、持参した北欧系作家のミステリーの文庫を読んでいた。四月のことだ。旅に出たのだ、活字から離れればよいものをつい読んでいた。北欧系ミステリー作家の作風がすべて北欧の冬の景色を思い浮かばせるように沈鬱で厳しいとは思わない。だが、読めば読むほどこちらの気持ちも萎えていき、光あふれる熱帯のゴールに居ながらにして交易時代の文化が積み重った砦(とりで)の町を散策する気になれなかった。なんともばかばかしい話だ。
末尾の文段は、次のようである。
>だが、釈然としない。活字にこだわってきた小説家が電子書籍にまで気を遣わねばならないのか。ゴールにいる数日間、結局答えは出なかった。
(読み手を暗い気持ちに陥らせる時代小説だけは書くまい)
と思いながら、また夜明け前に起きての執筆暮らしに戻った。
段落は、次のようである。
> 私は活字世界に生き残るために毎日書き続けた。三年目からは年間十二冊を超え、「月刊佐伯」と揶揄(やゆ)された。それでも、読者の一部の方は古き良き時代の雑誌連載、ハードカバーの流れを断ち切って、いきなり文庫化される時代小説を手にしてくれるようになった。分析すればいろいろと理由はあろう。
> 現在、私が文庫書下ろしに手を染めた当時の文庫観とは違う時代が到来していた。
> スリランカのゴールの話しに戻る。北欧ミステリーの小説に限らず欧米の小説家は、せいぜい年間一冊、精魂込めて集中して作品を仕上げると聞く。日本でも純文学系の作家は、全神経を尖(とが)らせて一作品を仕上げるのだろう。
2014/10/19付
日本経済新聞 朝刊
この夏、愛読者は興奮した。川端康成が初恋の女性に書いた手紙が見つかった。「毎日毎日心配で心配で、ぢつとして居られない」。22歳の大学生が遠隔地の恋人に、会えないもどかしさを切々と訴えていた。結局、恋は破れたが、婚約翌日に撮った写真が残っている。
そのときの光景が目に浮かぶ短編「雨傘」がある。霧雨のふる日、少年と少女が思い出にと写真館に立ち寄る。ぎこちない撮影のあとで、少女が先に表に出る。少年の傘を手にして、立っていた。来る道と違い、二人で入ると急に大人になった。夫婦のような気持ちがした。傘には、ほのかな喜び、幸福感がこもっていた。
その傘が香港では抵抗の象徴になっている。大学生、高校生などが先導する大規模デモは次期行政長官選挙での立候補制限への反発から始まった。政府が参加者を逮捕するなど強硬姿勢に転じたことで膠着が続く。降り注ぐ水、催涙弾を色鮮やかな傘の花が防いでいる。そこから運動は「雨傘革命」とも呼ばれ始めている。
返還から17年。中国の支配が強まるにつれ、自由が制限され、デモなどの動きに火がつく。英国と合意した30年前に事態は予想されていた(中嶋嶺雄「香港」)。だが、展開があまりに速い。50年保証した「高度の自治」も羊頭(ようとう)狗肉(くにく)だったらしい。民主派と政府が折り合い、同じ傘の下で、喜びを感じる日はまだ見えない。
冒頭の文は、次である。
> インド洋に突き出たスリランカ南部、港町ゴールのホテルで、持参した北欧系作家のミステリーの文庫を読んでいた
末尾の文は、次である。
> (読み手を暗い気持ちに陥らせる時代小説だけは書くまい) と思いながら、また夜明け前に起きての執筆暮らしに戻った。
書き出しの文段は、次のようである。
> インド洋に突き出たスリランカ南部、港町ゴールのホテルで、持参した北欧系作家のミステリーの文庫を読んでいた。四月のことだ。旅に出たのだ、活字から離れればよいものをつい読んでいた。北欧系ミステリー作家の作風がすべて北欧の冬の景色を思い浮かばせるように沈鬱で厳しいとは思わない。だが、読めば読むほどこちらの気持ちも萎えていき、光あふれる熱帯のゴールに居ながらにして交易時代の文化が積み重った砦(とりで)の町を散策する気になれなかった。なんともばかばかしい話だ。
末尾の文段は、次のようである。
>だが、釈然としない。活字にこだわってきた小説家が電子書籍にまで気を遣わねばならないのか。ゴールにいる数日間、結局答えは出なかった。
(読み手を暗い気持ちに陥らせる時代小説だけは書くまい)
と思いながら、また夜明け前に起きての執筆暮らしに戻った。
段落は、次のようである。
> 私は活字世界に生き残るために毎日書き続けた。三年目からは年間十二冊を超え、「月刊佐伯」と揶揄(やゆ)された。それでも、読者の一部の方は古き良き時代の雑誌連載、ハードカバーの流れを断ち切って、いきなり文庫化される時代小説を手にしてくれるようになった。分析すればいろいろと理由はあろう。
> 現在、私が文庫書下ろしに手を染めた当時の文庫観とは違う時代が到来していた。
> スリランカのゴールの話しに戻る。北欧ミステリーの小説に限らず欧米の小説家は、せいぜい年間一冊、精魂込めて集中して作品を仕上げると聞く。日本でも純文学系の作家は、全神経を尖(とが)らせて一作品を仕上げるのだろう。
2014/10/19付
日本経済新聞 朝刊
この夏、愛読者は興奮した。川端康成が初恋の女性に書いた手紙が見つかった。「毎日毎日心配で心配で、ぢつとして居られない」。22歳の大学生が遠隔地の恋人に、会えないもどかしさを切々と訴えていた。結局、恋は破れたが、婚約翌日に撮った写真が残っている。
そのときの光景が目に浮かぶ短編「雨傘」がある。霧雨のふる日、少年と少女が思い出にと写真館に立ち寄る。ぎこちない撮影のあとで、少女が先に表に出る。少年の傘を手にして、立っていた。来る道と違い、二人で入ると急に大人になった。夫婦のような気持ちがした。傘には、ほのかな喜び、幸福感がこもっていた。
その傘が香港では抵抗の象徴になっている。大学生、高校生などが先導する大規模デモは次期行政長官選挙での立候補制限への反発から始まった。政府が参加者を逮捕するなど強硬姿勢に転じたことで膠着が続く。降り注ぐ水、催涙弾を色鮮やかな傘の花が防いでいる。そこから運動は「雨傘革命」とも呼ばれ始めている。
返還から17年。中国の支配が強まるにつれ、自由が制限され、デモなどの動きに火がつく。英国と合意した30年前に事態は予想されていた(中嶋嶺雄「香港」)。だが、展開があまりに速い。50年保証した「高度の自治」も羊頭(ようとう)狗肉(くにく)だったらしい。民主派と政府が折り合い、同じ傘の下で、喜びを感じる日はまだ見えない。