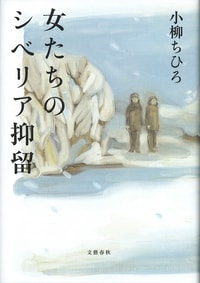従軍看護婦、電話交換手、民間人、受刑者……70年の沈黙を破って彼女たちが初めて語ったシベリア抑留、もう一つの歴史
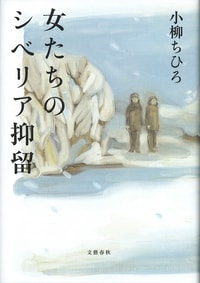 『女たちのシベリア抑留』(小柳ちひろ 著)
『女たちのシベリア抑留』(小柳ちひろ 著)
女性のシベリア抑留
「シベリアに女の人もいたんですか? 初めて聞きました」
「いや、シベリアに女はいないはずですよ」
一九四五年八月、日本の敗戦後、旧満州などから関東軍兵士らおよそ六〇万人がソ連やモンゴルの収容所に送られ、強制労働に従事させられた、いわゆる「シベリア抑留」。
その中に数百人の女性もいたという。
かつてシベリアに抑留された元兵士たちに、女性たちについて知っているか尋ねてみると、たいていの人が怪訝そうな顔をした。
だが中には抑留された女性について、わずかに見聞きしている人もいた。
細谷弘治さんは、満州国の首都新京(現在の長春)にあった満州国軍軍官学校に在籍中、終戦を迎え、シベリアに抑留された。
一七歳だった。満州国軍とは、満州国の建国とともに創設された軍隊で、“五族協和”を標榜し、漢族・満州族・朝鮮族・蒙古族で編成されていた。
日本人は、軍官学校を卒業した各民族の将校(軍官)とともに指揮官として従軍した。韓国の朴正煕元大統領も軍官学校の同窓の一人である。
細谷さんたち軍官学校の第七期生、三七五人のうち三一六人が抑留され、そのうち八六人が亡くなった。
細谷さんが送られたブカチャーチャの収容所に、一人の日本人女性がいた。
看護婦だと聞いていたが、直接言葉を交わしたこともなく、詳しいことはわからない。
細谷さんは、この女性がどういう経緯でシベリアに送られたのか、かねてから不思議に思っていたという。
永田潔さんは、入隊後、関東軍露語教育隊に配属され、ロシア語教育を受けて特務機関に在籍していた。
シベリアに抑留後まもなく裁判で刑を受け長期抑留を強いられた、いわゆる“戦犯”である。
終戦から一一年後、一九五六年に釈放され、帰国を果たした。
「シベリアに女の方も……?」
と切り出すと、
「ええ、いましたよ」
と、こともなげな返事が返ってきた。
永田さんの記憶に残っているのは、終戦から五年後、多くの抑留者が日本に帰国し、“戦犯”だけがソ連各地からハバロフスクの収容所に集められた頃、慰問団として楽団とともに収容所を訪れた歌手の女性だ。
終戦前までは樺太でドサ回りをしていたと聞いている。
笑うと出っ歯のため、花より先に葉が出る山桜になぞらえ「山桜嬢」と呼ばれていたが、本名は知らない。
「ソ連の奴らが自分らの慰安のために帰さないんですよ」
と苦々しげに語った言葉が妙に生々しかった。
千島列島の得撫島で終戦を迎えた元少尉の渡辺照造さんは、抑留中、女性がいるという噂を耳にした。
「ナホトカで女のアクチブがアジっているという話を聞いたんだよ。『なんでシベリアに女がいるんだ?』と思ったけどね」
“アクチブ”とは活動家を意味するロシア語で、「民主運動」と呼ばれる、シベリア抑留者たちに対して行われた共産主義の宣伝教育の旗振り役となった日本人を指す。
渡辺さんは、アクチブたちが糾弾の対象とした“反動将校”と見なされ、何度も激しい吊るし上げを経験している。
渡辺さんは当時を思い出したのか複雑な笑みを浮かべ、思い出したように席を立った。
「ああ、これにも載っているよ」
本棚から大きなハードカバーの本を取り出して来ると、慣れた手つきでページを繰り始めた。ソ連当局が日本人捕虜の思想教育のために発行した「日本新聞」の復刻版だ。
「これ、これ」
渡辺さんが示したページには、若い女性の似顔絵と、「在ソ中の皆様に」と題された、抑留者に決起を促す激しい言葉が並んでいた。
この女性の名はS子さんという。
抑留者の間で「ナホトカのジャンヌ・ダルク」と呼ばれていたと聞く。
のちに私は、S子さんの足跡を追うことになる。
戦後になってから、女性の元抑留者と交流があったという人もいた。
依田正一さんは、抑留者たち自身が編纂し、シベリア抑留の実態を知るための貴重な資料集となっている『捕虜体験記』(全八巻)の編集に関わった一人だ。
この時、体験記を寄せた元抑留者の中に、一人の女性がいた。
「兵器廠かどこかの軍属だとか言っていたな。ソ連軍が満州に入って来て避難する際、女だとわからないように軍服を着て男装していたために、員数合わせで連れて行かれたらしいんだよ」
依田さんは、同情極まりないという表情を浮かべて言った。
シベリア抑留を描いた画文集で有名な画家の佐藤清さんは、戦後「日独捕虜交歓会」という会合で、女性の元抑留者に出会った。
千島で捕えられた電話交換手だったという。
この地域の電話交換手と言えば、ソ連が侵攻した時、「これが最後です、さようなら」と言い残して自決した、樺太真岡郵便局の九人の乙女のエピソードが思い出される。
彼女たちも、自決していなければソ連軍の捕虜となっていたのだろうか。
「その人に『抑留された女の人はどれぐらいいるのですか?』と聞いたら、『一〇〇〇人ぐらいはいるんじゃないですか』と言っていましたよ。
確かなことはわかりませんがね。看護婦で抑留された人もいましたから、看護婦と交換手がいちばん多かったんじゃないかな。女性で抑留されたのは」
日本の敗戦後、満州や北朝鮮、樺太、千島列島から、ソ連、およびモンゴルの収容所に抑留された日本人は、厚生労働省の調べによれば、およそ五七万五〇〇〇人。
その中に「数百人の女性もいた」という事実は、シベリア抑留について総括的に書かれた書物の中で必ず触れられている。
しかし、女性たちがどのような経緯で抑留され、何を経験したのかについてはほとんど記述されていない。
シベリアに女性も抑留されたという事実は、多くの場合「女性すらも容赦なく連行した」ソ連の非道さを強調するための枕詞に留まっている。
なぜ、女性たちの存在は忘れられてしまったのか。誰かが意図的にその存在を隠したのか。それとも、誰も注意を払わなかっただけなのか。
歴史から消された女性たち
実は私自身も、女性抑留者の存在に気付きながら、その前を素通りしたことがある。
テレビドキュメンタリーのディレクターである私が初めてシベリア抑留について取材することになったのは、二〇一〇年にNHKスペシャル「引き裂かれた歳月 証言記録シベリア抑留」の制作に携わった時のことだ。
その時、ロシア取材を担当していた栗田和久ディレクターが持ち帰った、ある地方公文書館に所蔵されているアルバムの複写を見た。アルバムは、収容所当局が日本人抑留者を撮影した写真を収めたものだ。収容所当局と日本人の良好な関係を強調した、多分にプロパガンダ色の濃いものだったが、その中に、日本への帰国を前に整列する女性抑留者たちの写真があった。ロシア語で「ナホトカのアクチブたち」と手書きのキャプションがついたページには、数人の若い兵士たちに混じり、溌剌とした笑顔を見せているおさげ髪の若い女性もいた。名前を確かめると、前述の「ナホトカのジャンヌ・ダルク」と呼ばれたS子さんだった。彼女の名前は、全国抑留者補償協議会を結成し初代会長を務めた斎藤六郎氏の著作にも登場する。
「女性もソ連の捕虜になったのか。どれほど苦労したことだろう」とその時思った。
しかし、この時の取材のテーマは、シベリアの民主運動と、それによって引き裂かれた日本人抑留者たちの対立を浮かび上がらせることだった。
限られた取材期間の中で、なすべきことは山ほどある。
なぜ民主運動が日本人抑留者の間に広がったのか。運動を主導したのは誰か。
五七万人もの人々が体験した巨大な時代の潮流を、約五〇分のストーリーにまとめるためには、最大公約数的な体験を描くための情報収集を優先せざるを得ない。
女性抑留者は民主運動の根幹に関わった存在ではない。それゆえ女性の抑留という特異な側面を盛り込むことは難しいと思われた。
それに、女性でありながらソ連の捕虜になった人たちにとって、抑留生活は忘れたい記憶に違いない。
現在、どこかで静かに人生の最晩年を過ごしている彼女たちを探し出し、当時を語って欲しいと望むこと自体、取材とはいえ、あまりにも失礼なのではないだろうか──。
シベリア民主運動の取材は非常に難しかった。抑留当時、アクチブとして共産主義に傾倒していたはずの多くの人が、取材の申し込みに対し、狼狽し、平静さを失った。
多くの人は、シベリアの収容所という異常な環境で、イデオロギーに熱狂した自らの過去を恥じているように感じられた。
ロシアの地方公文書館に残るアルバムの中で、無邪気に笑っている「ナホトカのジャンヌ・ダルク」ことS子さんもまた、当時の記憶を忘れたいと思っているかもしれなかった。
しかし、その後も数年にわたり、あの戦争の時代に生きた人々の取材を続ける中で、忘れられた女性たちの存在が気になってきた。
戦争について取材する場合、対象者の多くは男性である。しかし時折、男性たちの妻や姉妹など、女性たちの話を聞くと、はっとするような真実が立ち現れる瞬間があった。
女性たちが自ら語り、書き残した記録は非常に少ない。
そして歴史について書かれた書物も、多くは男性の書き手によるもので、女性たちを描くために割かれているページは少ない。
だからこそ、女性たちの存在に気付いた者がその声を聞き、記録を残さなければ、彼女たちの存在は消えてしまうのではないか。
私は、シベリアに抑留された女性たちを探すことにした。
二〇一四年一月から取材を開始し、手がかりが見つからないまま、あっという間に二か月が過ぎた。ようやく一人の女性元抑留者に会えたのは、三月九日のことだった。