落語「酢豆腐」にでてくる“かくやのこうこ”のかくやって何?
銭のない町内の若い連中が、かくやのこうこ(覚弥の香々)で一杯やろうとします。
糠漬けをかき回すのは誰か。食べたいが糠漬けに手を入れるのは嫌な連中は、いろいろ言い訳をします。
香々はお漬物ですが、「かくや」とは何か。
覚弥とは、刻んだ漬物をいう。みそ漬、たくあん、ねか漬などの古漬を刻んで水にさらし、酒、醤油などをかけて食べる。
江戸時代の初め、東照公の料理人岩下覚彌の創始(随・松屋筆記)とも、高野山の隔夜堂を守る歯の弱い老僧のために作られたものから(随・柳亭記)ともいう。“隔夜”堂で、“かくや”か。
銭のない町内の若い連中が、かくやのこうこ(覚弥の香々)で一杯やろうとします。
糠漬けをかき回すのは誰か。食べたいが糠漬けに手を入れるのは嫌な連中は、いろいろ言い訳をします。
香々はお漬物ですが、「かくや」とは何か。
覚弥とは、刻んだ漬物をいう。みそ漬、たくあん、ねか漬などの古漬を刻んで水にさらし、酒、醤油などをかけて食べる。
江戸時代の初め、東照公の料理人岩下覚彌の創始(随・松屋筆記)とも、高野山の隔夜堂を守る歯の弱い老僧のために作られたものから(随・柳亭記)ともいう。“隔夜”堂で、“かくや”か。










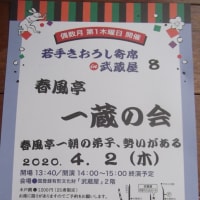

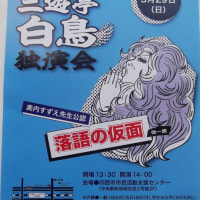
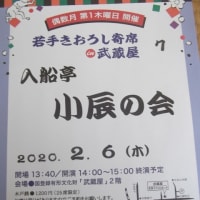
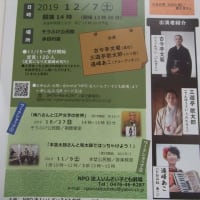
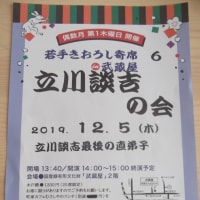
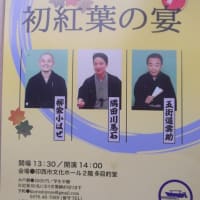
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます