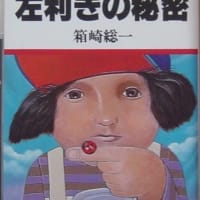いまさら説明するまでもないと思いますが、『まぐまぐ!』メルマガ大賞の教育部門で連続一位を続けている『親力で決まる子供の将来』の筆者で、他にも『ドラゴン桜』関係やあれやこれやで大活躍中の、元小学校教師の教育評論家・親野智可等先生の教育・子育てコラムです。
日経BPnet SAFETY JAPAN HOME >> コラム
第45回 左利きを直す必要はない 親野 智可等氏 2009年3月6日
内容は、以前、先のメルマガの連載記事やその書籍化『「親力」365日!』(宝島社)収録の<親力88>「左利きを右利きにする必要は、一切ない」等でもお書きになられていたことのおさらいです。
・・・
私の目についた点を見て行きましょう。
1 わたしは左利きを右利きに直す必要も両手利きにする必要も一切ないし、そうしてはいけないと考えている。
2 そもそも左利きを「直す」という言葉自体に、差別的発想がある。
3 左利きの子は左利きのまま育てた方が、自分の能力を十分に発揮できる。
4 「なぜ左利きの子だけ両手利きにならなければならないのか?」と考える必要がある。それは、決して子どもためにならないし、差別構造の温存につながるものでもあるのだ。
5 無理やり利き手を替えさせられたり両手利きにさせられたりすることには大きな弊害がある。
(子どもはコンプレックスを感じてしまう。/ 自信を喪失してしまう。/ 親子の良好な人間関係の形成を妨げることにもなる。/ ある種の良心の呵責を覚えさせてしまう。/ 大人に対して反発心を持つようになる。)
6 仮に左利きを右利きに替えることに成功したとしても、大人になって、コンプレックスや大人への不信感に悩まされている場合がかなりある。
7 左利きという個性をセールスポイントにするぐらいの気持ちで子育てしてほしいと思う。
8 実際、今の時代は「人と違う個性がセールスポイントになる時代」「自分の特色を最大限生かす時代」である。まず、子どもに左利きであることに自信を持たせてほしい。
9 右利きの人は驚くほど左利きの人への配慮がない。
10 まず、右利きの人が気づくことが第一歩なのだ。
11 左利きの人たちがどんどん発言すれば、社会の無神経さに右利きの人たちも気付く。そういう気付きが出てくれば、車椅子利用者、視覚障害者、聴覚障害者、老人、妊婦などに対する無神経さにも気付いてくるはずだ。根っこは同じ無神経さなのだから。
12 まず一人ひとりが、こんなことから心掛けたい。
(「ぎっちょ」という言葉を使わず、その代わりに「左利き」「サウスポー」「レフティ」を使う。/ 「おはしを持つ方が右手」と言われて混乱する。これも、左利きの人たちを全く無視した表現と言わざるを得ない。だから、「名札のある方が左」「名札のない方が右」などの言い方に替えていくといいだろう。特に幼稚園、保育園、小学校の教職員の皆さんには、このことを強くお願いしたい。)
13 企業関係者のみなさんに提案
(左利きも右利きも誰でも使えるユニバーサルデザインを意識した物づくりを進めてほしいのだ。/ ぜひ、左利きの人も右利きの人も同じように便利に使えるものを作ってほしい。それが無理なら、製品の1割は左利き仕様で作ってほしい。そこにビジネスチャンスもあるはずだ。)
・・・
基本的に私も同感です。
個々について、話したいことがいっぱいありますが、ここでは置いておきます。
今までにも、このブログや、メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』誌上でさんざん書いてきましたから。
(いずれ機会があれば、番号を振った各項目について書いてみるかもしれません。)
私自身一番大切なことは、その人が自分らしく自分本来の姿で、自分の才能を活かして、日々真っ当に生きることだ、と考えています。
左利き・右利きという性質も、一つの才能です。
左手・左足・左目といった左体側が得意な人、右手・右足・右目といった右体側が得意な人、ということです。
子供の才能を伸ばして、自分の力で生きてゆけるように導いてやるのが、親の務めでしょう。
そういうふうに考えれば、左利きの問題も何も難しいものではないのです。
もし子供が左利きだとわかったら、その才能を伸ばし、活かせるようにしてやればよいのですから。
例えば、
左手・左利き用の道具を与える。
左利き用の道具がない場合は(悲しいことですが、まだまだ左手・左利きが使用することを想定していない道具や機械がたくさんあるのです)、右手・右利き用をいかにすればうまく使えるようになるか、その技術や工夫を研究して伝授する。
その一方で、左利きでも不都合のないように、左右平等の社会に変えてゆくように努力する。
こういう製品を作って欲しいとメーカーに訴える。
こういう点を改めるべきだと、社会のシステムを改善する要望を出す。
―等々です。
左右平等の社会を一度築き上げてしまえば、自分の子供だけでなく、他の左利きの子供たちも、そのまた次の世代の左利きの子供たちも、苦労をすることなく生きてゆけるようになるのです。
私たちは、過去、多くの現実を変えてきました。
人間以外の多くの動植物は、環境に自分を合わせて生き延びてきました。
それに対して、人間は環境を変えることで、自分たちに適した社会を作り、ここまで繁栄してきたのです。
確かに、社会の在り方を変えるということは、一朝一夕にできることではありません。
しかし、そういう今日の地道な努力の積み重ねが、明日の幸せにつながってゆくのです。
左利き右利きの問題だけでなく、何事においても、「世の中が○○だから○○に」といった形で、社会の風潮やその時代の状況に合わせた、その場その時の世渡りをするのではなく、子供の意思や適性に合わせた、子供本意の生き方を考えてやるべきでしょう。
いつの時代でも生きてゆくのは、子供自身です。
親は所詮、子供が死ぬまで面倒見てやれません。
親であれ教師であれ、まずは、子供の才能を見極め、それぞれの持ち味を活かした生き方ができるように導いてあげて欲しいものです。
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より「左利きを直す必要はない-親野智可等『父親のための親力養成塾』第45回」を転載したものです。
---
 ◆「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」
◆「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」
―左利きの人、左利きに興味のある人のためのメールマガジン発行中! 創刊三周年!!
「登録及び解除(配信中止)」は、こちら↓
左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii(レフティやすおの左組通信メールマガジン)
「最新号」は、こちら
* 渡瀬けん/著『左利きの人々』中経の文庫(2008.12)「参考サイトその他」欄に掲載されました!(『レフティやすおの本屋』)
* 親野智可等・発行「親力で決まる子供の将来」No913 2007/12/26号で紹介されました!
*『R25』2007.12.06(No.170)"ランキンレビュー"「右利きが左利きより多いのはなぜ?」で紹介されました!
◆◆古典の名著・名作を楽しむメルマガ「レフティやすおの楽しい読書」毎月発行!
「登録及び解除(配信中止)」は、こちら「レフティやすおの楽しい読書」、まぐまぐ!のページ
「最新号」は、こちら
◆◆◆左利きがメイン・テーマのブログ「レフティやすおのお茶でっせ」
* 『モノ・マガジン』2008.2.2号(No.598)「特集・左利きグッズ大図鑑」で紹介される!
* 日経BPnet SJ 親野智可等先生の連載コラム『父親のための親力養成塾』第45回 左利きを直す必要はないで紹介されました!
日経BPnet SAFETY JAPAN HOME >> コラム
第45回 左利きを直す必要はない 親野 智可等氏 2009年3月6日
内容は、以前、先のメルマガの連載記事やその書籍化『「親力」365日!』(宝島社)収録の<親力88>「左利きを右利きにする必要は、一切ない」等でもお書きになられていたことのおさらいです。
・・・
私の目についた点を見て行きましょう。
1 わたしは左利きを右利きに直す必要も両手利きにする必要も一切ないし、そうしてはいけないと考えている。
2 そもそも左利きを「直す」という言葉自体に、差別的発想がある。
3 左利きの子は左利きのまま育てた方が、自分の能力を十分に発揮できる。
4 「なぜ左利きの子だけ両手利きにならなければならないのか?」と考える必要がある。それは、決して子どもためにならないし、差別構造の温存につながるものでもあるのだ。
5 無理やり利き手を替えさせられたり両手利きにさせられたりすることには大きな弊害がある。
(子どもはコンプレックスを感じてしまう。/ 自信を喪失してしまう。/ 親子の良好な人間関係の形成を妨げることにもなる。/ ある種の良心の呵責を覚えさせてしまう。/ 大人に対して反発心を持つようになる。)
6 仮に左利きを右利きに替えることに成功したとしても、大人になって、コンプレックスや大人への不信感に悩まされている場合がかなりある。
7 左利きという個性をセールスポイントにするぐらいの気持ちで子育てしてほしいと思う。
8 実際、今の時代は「人と違う個性がセールスポイントになる時代」「自分の特色を最大限生かす時代」である。まず、子どもに左利きであることに自信を持たせてほしい。
9 右利きの人は驚くほど左利きの人への配慮がない。
10 まず、右利きの人が気づくことが第一歩なのだ。
11 左利きの人たちがどんどん発言すれば、社会の無神経さに右利きの人たちも気付く。そういう気付きが出てくれば、車椅子利用者、視覚障害者、聴覚障害者、老人、妊婦などに対する無神経さにも気付いてくるはずだ。根っこは同じ無神経さなのだから。
12 まず一人ひとりが、こんなことから心掛けたい。
(「ぎっちょ」という言葉を使わず、その代わりに「左利き」「サウスポー」「レフティ」を使う。/ 「おはしを持つ方が右手」と言われて混乱する。これも、左利きの人たちを全く無視した表現と言わざるを得ない。だから、「名札のある方が左」「名札のない方が右」などの言い方に替えていくといいだろう。特に幼稚園、保育園、小学校の教職員の皆さんには、このことを強くお願いしたい。)
13 企業関係者のみなさんに提案
(左利きも右利きも誰でも使えるユニバーサルデザインを意識した物づくりを進めてほしいのだ。/ ぜひ、左利きの人も右利きの人も同じように便利に使えるものを作ってほしい。それが無理なら、製品の1割は左利き仕様で作ってほしい。そこにビジネスチャンスもあるはずだ。)
・・・
基本的に私も同感です。
個々について、話したいことがいっぱいありますが、ここでは置いておきます。
今までにも、このブログや、メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』誌上でさんざん書いてきましたから。
(いずれ機会があれば、番号を振った各項目について書いてみるかもしれません。)
私自身一番大切なことは、その人が自分らしく自分本来の姿で、自分の才能を活かして、日々真っ当に生きることだ、と考えています。
左利き・右利きという性質も、一つの才能です。
左手・左足・左目といった左体側が得意な人、右手・右足・右目といった右体側が得意な人、ということです。
子供の才能を伸ばして、自分の力で生きてゆけるように導いてやるのが、親の務めでしょう。
そういうふうに考えれば、左利きの問題も何も難しいものではないのです。
もし子供が左利きだとわかったら、その才能を伸ばし、活かせるようにしてやればよいのですから。
例えば、
左手・左利き用の道具を与える。
左利き用の道具がない場合は(悲しいことですが、まだまだ左手・左利きが使用することを想定していない道具や機械がたくさんあるのです)、右手・右利き用をいかにすればうまく使えるようになるか、その技術や工夫を研究して伝授する。
その一方で、左利きでも不都合のないように、左右平等の社会に変えてゆくように努力する。
こういう製品を作って欲しいとメーカーに訴える。
こういう点を改めるべきだと、社会のシステムを改善する要望を出す。
―等々です。
左右平等の社会を一度築き上げてしまえば、自分の子供だけでなく、他の左利きの子供たちも、そのまた次の世代の左利きの子供たちも、苦労をすることなく生きてゆけるようになるのです。
私たちは、過去、多くの現実を変えてきました。
人間以外の多くの動植物は、環境に自分を合わせて生き延びてきました。
それに対して、人間は環境を変えることで、自分たちに適した社会を作り、ここまで繁栄してきたのです。
確かに、社会の在り方を変えるということは、一朝一夕にできることではありません。
しかし、そういう今日の地道な努力の積み重ねが、明日の幸せにつながってゆくのです。
左利き右利きの問題だけでなく、何事においても、「世の中が○○だから○○に」といった形で、社会の風潮やその時代の状況に合わせた、その場その時の世渡りをするのではなく、子供の意思や適性に合わせた、子供本意の生き方を考えてやるべきでしょう。
いつの時代でも生きてゆくのは、子供自身です。
親は所詮、子供が死ぬまで面倒見てやれません。
親であれ教師であれ、まずは、子供の才能を見極め、それぞれの持ち味を活かした生き方ができるように導いてあげて欲しいものです。
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より「左利きを直す必要はない-親野智可等『父親のための親力養成塾』第45回」を転載したものです。
---
 ◆「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」
◆「左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii」―左利きの人、左利きに興味のある人のためのメールマガジン発行中! 創刊三周年!!
「登録及び解除(配信中止)」は、こちら↓
左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii(レフティやすおの左組通信メールマガジン)
「最新号」は、こちら
* 渡瀬けん/著『左利きの人々』中経の文庫(2008.12)「参考サイトその他」欄に掲載されました!(『レフティやすおの本屋』)
* 親野智可等・発行「親力で決まる子供の将来」No913 2007/12/26号で紹介されました!
*『R25』2007.12.06(No.170)"ランキンレビュー"「右利きが左利きより多いのはなぜ?」で紹介されました!
◆◆古典の名著・名作を楽しむメルマガ「レフティやすおの楽しい読書」毎月発行!
「登録及び解除(配信中止)」は、こちら「レフティやすおの楽しい読書」、まぐまぐ!のページ
「最新号」は、こちら
◆◆◆左利きがメイン・テーマのブログ「レフティやすおのお茶でっせ」
* 『モノ・マガジン』2008.2.2号(No.598)「特集・左利きグッズ大図鑑」で紹介される!
* 日経BPnet SJ 親野智可等先生の連載コラム『父親のための親力養成塾』第45回 左利きを直す必要はないで紹介されました!










![[コラボ]<左利きミステリ>第6回海外編(前)新規発見作-週刊ヒッキイ第680号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/50/0b/d9ba852c5783b88f7be207a9fce5daaa.jpg)
![[コラボ]<左利きミステリ>第6回海外編(前)新規発見作-週刊ヒッキイ第680号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7f/33/9916e472f5bff0e4d120e8e7560bbb67.jpg)
![[コラボ]<左利きミステリ>第6回海外編(前)新規発見作-週刊ヒッキイ第680号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7b/ec/5e39035345e1fe280f098cfe99b84505.jpg)
![[コラボ]<左利きミステリ>第6回海外編(前)新規発見作-週刊ヒッキイ第680号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/6d/6b1be2f6324a79c00fc758708d86c253.jpg)