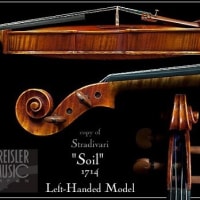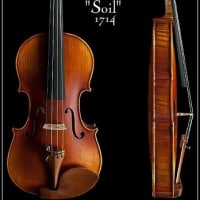今、親野智可等先生の人気教育メルマガ『親力で決まる子供の将来』で、「親力147・・・子どもの人生は子どものもの」が連載されています。
※『親力で決まる子供の将来』
・2006/9/20・・No686~「親力147・・・子どもの人生は子どものもの」
・最新号
今、マスコミで盛んに持ち上げているスポーツ界の親子鷹とも言うべき人たちの「○○家の子育て」に関して、教育者として注意を促されています。
これらはあくまでもひとつの成功例であり、その裏には数々の報道されない後悔が渦巻いているものであり、そのまま受け取るのは危険だというのです。
その失敗例として、奈良の家族3人放火殺人事件や、絵が好きだった男の子の例、なんでもよくできた女の子の例を挙げておられます。
習い事をいっぱいやっていた少女は、五年になった時、学校に来なくなりました。
それまで、全てにおいて模範的ないい子で「いや」とか「やめたい」などと言ったことがなかったのが、です。
親の方には、子どもに無理をさせているとか押しつけているという意識は全くなかったのです。
しかし、とうとう限界が来てしまったのです。
そして、こういう子が今たくさんいる、と親野先生は言います。
親は気をつける必要がある。
無理に過剰な要求をしているつもりがなくても、結果的にそうなっていることもある、と。
ここには「親の強い思いの押しつけ」、「子どもの意思、特質、能力の無視」とのふたつの問題点がある、と指摘されています。
なぜそんなことになるのか、その理由は―
「自分の夢や願いを子どもに託す親がいる」、「それがこの子のためだと親が思っている」から。
例え愛情から出たものであっても、これらは「子どもの人生を奪うこと」なのです、と。
この連載は、まだ続いています。
私の感想を、先生への返信から引用しておきます。
------
「子どもの人生は子どものもの」毎回興味深く拝読しております。
私はつい何事も左利きに結び付けて考えてしまうのですが、今回のテーマもまた左利きの子供に対する教育に当てはまります。
右利きの親御さんが、左利きのお子さんに右手を使わせようとする気持ちになるのは、その子のその後の人生において、左手を使うより右手を使うほうが便利で、日常生活が楽になるのではないか、という考えによるようです。
特に書字において、その考えが根強くあるように思われます。
他のことは左手使いでもよしとする人でも字だけは右手でないと書きにくいのではないか、なかでも毛筆習字に関しては、これは絶対左手では書けない、右手でないときれいに書けない、という考えが強いようです。
しかも、左利きの親御さんのなかにもこの考えを持つ人がいます。
自分が左手書字で苦労したから、子供は小さいときからやれば慣れるだろう、と右手書字を強いる人がいます。
子供の意見を尊重しているという親御さんのなかにも、本当に子供の自発的な意思を確認できているかどうか、はなはだ怪しい場合もあるような気がします。
親は子供の笑顔を見るのが好きです。
しかし、子供というものは、親が子の笑顔を見たいと思う以上に、親の喜ぶ顔を見たいものなのです。
そして、親の求めにできるだけ応えたいと思うものです。
私のもとに持ち込まれた相談のなかにも、お父さんが強く右手を使うように言うので、というお子さんがいました。
最終的に、お父さんが、もういいんだよ、自分の使いたいほうの手を使えばいいんだよ、と子供さんに話して解決に至ったと聞いています。
私自身もそうでした。
私は学校の先生になりたかった時期がありました。
でも、経済的な事情もあり、自分の知っている世界に進んで欲しいという親の希望もあり、私も物作りは好きな方だったので、大学はあきらめて工業高校に進みました。
15歳は子供ではないと思われるかもしれません。しかし、今の私から見れば、本当に子供です。
子供が自分の意志を貫くのはなかなかむずかしいものです。
今私は、結局のところ、次善の道を進むのは最善の道が閉ざされてからでもよいのではないか、と考えるようになりました。
まずは自分の一番を求め、それがどうにもならないとわかってから、次善の策を練れば良いと思います。
>なぜなら、子どもの人生は子どものものだからです。
>誰にも自分の人生を自分で決める生得の権利があるのです。
>子どもの内に秘めている意思を引き出してやることこそ、親のやるべきことです。
まさにその通りだと思います。
「子どもの人生は子どものもの」という考えを持って、正しく子供の教育に当たって行けば、このような問題もクリアできるのではないか、と私も考えています。
なかなかむずかしいことですが、必ずやらねばならないことです。
ヘレン・ケラーの自伝に、教育についてこんなことが書いてありました。
「生徒が自ら進んで勉強するためには、勉強中も休憩中も、「自由」は自分の手の中にある、と感じなければならない。そして、自ら勝利の喜びと敗北の失望感を味わってはじめて、嫌いな課題でも本腰で取り組み、単調な教科書の勉強も、勇気を持って楽しくやり抜こう、と決心できるのだ。」(『奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝』小倉慶郎訳 新潮文庫)
子供の人生の教育も同じことだと思います。
自分で選択できる自由がある、という実感を子供が持てなくてはいけません。
日本の子供は、特に大人の顔色をうかがう傾向が強い、と子供の発育を研究している専門家は言います。
これは、心に留め置く必要がある、と思います。
また、思いのたけを長々とつづってしまい、失礼いたしました。
では、続きを楽しみにしております。
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より「子供に自分で選択できる自由の実感を:メルマガ『親力で―』から」を転載したものです。
※『親力で決まる子供の将来』
・2006/9/20・・No686~「親力147・・・子どもの人生は子どものもの」
・最新号
今、マスコミで盛んに持ち上げているスポーツ界の親子鷹とも言うべき人たちの「○○家の子育て」に関して、教育者として注意を促されています。
これらはあくまでもひとつの成功例であり、その裏には数々の報道されない後悔が渦巻いているものであり、そのまま受け取るのは危険だというのです。
その失敗例として、奈良の家族3人放火殺人事件や、絵が好きだった男の子の例、なんでもよくできた女の子の例を挙げておられます。
習い事をいっぱいやっていた少女は、五年になった時、学校に来なくなりました。
それまで、全てにおいて模範的ないい子で「いや」とか「やめたい」などと言ったことがなかったのが、です。
親の方には、子どもに無理をさせているとか押しつけているという意識は全くなかったのです。
しかし、とうとう限界が来てしまったのです。
そして、こういう子が今たくさんいる、と親野先生は言います。
親は気をつける必要がある。
無理に過剰な要求をしているつもりがなくても、結果的にそうなっていることもある、と。
ここには「親の強い思いの押しつけ」、「子どもの意思、特質、能力の無視」とのふたつの問題点がある、と指摘されています。
なぜそんなことになるのか、その理由は―
「自分の夢や願いを子どもに託す親がいる」、「それがこの子のためだと親が思っている」から。
例え愛情から出たものであっても、これらは「子どもの人生を奪うこと」なのです、と。
「子どもは、親の強い思いを見せられると、なかなか「いや」と言えないものなのです。・・・
親を愛していますし、親を喜ばせたいとも思っています。
親をがっかりさせたくないという気持ちは、子どもならみんな持っています。
ですから、「いや」と言わないからといって、だいじょうぶということにはならないのです。」
この連載は、まだ続いています。
私の感想を、先生への返信から引用しておきます。
------
「子どもの人生は子どものもの」毎回興味深く拝読しております。
私はつい何事も左利きに結び付けて考えてしまうのですが、今回のテーマもまた左利きの子供に対する教育に当てはまります。
右利きの親御さんが、左利きのお子さんに右手を使わせようとする気持ちになるのは、その子のその後の人生において、左手を使うより右手を使うほうが便利で、日常生活が楽になるのではないか、という考えによるようです。
特に書字において、その考えが根強くあるように思われます。
他のことは左手使いでもよしとする人でも字だけは右手でないと書きにくいのではないか、なかでも毛筆習字に関しては、これは絶対左手では書けない、右手でないときれいに書けない、という考えが強いようです。
しかも、左利きの親御さんのなかにもこの考えを持つ人がいます。
自分が左手書字で苦労したから、子供は小さいときからやれば慣れるだろう、と右手書字を強いる人がいます。
子供の意見を尊重しているという親御さんのなかにも、本当に子供の自発的な意思を確認できているかどうか、はなはだ怪しい場合もあるような気がします。
親は子供の笑顔を見るのが好きです。
しかし、子供というものは、親が子の笑顔を見たいと思う以上に、親の喜ぶ顔を見たいものなのです。
そして、親の求めにできるだけ応えたいと思うものです。
私のもとに持ち込まれた相談のなかにも、お父さんが強く右手を使うように言うので、というお子さんがいました。
最終的に、お父さんが、もういいんだよ、自分の使いたいほうの手を使えばいいんだよ、と子供さんに話して解決に至ったと聞いています。
私自身もそうでした。
私は学校の先生になりたかった時期がありました。
でも、経済的な事情もあり、自分の知っている世界に進んで欲しいという親の希望もあり、私も物作りは好きな方だったので、大学はあきらめて工業高校に進みました。
15歳は子供ではないと思われるかもしれません。しかし、今の私から見れば、本当に子供です。
子供が自分の意志を貫くのはなかなかむずかしいものです。
今私は、結局のところ、次善の道を進むのは最善の道が閉ざされてからでもよいのではないか、と考えるようになりました。
まずは自分の一番を求め、それがどうにもならないとわかってから、次善の策を練れば良いと思います。
>なぜなら、子どもの人生は子どものものだからです。
>誰にも自分の人生を自分で決める生得の権利があるのです。
>子どもの内に秘めている意思を引き出してやることこそ、親のやるべきことです。
まさにその通りだと思います。
「子どもの人生は子どものもの」という考えを持って、正しく子供の教育に当たって行けば、このような問題もクリアできるのではないか、と私も考えています。
なかなかむずかしいことですが、必ずやらねばならないことです。
ヘレン・ケラーの自伝に、教育についてこんなことが書いてありました。
「生徒が自ら進んで勉強するためには、勉強中も休憩中も、「自由」は自分の手の中にある、と感じなければならない。そして、自ら勝利の喜びと敗北の失望感を味わってはじめて、嫌いな課題でも本腰で取り組み、単調な教科書の勉強も、勇気を持って楽しくやり抜こう、と決心できるのだ。」(『奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝』小倉慶郎訳 新潮文庫)
子供の人生の教育も同じことだと思います。
自分で選択できる自由がある、という実感を子供が持てなくてはいけません。
日本の子供は、特に大人の顔色をうかがう傾向が強い、と子供の発育を研究している専門家は言います。
これは、心に留め置く必要がある、と思います。
また、思いのたけを長々とつづってしまい、失礼いたしました。
では、続きを楽しみにしております。
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より「子供に自分で選択できる自由の実感を:メルマガ『親力で―』から」を転載したものです。