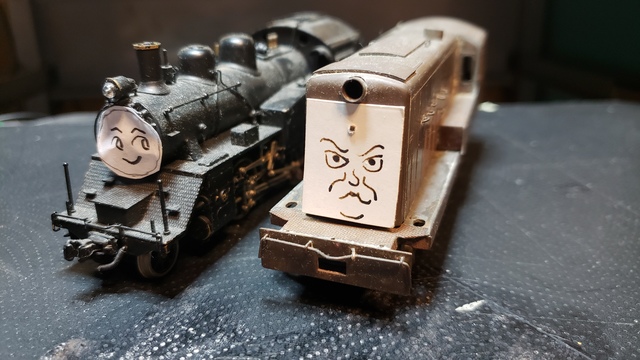おはようございます。
関東地方、今朝またまた水曜日の雪 の予報でしたが、たいしたことはなさそうなのでよかったです。
の予報でしたが、たいしたことはなさそうなのでよかったです。
さて、はじめます。
次の工作はなにを始めるかちょっと考えている間につなぎです。
以前に買ってタンスの肥やしになっていたブロクソン製フレキシブルシャフトを試してみます。
ケースを開け中身をチェック!
スタンドにシャフトにL型棒に固定用クランプと入っています。
スタンドの裏側に、円盤をビスで回転軸を取り付けます。
固定用クランプにてデスクに固定し、
ルーター本体を蝶ネジにて固定し、
シャフトを本体に接続すれば出来上がりです。
先端部は、いろいろ持ってます。
一番小さい丸を使ってみます。
不要なアルミ細板に文字をマーキングし、
慎重に削ったつもりが小学生の版画みたいになってしまいました。
時間もかかり甘くないですね、熟練が必要なわけです。
あ~フライス盤ほしなあ~
おはようございます。
さて、昨日はちょっと嗜好をかえまして、ワタクシの所属するオープンカーのクラブのツーリングに参加してきました。
関東近辺が主な活動場所なのですが、毎月行先を変えまして今回は栃木県は芳賀郡方面という事で、完全な幽霊部員となっていた私も参加した次第です。
まずは、こんなところを訪れ
こんなところで、昼食を摂りました。
途中でおせんべを焼いたり、
イチゴを摘んだりしました。
ほとんど食ってばかりですね
で、鉄分といえば
昼食場所の駐車場の策に使われている枕木と、
みんなで撮った真岡鉄道のSL列車ぐらいです。
もっとも私は、いつでも撮れるのでしっかりと人間観察させていただきました。
みなさんSL見て、結構喜ぶものなんですね
 天気は良かったのですが、風が強く冷たかったのでオープンカーにはちょっと適しませんでしたが、よい思い出作りができました。
天気は良かったのですが、風が強く冷たかったのでオープンカーにはちょっと適しませんでしたが、よい思い出作りができました。
おはようございます。
九州で起きたバス事故の影響で、フェード現象やペーパーロック現象など若かりしころ自動車教習所にて覚えた言葉がゆきかってます。ブレーキが効かない時の対処方法のひとつとしてエンジンを切るというのがありましたが、今は機構的に切ってはいけないそうですね。
時代と共に変わるという事ですか、肝に銘じておきます。
さて、はじめます。
スノープロ―製作に取り掛かりました。当初0.2㎜真鍮板で罫書き曲げて作ろうとしましたがうまくいかず、結局2㎜×3㎜のアングルを使い簡単に作りました。
まあ、雰囲気は出ていると思います。
固定方法を考えるため、台車の上に乗せてみました。
車輪に触らないように前に出す必要があります。
さかさまにして、車輪踏み面と前の雪寄せの間にスケールをあててみました。
なんとか隙間が確認できます。
これで、直線で平らな所ならばレールに触らないですむでしょう。
と、思います。
つづく