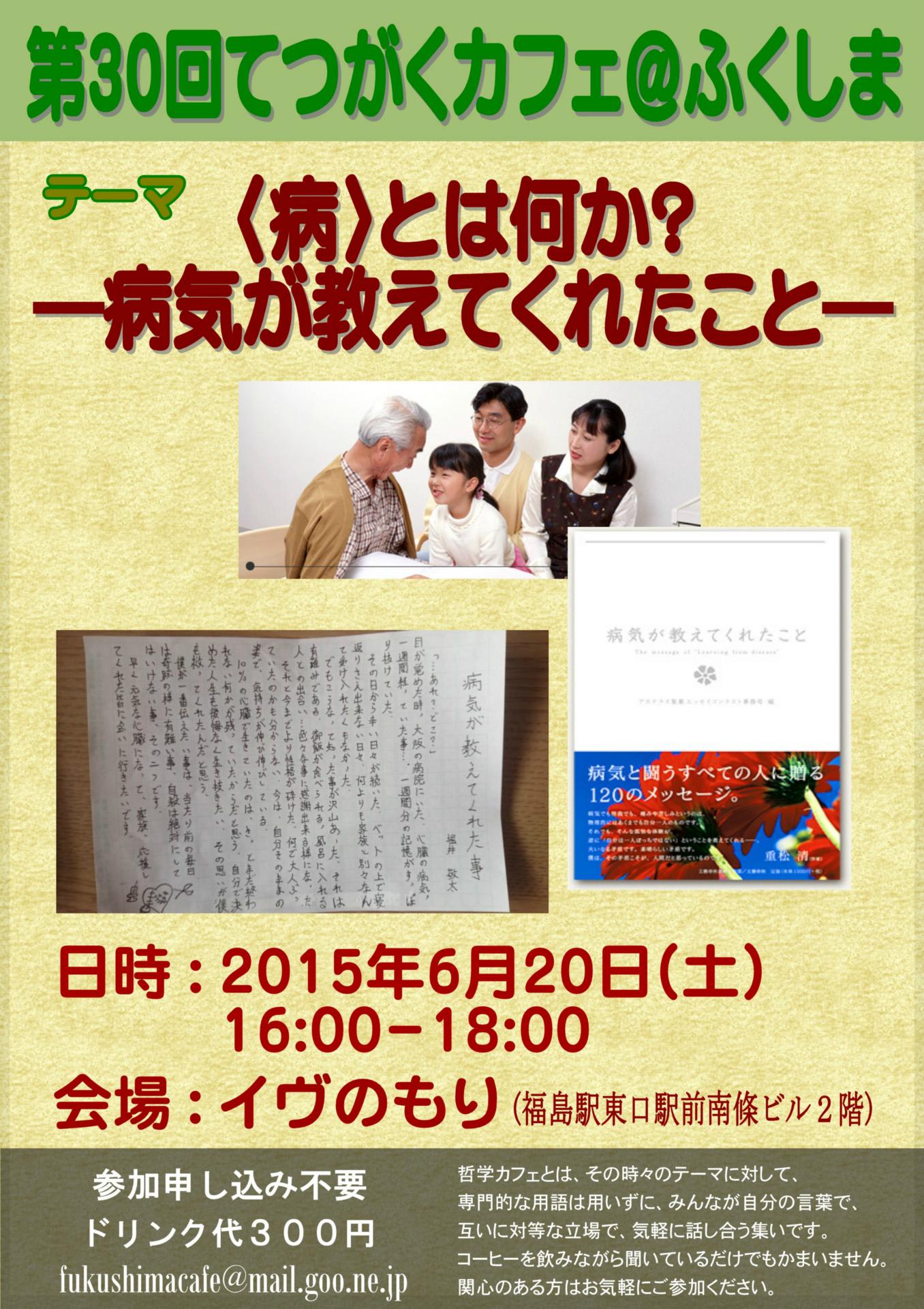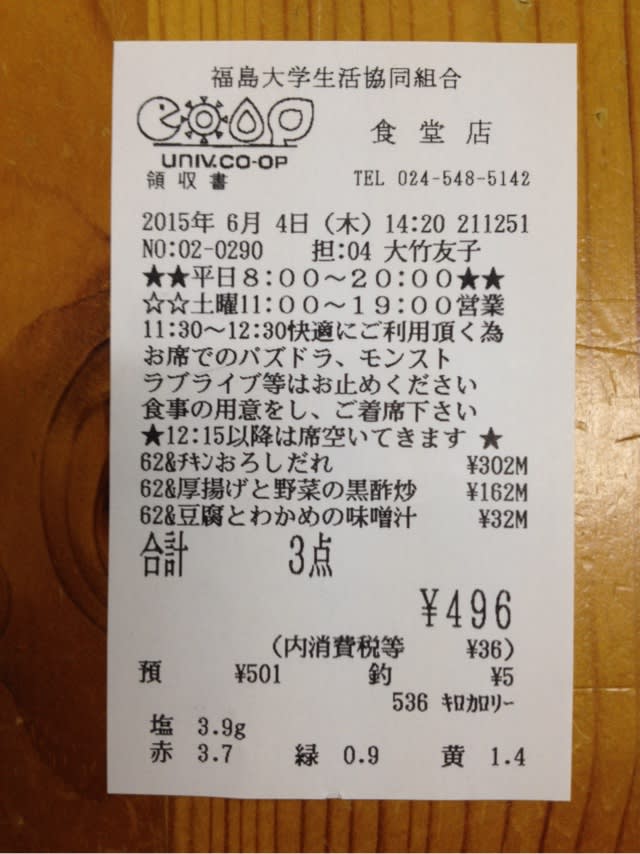川口高校での講演会では、次のような長い感想もいただいていました。
最後に質問が付されていたので、先日のブログではまだご紹介せず、
今日まで温存しておきました。
これも全文をご紹介しましょう。
「今日の講演は僕にとってとても興味深いものでした。
特に印象的だったのが、学ぶ事に対して根本的な部分から、
つまり、サル、猿人の時代から考察していく所です。
僕も勉強やそれ以外の事に関して根本的原理から考察する人間です。
というか好きです。
上記の方 [感想用紙の1番 (人はなぜ勉強しなくてはならないのだと思いますか?) の回答]
を見ていただければ分かると思います。
僕は今回、上記の事を書いた上で先生の講演を聞いたとき、とても驚きました。
僕の考え方に近い考え方をしていたからです。
僕は担任の先生 (林裕文先生) とよく話しますが、「哲学的」 だとよく言われていました。
そのせいか先生の講演はとても共感できました。
僕も大学を進路に考えている人間なのでがんばっていますが勉強はできません。はい。
そんでもって文系か理系かの偏りがないです。
というのも 「僕、全教科できすぎて偏りないからどっち行こうか迷ってんだよね~」
という感じではなく (むしろこうなりたい)、社会、国語はできるが英語がダメ、
理科は得意だが数学がダメといった感じです。どうすればいいでしょうか?」
ちなみに1番の質問 (人はなぜ勉強しなくてはならないのだと思いますか?) には、
以下のように答えてくれていました。
「人は古来より他の動物たちのような高い身体能力や筋力がなく、
自然界では圧倒的に弱き種ではあったと思いますが、
造物主より唯一与えられた産物が高い知的能力だったと思います。
生物とは自らの持つ能力を駆使し、成長させ、高めて生きていくものだと思います。
僕は人間である以上、その人間という種がもつ能力の向上のために勉強と向きあっています。」
どうです。
すっごいでしょう。
「おまいはオレか?」 と言いたくなるくらいです。
わざわざ私が金山町まで出向かずとも、彼に講演してもらえばよかったのではないか、と思います。
これだけ考え方が似ていると、私の講演を聞かずともわかりきった話ばかりだったかもしれませんが、
共感をもって聞いていただけたようで、それはたいへんよかったです。
そういう方から質問をいただいてしまったのでお答えしないわけにはいきません。
「Q.文系・理系の偏りがないのですが、どうすればいいでしょうか?」
なるほど。
深刻な問題ですね。
個人的には文系・理系というくくりが大雑把すぎると思っているので、
自分の得意な教科をガンガン伸ばせばいいんじゃないと言いたくなりますが、
大学受験ということを視野に入れると、そういうわけにもいかないのでしょう。
さて、どうすればいいのでしょうか?
要するに英語と数学が苦手なんですね。
この2つってある種、似ているところがあるかもしれません。
実は私、大学に就職するまでは学習塾でバイトをしていましたが、
中学生相手に英語と数学を教えていました。
大学受験のころ私は文系で英語はまあ得意科目でしたが、
数学はお世辞にも得意と言えるような状態ではありませんでした。
それがなぜ塾で数学を教えようと思ったのか?
人に教えようと思うと数学って教えるのは簡単なんですよ。
公式とか、要するに解き方の原理を教えて、あとは例題を解かせればいいだけなので。
社会とか国語ってそういう解き方の公式があるわけじゃなくて、
いろいろなことをイチから全部説明してあげなきゃいけないじゃないですか。
たくさんの言葉を暗記もしてもらわなきゃいけないし。
数学って意外と覚えること少ないんですよね。
逆に英語はものすごく数学に似ているところがあります。
本格的な小説とかを読むとまた違ってくるんだろうけど、
大学受験までの英語って基本的に口語調ではなく、
きちんと主語、述語、目的語、補語などが文法通りに正しく並べられている文章が中心だし、
内容も論説文が多いので、とても論理的にきちんと意味が取れるように構成されていて、
単語の意味さえ知っていれば、
あとは数学の問題を解くようにクリアに答えが導き出せるようになっている場合がほとんどです。
だからぼくのような教育の素人でも、英語と数学なら何とか教えることができたのです。
さて、質問者の方は英語と数学のどこが苦手なのでしょうか?
パズルとか苦手?
ぼくは英語と数学はパズルと一緒で、正しく考えていけば必ず正解が出る、
思考の訓練としては一番初歩的な教科だと思っています。
逆に、国語や社会や理科のどういうところが得意なのでしょうか?
たくさんの事柄を暗記するのが苦にならないタイプなんですか?
それともそれらの3教科は常識で答えられる感じ?
あるいは、正解がひとつだけ存在するとは限らない高度な問題を扱うところが好きですか?
いずれにせよ、国語、社会、理科ができるのであれば、
英語と数学は楽勝でやっつけられると思うよ。
たんに苦手意識をもっちゃってるから上手くいかないだけで、
それら2教科はただのパズルだということさえわかればまったく怖くなくなります。
ひとつアドバイスするとすれば、パズルを解くにはパズルのルールを、
初歩的なルールから順番に全部ちゃんと知っておかなくてはなりません。
高度で複雑なルールというのは、基本の初歩的なルールの積み重ねの上に作られているので、
一度どこかでつまずいてしまうと、そこから先には絶対に進めないようになっています。
だから、自分がどこでつまずいてしまったのかをさかのぼって発見するのが大事です。
高1レベルでつまずいたのかもしれないし、
ひょっとすると中学校のどこかでつまずいたのかもしれません。
そのときには恥ずかしがったり面倒くさがったりすることなく、
つまずいたところまでちゃんと戻ってやり直すことが必要です。
それを怠っていると、いくら先に進もうとしても絶対にうまくいきません。
ぼくは高校1年生のときに数Ⅰでつまずいちゃったので、そのまま文系に進みましたが、
国立文系コースだったので受験前には数Ⅰをやり直す必要がありました。
高1のときの数学の授業では最初の因数分解からさっぱりわからなかったのに、
自分で参考書を使って順番にルールを覚えていったら、
ものすご~く簡単なのでビックリした覚えがあります。
高1のときの先生がまったく基礎・基本の説明とかをしてくれなくて、
すぐに問題を解かせるタイプだったのでそれで落ちこぼれてしまったのですが、
ちゃんとパズルのルールが理解できると、パズルはいとも簡単に解けるし、
自分で解けるとやっていて面白くなってくるし、
あの先生はなんでちゃんと教えてくれなかったんだろうと本当に頭に来たことがありました。
数学とか英語って人それぞれつまずくポイントが違いますので、
クラス全員にわからせるのはなかなか難しいです。
自分で自分のつまずきを発見するよう独学で基本からやり直してみるか、
先生に個別的に相談して自分がどこでつまずいているかを診断してもらうか、
いずれかを試してみるといいと思います。
英語、数学が克服できると、
「僕、全教科できすぎて偏りないからどっち行こうか迷ってんだよね~」状態になっちゃいますね。
素晴らしいと思います。
現代の複雑で高度な問題は、文系とか理系とかって分業していても解けない問題が増えています。
すべての学問が 「学際的」 にいろいろな分野と積極的に関わっていくことが求められています。
大学でもそういう文系とも理系とも分類できないような学問領域がどんどん創設されています。
例えばこの福島の状況も、文系の知識だけでも理系の知識だけでも解決できない、
高度に複雑に絡み合った問題群から構成されています。
そうした難問を解きほぐし、福島の人々のため、日本中の人々のため、
世界中の人々のために貢献できるカッコいい大人になってください!
最後に質問が付されていたので、先日のブログではまだご紹介せず、
今日まで温存しておきました。
これも全文をご紹介しましょう。
「今日の講演は僕にとってとても興味深いものでした。
特に印象的だったのが、学ぶ事に対して根本的な部分から、
つまり、サル、猿人の時代から考察していく所です。
僕も勉強やそれ以外の事に関して根本的原理から考察する人間です。
というか好きです。
上記の方 [感想用紙の1番 (人はなぜ勉強しなくてはならないのだと思いますか?) の回答]
を見ていただければ分かると思います。
僕は今回、上記の事を書いた上で先生の講演を聞いたとき、とても驚きました。
僕の考え方に近い考え方をしていたからです。
僕は担任の先生 (林裕文先生) とよく話しますが、「哲学的」 だとよく言われていました。
そのせいか先生の講演はとても共感できました。
僕も大学を進路に考えている人間なのでがんばっていますが勉強はできません。はい。
そんでもって文系か理系かの偏りがないです。
というのも 「僕、全教科できすぎて偏りないからどっち行こうか迷ってんだよね~」
という感じではなく (むしろこうなりたい)、社会、国語はできるが英語がダメ、
理科は得意だが数学がダメといった感じです。どうすればいいでしょうか?」
ちなみに1番の質問 (人はなぜ勉強しなくてはならないのだと思いますか?) には、
以下のように答えてくれていました。
「人は古来より他の動物たちのような高い身体能力や筋力がなく、
自然界では圧倒的に弱き種ではあったと思いますが、
造物主より唯一与えられた産物が高い知的能力だったと思います。
生物とは自らの持つ能力を駆使し、成長させ、高めて生きていくものだと思います。
僕は人間である以上、その人間という種がもつ能力の向上のために勉強と向きあっています。」
どうです。
すっごいでしょう。
「おまいはオレか?」 と言いたくなるくらいです。
わざわざ私が金山町まで出向かずとも、彼に講演してもらえばよかったのではないか、と思います。
これだけ考え方が似ていると、私の講演を聞かずともわかりきった話ばかりだったかもしれませんが、
共感をもって聞いていただけたようで、それはたいへんよかったです。
そういう方から質問をいただいてしまったのでお答えしないわけにはいきません。
「Q.文系・理系の偏りがないのですが、どうすればいいでしょうか?」
なるほど。
深刻な問題ですね。
個人的には文系・理系というくくりが大雑把すぎると思っているので、
自分の得意な教科をガンガン伸ばせばいいんじゃないと言いたくなりますが、
大学受験ということを視野に入れると、そういうわけにもいかないのでしょう。
さて、どうすればいいのでしょうか?
要するに英語と数学が苦手なんですね。
この2つってある種、似ているところがあるかもしれません。
実は私、大学に就職するまでは学習塾でバイトをしていましたが、
中学生相手に英語と数学を教えていました。
大学受験のころ私は文系で英語はまあ得意科目でしたが、
数学はお世辞にも得意と言えるような状態ではありませんでした。
それがなぜ塾で数学を教えようと思ったのか?
人に教えようと思うと数学って教えるのは簡単なんですよ。
公式とか、要するに解き方の原理を教えて、あとは例題を解かせればいいだけなので。
社会とか国語ってそういう解き方の公式があるわけじゃなくて、
いろいろなことをイチから全部説明してあげなきゃいけないじゃないですか。
たくさんの言葉を暗記もしてもらわなきゃいけないし。
数学って意外と覚えること少ないんですよね。
逆に英語はものすごく数学に似ているところがあります。
本格的な小説とかを読むとまた違ってくるんだろうけど、
大学受験までの英語って基本的に口語調ではなく、
きちんと主語、述語、目的語、補語などが文法通りに正しく並べられている文章が中心だし、
内容も論説文が多いので、とても論理的にきちんと意味が取れるように構成されていて、
単語の意味さえ知っていれば、
あとは数学の問題を解くようにクリアに答えが導き出せるようになっている場合がほとんどです。
だからぼくのような教育の素人でも、英語と数学なら何とか教えることができたのです。
さて、質問者の方は英語と数学のどこが苦手なのでしょうか?
パズルとか苦手?
ぼくは英語と数学はパズルと一緒で、正しく考えていけば必ず正解が出る、
思考の訓練としては一番初歩的な教科だと思っています。
逆に、国語や社会や理科のどういうところが得意なのでしょうか?
たくさんの事柄を暗記するのが苦にならないタイプなんですか?
それともそれらの3教科は常識で答えられる感じ?
あるいは、正解がひとつだけ存在するとは限らない高度な問題を扱うところが好きですか?
いずれにせよ、国語、社会、理科ができるのであれば、
英語と数学は楽勝でやっつけられると思うよ。
たんに苦手意識をもっちゃってるから上手くいかないだけで、
それら2教科はただのパズルだということさえわかればまったく怖くなくなります。
ひとつアドバイスするとすれば、パズルを解くにはパズルのルールを、
初歩的なルールから順番に全部ちゃんと知っておかなくてはなりません。
高度で複雑なルールというのは、基本の初歩的なルールの積み重ねの上に作られているので、
一度どこかでつまずいてしまうと、そこから先には絶対に進めないようになっています。
だから、自分がどこでつまずいてしまったのかをさかのぼって発見するのが大事です。
高1レベルでつまずいたのかもしれないし、
ひょっとすると中学校のどこかでつまずいたのかもしれません。
そのときには恥ずかしがったり面倒くさがったりすることなく、
つまずいたところまでちゃんと戻ってやり直すことが必要です。
それを怠っていると、いくら先に進もうとしても絶対にうまくいきません。
ぼくは高校1年生のときに数Ⅰでつまずいちゃったので、そのまま文系に進みましたが、
国立文系コースだったので受験前には数Ⅰをやり直す必要がありました。
高1のときの数学の授業では最初の因数分解からさっぱりわからなかったのに、
自分で参考書を使って順番にルールを覚えていったら、
ものすご~く簡単なのでビックリした覚えがあります。
高1のときの先生がまったく基礎・基本の説明とかをしてくれなくて、
すぐに問題を解かせるタイプだったのでそれで落ちこぼれてしまったのですが、
ちゃんとパズルのルールが理解できると、パズルはいとも簡単に解けるし、
自分で解けるとやっていて面白くなってくるし、
あの先生はなんでちゃんと教えてくれなかったんだろうと本当に頭に来たことがありました。
数学とか英語って人それぞれつまずくポイントが違いますので、
クラス全員にわからせるのはなかなか難しいです。
自分で自分のつまずきを発見するよう独学で基本からやり直してみるか、
先生に個別的に相談して自分がどこでつまずいているかを診断してもらうか、
いずれかを試してみるといいと思います。
英語、数学が克服できると、
「僕、全教科できすぎて偏りないからどっち行こうか迷ってんだよね~」状態になっちゃいますね。
素晴らしいと思います。
現代の複雑で高度な問題は、文系とか理系とかって分業していても解けない問題が増えています。
すべての学問が 「学際的」 にいろいろな分野と積極的に関わっていくことが求められています。
大学でもそういう文系とも理系とも分類できないような学問領域がどんどん創設されています。
例えばこの福島の状況も、文系の知識だけでも理系の知識だけでも解決できない、
高度に複雑に絡み合った問題群から構成されています。
そうした難問を解きほぐし、福島の人々のため、日本中の人々のため、
世界中の人々のために貢献できるカッコいい大人になってください!










 。
。 」 という暖かい声をかけていただきました。
」 という暖かい声をかけていただきました。



 ほかの話を聞きたいと思いました。いろんな人に質問をしながら話したほうがみんなもねないで聞いてくれると思います! 国語の時間に1分間スピーチというのがあるのですが、みんなの前で話すのは大変なのはわかりますが、みんなをまきこんで、自分の考えだけをずばずば言うよりは話を聞いてもらえますし、みんなが考えてくれると思います。また川口高校に来て話を聞かせてほしいと思います! ありがとうございました。(^^)!!!
ほかの話を聞きたいと思いました。いろんな人に質問をしながら話したほうがみんなもねないで聞いてくれると思います! 国語の時間に1分間スピーチというのがあるのですが、みんなの前で話すのは大変なのはわかりますが、みんなをまきこんで、自分の考えだけをずばずば言うよりは話を聞いてもらえますし、みんなが考えてくれると思います。また川口高校に来て話を聞かせてほしいと思います! ありがとうございました。(^^)!!!