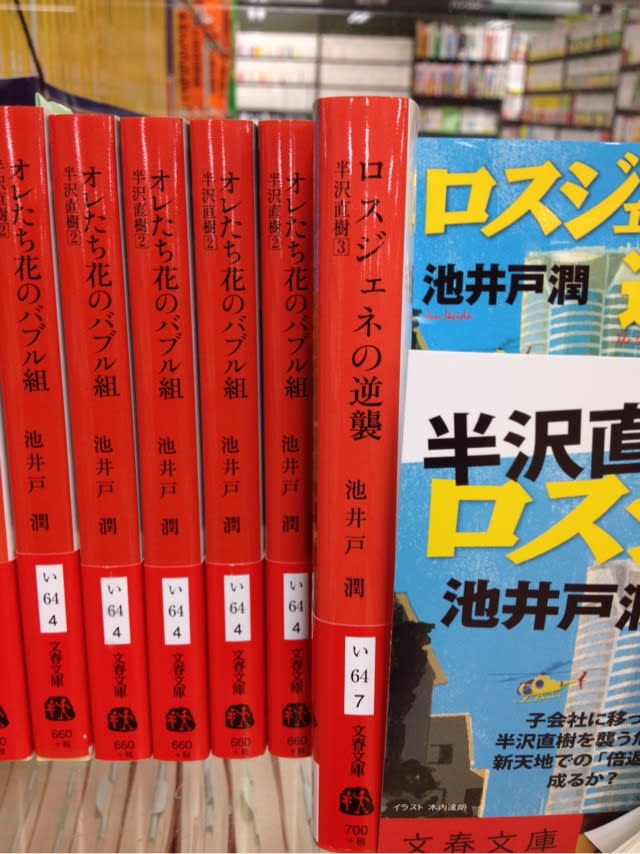東京の家は東京23区のど真ん中にあるんですが、まあいわゆる高級住宅街なわけです。
で、この辺を走っているクルマはたいがい高級外車ばかりなので、
そうしたものを見てももう慣れっ子でまったく動じたりしなくなっているのですが、
地下鉄の駅から家に向かう途中、こんなものを見つけて目がテンになりました。

うおおおおっ、ベンツの軽トラですかっ
そんなものがあったんですかっ?
そして、そんなものを購入する人がいるんですかっ?
思わずパシャパシャ写メを撮ってしまいました。
この写真、ナンバープレートは派手に塗りつぶしておきましたが、
軽自動車であることを表すオレンジ色のプレートなのは辛うじて確認できると思います。
うーん、こんなものがあったとは…。
いったいいくらぐらいするんだろう?
と思ってさっそくググってみることにしました。
すると…。
情報が出て来ないんです。
その代わりに 「YAHOO!知恵袋」 でこんな質問を見つけてしまいました。
「ベンツの軽トラってあるんですか?」
これに対する皆さんからの回答がどこまで信頼に足るものなのか、
もうこれ以上確認する気にもなりませんが、たぶんそういうことなのでしょう。
保存のために、質問の全文とベストアンサーをコピペしておきます。
質問 (2005/8/3 13:52:18)
「ベンツの軽トラってあるんですか?
ベンツのマークをつけた軽トラが近所を走っているのをよく見かけるんですけど。
自分で付けてたら痛いですよね。」
ベストアンサーに選ばれた回答 (2005/8/3 13:55:17)
「メルセデス・ベンツブランドの車の中に日本の軽規格に適合するモデルはありません。
おそらくご本人はしゃれのつもりでしょうが、
他人が見るとおっしゃるとおり 「痛い」 タイプの車だと思われます。」
わたし的にはしばらくの間ちょっとビックリもさせてもらいましたし、
これで1本ブログも書かせていただきましたので 「痛い」 というふうには評価しません。
いや、じっくり見たんですけど、
車体のちょっとしたカーブに沿わせてベンツマークは貼り付けられており、
とてもマークだけ後付けしたようには見えないんですよ。
楽しませてくれてどうもありがとうございました。
このベンツの軽トラで、この街を我がもの顔で走り回る高級外車たちをビビらせてやってください。
で、この辺を走っているクルマはたいがい高級外車ばかりなので、
そうしたものを見てももう慣れっ子でまったく動じたりしなくなっているのですが、
地下鉄の駅から家に向かう途中、こんなものを見つけて目がテンになりました。

うおおおおっ、ベンツの軽トラですかっ

そんなものがあったんですかっ?
そして、そんなものを購入する人がいるんですかっ?
思わずパシャパシャ写メを撮ってしまいました。
この写真、ナンバープレートは派手に塗りつぶしておきましたが、
軽自動車であることを表すオレンジ色のプレートなのは辛うじて確認できると思います。
うーん、こんなものがあったとは…。
いったいいくらぐらいするんだろう?
と思ってさっそくググってみることにしました。
すると…。
情報が出て来ないんです。
その代わりに 「YAHOO!知恵袋」 でこんな質問を見つけてしまいました。
「ベンツの軽トラってあるんですか?」
これに対する皆さんからの回答がどこまで信頼に足るものなのか、
もうこれ以上確認する気にもなりませんが、たぶんそういうことなのでしょう。
保存のために、質問の全文とベストアンサーをコピペしておきます。
質問 (2005/8/3 13:52:18)
「ベンツの軽トラってあるんですか?
ベンツのマークをつけた軽トラが近所を走っているのをよく見かけるんですけど。
自分で付けてたら痛いですよね。」
ベストアンサーに選ばれた回答 (2005/8/3 13:55:17)
「メルセデス・ベンツブランドの車の中に日本の軽規格に適合するモデルはありません。
おそらくご本人はしゃれのつもりでしょうが、
他人が見るとおっしゃるとおり 「痛い」 タイプの車だと思われます。」
わたし的にはしばらくの間ちょっとビックリもさせてもらいましたし、
これで1本ブログも書かせていただきましたので 「痛い」 というふうには評価しません。
いや、じっくり見たんですけど、
車体のちょっとしたカーブに沿わせてベンツマークは貼り付けられており、
とてもマークだけ後付けしたようには見えないんですよ。
楽しませてくれてどうもありがとうございました。
このベンツの軽トラで、この街を我がもの顔で走り回る高級外車たちをビビらせてやってください。













 。
。








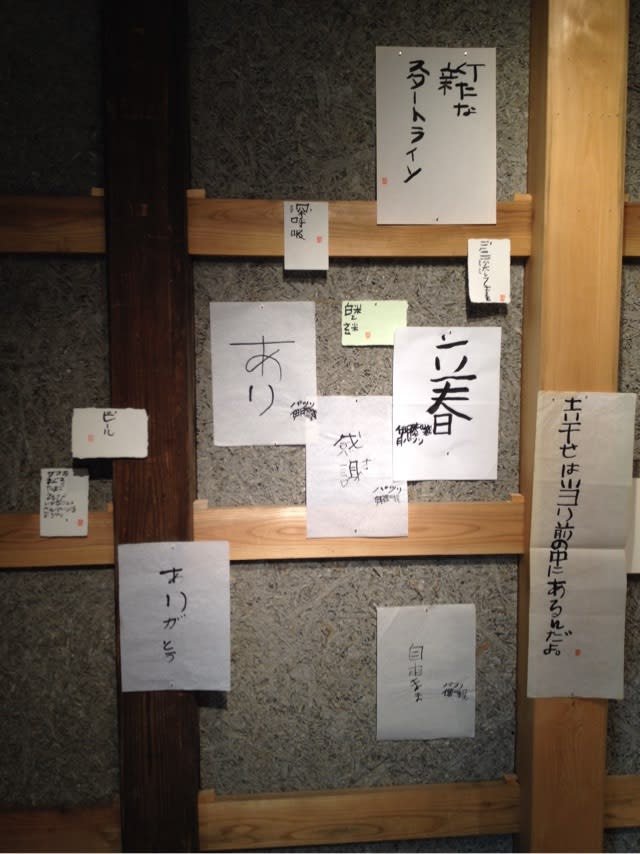























 。
。













 。
。