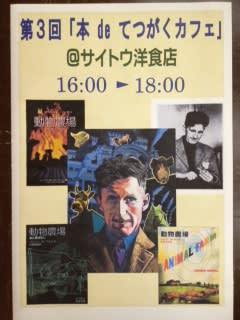もう10月も終わり。
今年もあと残すところわずか2ヶ月となりました。
11月も10月から引き続きイベント盛りだくさんとなりそうです。
今週末にはうちの陸上部所属のゼミ生が関わっている、
「ももりんダッシュNo.1」 が開催されます。
私としても大いに応援&宣伝しようと思っていたのですが、
ふと気づくと申し込み締め切りはとっくに終わってしまっていたようで、
出鼻をくじかれてしまいました。
まあ、今から出場はできませんが、子どもたちが走る様子を応援しに行ってあげてください。
大学からは 「生涯学習ネットワークフォーラム まなびピア2012」 のお知らせが届きました。
東北各地でそれぞれのテーマで開催されるみたいですが、
11月10日 (土)、11日 (日) にコラッセふくしまで福島分科会が開催されます。
テーマは 「若者達が活躍する 『持続可能なまち・地域・社会』」。
3.11以降、さまざまな復興の取り組みに関わってきた学生の皆さんにも関心のあるテーマじゃないでしょうか。
ホントは私も行きたいところなのですが、その週末は日本カント協会の学会のため、
関西に遠出していて顔を出すことができません。
特に2日目の 「熟議」 というのが気になっています。
「倫理学概説」 でちょこっとやったようなワールドカフェみたいなことするのかなあ?
ああ、気になるなあ、残念
ぜひ皆さん、私の代わりに参加してきてください。
昨年、倫理学概説の単位をもらった人、この後期に私から単位をもらいたい人はぜひっ
定員があって参加申し込みが必要なようです。
ちょっとめんどくさいですが、こちらから参加申し込みのほどよろしくお願いします。
生涯学習ネットワークフォーラム まなびピア2012
開催日 : 2012年10月10日 (土) 11日 (日)
会 場 : コラッセふくしま
テーマ : 「若者達が活躍する 『持続可能なまち・地域・社会』」
1日目 : ●ポスターセッション 〔10:30~12:00〕
●オープニングセレモニー 〔13:00~13:30〕
●基調講演 〔13:30~14:30〕
●小会議 〔15:00~17:00〕
2日目 : ●熟議 〔10:00~14:45〕
●クロージング 〔15:00~15:30〕
今年もあと残すところわずか2ヶ月となりました。
11月も10月から引き続きイベント盛りだくさんとなりそうです。
今週末にはうちの陸上部所属のゼミ生が関わっている、
「ももりんダッシュNo.1」 が開催されます。
私としても大いに応援&宣伝しようと思っていたのですが、
ふと気づくと申し込み締め切りはとっくに終わってしまっていたようで、
出鼻をくじかれてしまいました。
まあ、今から出場はできませんが、子どもたちが走る様子を応援しに行ってあげてください。
大学からは 「生涯学習ネットワークフォーラム まなびピア2012」 のお知らせが届きました。
東北各地でそれぞれのテーマで開催されるみたいですが、
11月10日 (土)、11日 (日) にコラッセふくしまで福島分科会が開催されます。
テーマは 「若者達が活躍する 『持続可能なまち・地域・社会』」。
3.11以降、さまざまな復興の取り組みに関わってきた学生の皆さんにも関心のあるテーマじゃないでしょうか。
ホントは私も行きたいところなのですが、その週末は日本カント協会の学会のため、
関西に遠出していて顔を出すことができません。
特に2日目の 「熟議」 というのが気になっています。
「倫理学概説」 でちょこっとやったようなワールドカフェみたいなことするのかなあ?
ああ、気になるなあ、残念

ぜひ皆さん、私の代わりに参加してきてください。
昨年、倫理学概説の単位をもらった人、この後期に私から単位をもらいたい人はぜひっ

定員があって参加申し込みが必要なようです。
ちょっとめんどくさいですが、こちらから参加申し込みのほどよろしくお願いします。
生涯学習ネットワークフォーラム まなびピア2012
開催日 : 2012年10月10日 (土) 11日 (日)
会 場 : コラッセふくしま
テーマ : 「若者達が活躍する 『持続可能なまち・地域・社会』」
1日目 : ●ポスターセッション 〔10:30~12:00〕
●オープニングセレモニー 〔13:00~13:30〕
●基調講演 〔13:30~14:30〕
●小会議 〔15:00~17:00〕
2日目 : ●熟議 〔10:00~14:45〕
●クロージング 〔15:00~15:30〕











 。
。