一昨日もお伝えしたとおり、「キャリア形成論」 第1回目のワークシートの課題は、
「キャリア形成論ガイダンスで印象に残ったこと (なるほどと納得したこと、違和感を感じたことなど) を、書いてください。」
というものでしたから、300人中ほんのわずかでしたが、
ガイダンス内容に対する違和感を書いてくれた人も数名いました。
今日はそのうちのひとつをご紹介いたします。
「第1回キャリア形成論ガイダンスを受講して、緊張感のある中、自分のキャリア形成は既に始まっており、自分で切り開いていかなければならないのだと強く自覚した。しかしながら、啓発されるとともに、ガイダンスの中には違和感をおぼえる指導がいくつかあった。まずメモをとるのがよいという指導である。そもそも、教員の方々がわざわざテキストを用意し、そこに必要事項を記入してくださっており、その上前に立って口頭で説明してくださっているのに対し、顔を下に向け、相手の方を向かないというのは大変失礼にあたると思う。心にひびくような言葉は、本当にひびいたのなら、容易に忘れることはないだろうというのが私の考えだ。また、自主的に取り組むよう指導もあったが、このようなレベルの低い指導を受けるとは思わなかった。低いレベルの集団と思われているのか、と感じた。教員の方々に見直してもらえるよう気をひきしめ、態度を改めていきたい。これからの自分の成長につながるようこの講義を生かしたい。」
こういうふうに率直に自分の思ったことを書いてくれる人はありがたいですね。
この人は大きく言ってふたつの違和感を挙げてくれました。
「大事なことは書き留めよう」 という指導に対する違和感と、
「大学では何事にも自主的に取り組もう」 という指導に対する違和感です。
どちらも大切なご指摘ですね。
まずは、人の話を聞くときにメモを取りながら聞くべきかどうか、という問題について。
この人は、相手が話しているときにメモを取りながら聞くのは失礼だと考えており、
書き留めたりせず、相手の方をきちんと向いて話を聞くべきだと考えています。
その理由を2つ挙げています。
ひとつは、テキストに書いてあることをさらに口頭で説明してくれているのだから、
それをわざわざ書き留める必要はない、という論点。
もうひとつは、心に響く言葉は容易に忘れたりしないのだから書き留める必要はない、という論点。
前者についてはその通りだと思います。
たしかに、せっかくテキストが配られていて、そこに記載されている内容だとしたら、
大事だと思ったらせいぜいそこにアンダーラインしたり丸で囲んだりするくらいでよくて、
それをわざわざ書き留める必要はないでしょう。
そういう意味では、
一昨日ご紹介したノート代わりのメモのようなワークシートの3番目のやつ、
あれは、そもそもわざわざ書き留めるような内容ではなかったと言えるでしょう。
しかしながら、1番目と2番目に例示した人のワークシートに書かれていた内容は、
(例えば 「コミュニケーション能力とは初対面の人と話す能力である」 とか
「大学では主体的に学ぶ姿勢が求められている」 など)
テキストのなかには記載されておらず、先生方がただ口頭で発言されただけの内容だったので、
こういうことは忘れないように書き留めておくということは必要でしょう。
(ワークシートではなく、自分のノートかテキストのなかに書き留めてほしいですけどね。)
もうひとつの論点に関して言うと、これは人と場合によりけりと言わざるをえません。
この世にはむちゃくちゃ記憶力のいい人がいるということを私は知っています。
日常のささいな出来事から人の発言まで、それはもうことごとく記憶できてしまえる人がいます。
そういう人が知り合いにいるととても便利ですので、
記憶力に問題を抱えている私はそういう人たちのことを 「外付けハードディスク」 と呼んで、
事あるごとに 「あの時ってどこの店に行ったんだっけ?」 とか
「あの飲み会のとき◯◯さんは何喋ってたっけ?」 と、記憶の補完をお願いするようにしています。
そういう記憶力を持ってる人って本当にうらやましいですが、
そういう人はそんなにざらにいるわけではありません。
こういう人であれば、授業中やインタビュー中にノートやメモを取ったりする必要はないでしょう。
しかし、人類の大多数はそうではないですし、大学生のほとんどはそうではないのです。
したがって 「心に響くことは容易に忘れないのだから書き留める必要はない」 という主張に対しては、
2つの観点から反論しておきたいと思います。
ひとつは主張の前半部分を認めたとして、
でもそうすると、心に響かなかったことは容易に忘れてしまうわけですね。
ひょっとすると、聞いたその時には心に響かなかったことが、
後々になって実は大事なことだったということが判明するということがありえます。
たぶん大学で教わることの大半はそうだろうと思います。
最初のうち大学の先生方が話していることのほとんどはみなさんの心に響かないはずです。
それは高校までの学びによって皆さんの中に芽生えた関心と、
大学教員が研究対象としていて授業のなかで話してくれる、
ものすごく繊細な最先端の問題意識とが乖離しているからです。
たぶん最初のうちは先生たちが何を話しているのか、
何を問題にしているのかまったくわからないかもしれません。
でも、その学問への理解が深まってくると、
ああ、あの時に先生が言っていたあの話ってそういうことだったのかあ、
と後になってその重要性に気が付くということがありえるのです。
ですから、今は心に響かない (からすぐに忘れてしまうような) ことのなかに
大切なカギがひそんでいるかもしれません。
そう思うと、書き留めておくことは必要だという気がしてきませんか?
もうひとつは主張の前半部分に対する反論です。
この人の想定とは異なり、人間は心に響いたことだって忘れてしまう場合があります。
先に挙げたような記憶力のいい人にはわからないかもしれませんが、
その場でどんなに素晴らしいと感動して聞いていても、
その中身を忘れてしまうという人がこの世には存在するのです。
かく言う私自身がそうですし、これまでの教職経験からすると、大学生の多くもそうです。
だからそういう経験に基づいて、私たちは皆さんに書き留めなさいと警告しているわけです。
したがって、相手の話を聞くときにメモを取りながら聞くことは、
基本的には失礼なことではありません。
むしろメモを取らずに聞くほうが失礼かもしれません。
せっかく時間を割いて話してくれたのにそれを忘れてしまったらただの時間のムダですからね。
ただ、たしかにずーっと下を向きながら話を聞くというのも、
話す側からするとあまり気分のいいものでないと受け止められることはありえます。
ですから、このへんはさじ加減ということになるのですが、
相手の目を見て話を聞きながら、
ポイントポイントでさっとメモを取るというワザは身につけてもらいたいものです。
あるいは最初に相手の承諾を得て、録音させてもらうということもありえますが、
初対面の方の場合はなかなか録音させてくださいとも言いづらいものです。
ですので、適度に相手の顔を見ながら、適度にメモを取るワザを身につけてください。
こんなふうに書いてくれていた人もいました。
「メモを取らないと記憶にほとんど残らないという話をきいて、今までは、メモをとるのに集中して話が聞けなくなってしまうと思い、メモをとってこなかったが、記憶に残そうという意識でメモをとったらいつもより話が頭に入ってきたので、これからも意識してメモをとろうと思った。」
さて、2番目の違和感に話を移しましょう。
大学では自主的に取り組むよう指導しましたが、
そんなレベルの低い指導を受けるとは思わなかった、という違和感です。
そういう違和感を感じてくれたなんて、たいへん頼もしいですね。
大学生がこういう方ばかりだと、私たち大学教員もラクなんですが…。
大学生たるもの自主的に取り組むのは当たり前だとわかっている方ばかりだといいのですが、
残念ながら、そういう学生ばかりではないのです。
初沢先生からもお話があったように、15%の学生が留年したり退学したりしてしまいます。
自主的に取り組んでくれなかった結果でしょう。
また、たとえそうはならなかったとしても、大学に入学してきたばかりの大学生は、
高校のときまでの習慣が身についてしまっていて、
全部先生の言うとおりにやっていればよかった生活から気持ちを転換できていません。
一昨日紹介したワークシートのなかにも、高校と大学の違いに対する戸惑いが書かれていましたね。
ですから、ああいう指導は新入生には当然必要な指導であって、
一概に皆さんのことをレベルが低いとみなしているわけではないのです。
第3回の授業で、何でも当たり前と思ってはいけないという話をさせていただきました。
人間は自己中心的に考えがちな動物ですので、
自分にとっての当たり前をすべての人にとっての当たり前だと思い込む癖があります。
優秀な人は、他のみんなも優秀であって当たり前だと思いますし、
怠惰な人は、他のみんなも怠惰だと思い込みます。
大事なのはいろんな考え方の人、いろいろな価値観の人がいるということをわきまえておくことです。
今回の違和感を表明してくれた方が教員志望なのかどうかはわかりませんが、
どんな職業に就くにせよこの人間発達文化学類で学ぶからには、
人間の発達・成長を支援することのできる広い意味での教育者になっていただきたいと思います。
そして、教育者にとって大事なのは、自分と同じタイプの人間のみを相手にするのではなく、
自分とまったく違うタイプ、まったく違うレベルの人間をも相手にできなければいけないということです。
大学生なんだからこんなことできて当たり前、○○なんだからこんなこと知っていて当たり前、
というような先入見をもって臨んでしまうと相手の発達・成長を助けることはできません。
一度自分の常識を疑ってみて、いろいろな人間がいるということを受け入れる必要があるでしょう。
かく言う私たちも、自分の大学時代と引き比べて、
今どきの大学生が自分の思っていた大学生像とかけ離れていることを痛感する経験を何度もして、
だんだんとああいう指導も必要なんだとわかってきた次第です。
高い志をもって入学してきた方にとってはカルチャーショックなこともあるかもしれませんが、
それもまた大事な学びのひとつだと思って、
けっして相手に合わせる必要はありませんが、いろいろな人間と付き合ってみてください。















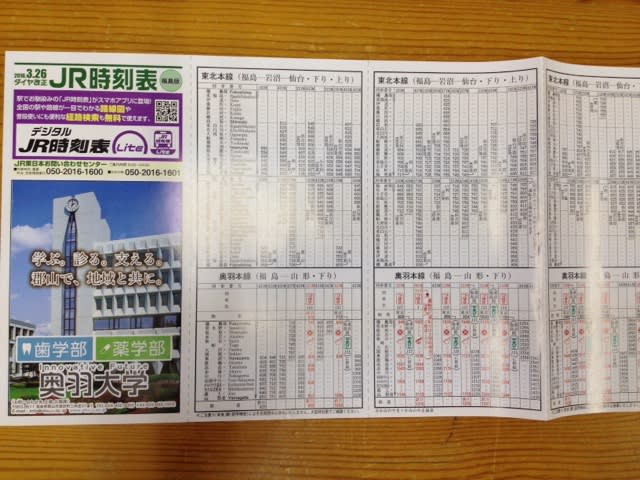

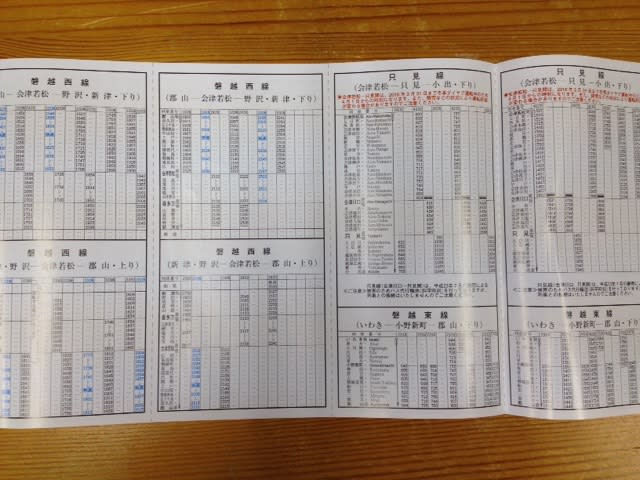

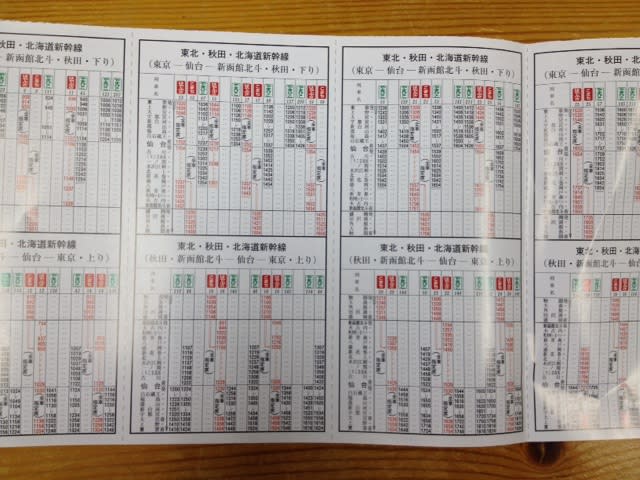







 。
。
 。
。
 。
。


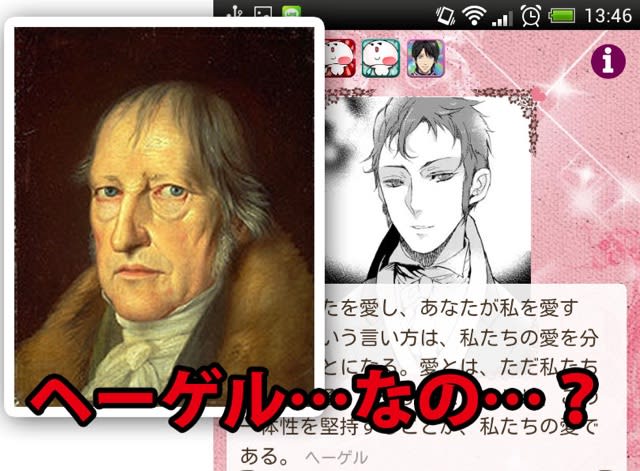





 。
。

 この記事には気色悪い画像が含まれています。
この記事には気色悪い画像が含まれています。



