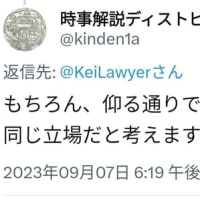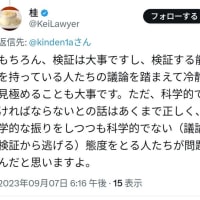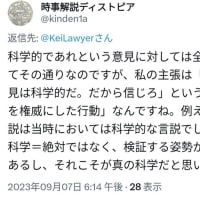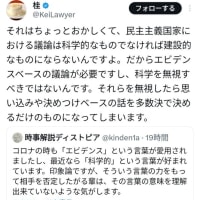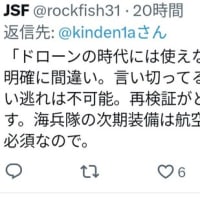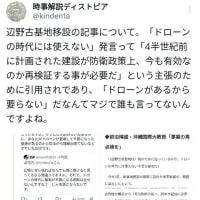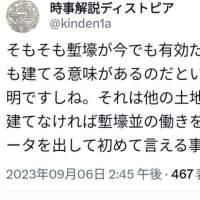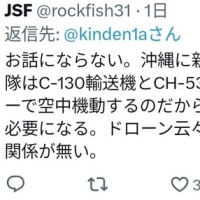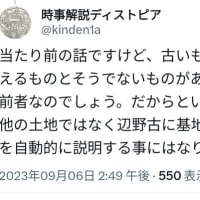アメリカ映画の最大の特徴として「強いアメリカ」というものが挙げられる。
わかりやすいのが鬱エンディングで有名なパニック映画『ミスト』で、
霧の中、怪物に囲まれ孤立無援となった絶望的状況を州軍が簡単に解決してしまう。
独裁→アメリカ軍介入→民主化&万事解決というイデオロギーが戯画化されているのだ。
同様にハリウッド版ゴジラでも、何かと犠牲を強いられ、時には敗北を喫する
日本版と違い、アメリカ版は特に犠牲も苦労もなく簡単にゴジラを倒してしまう。
極めつけが冒険活劇『インディ・ジョーンズ』シリーズで、
ナチスやソ連といったアメリカの敵に勝利する物語がそこでは描かれている。
2作目は一応、舞台はインドで変な宗教集団が敵になっているが、
これは見る人が見れば、ベトコンのメタファーであることにすぐに気づく。
このシリーズでは、悪役はことごとく悲惨な最期を迎えており、
2作目ではインディの活躍により邪教徒に支配された村々が解放され、
自由な社会へと生まれ変わるというわかりやすいアメリカン・ヴィクトリーが描かれている。
まさに、強いアメリカは弱者の指導者となり、正しい結果をもたらすのだ。

(http://youtu.be/M_8_o_2sc0Eより)
2月14日より公開されている映画『フォックスキャッチャー』は
弱いアメリカを描いた稀有な、それだけに価値ある作品の1つだ。
主人公であるマーク・シュルツはオリンピック・金メダリストなのだが、
これといった援助を受けることができず、貧しい暮らしを送っていた。
まず、このアメリカの勝利の象徴である金メダリストが
国に守られず、惨めな生活をしているという描き方が斬新。
上の写真を見ても、スポンサーのジョン・デュポン(右)が堂々としているのに対して
体力的に圧倒的に優位に立っているはずのマーク・シュルツ(左)はどこか情けない。
マークはアメリカの大財閥、デュポン社の御曹司(といっても中年の男性)である
ジョン・デュポンから自身が所有するチーム「フォックス・キャッチャー」に
入団することを条件に、多額の資金援助をするという誘いを受ける。
アメリカは救うべき人間を救わないとジョンは言う。
結果を出したにも関わらず、何の恩恵も受けていないマークにとって
ジョンの言葉は、深く心に響いてくるものだった。
ジョンは兄であるデイブにも入団を勧めるが、デイブは誘いを断る。
事実上の育ての親でもあり、名コーチでもある兄と離れ離れになることを
悲しみながらも、マークは恵まれた環境でトレーニングを積み、見事、国際試合で優勝する。
とまぁ、ここまではトントン拍子なのだが、
この辺からジョンがレスリングチームを作ったのは、
自分の手で強いアメリカを生み出すこと、それを母親に見せて自分を認めてもらうこと
という思いっきり個人的な理由があったからだということが次第にわかってくる。

(http://i.ytimg.com/vi/Fi1m6wdJEK4/mqdefault.jpg)
デュポンを一言で表すならば、
アメリカ版三島由紀夫である。
自分のことを「イーグル(アメリカの象徴はワシ。ちなみに中国は竜、ロシアは熊)」
と呼ばせたがり、愛国者を自称し、自分の手でアメリカに勝利をもたらすことを夢見ている。
父親を演じることに憧れ、自分が作らせたドキュメンタリー番組では
自分が選手の第二の父親であり、主導者なのだということを高らかに宣言する。
ミリタリー・マニアでもあり、部屋にはライフルや拳銃のコレクションがあり、
戦車まで揃えるほどの熱の入り様だ(おまけに機関銃が取り付けられていないと文句まで言う)
軍人?らと共に射撃訓練に興じ、時にはトレーニングルームの天井を撃ち、
周囲の注目を浴びようとする典型的な劇場型の人間。それがデュポンだ。
彼自身もレスリング大会に出場し優勝トロフィーを獲得しているが、
実は、スポンサーである彼を気遣って勝たせてもらっているだけであり、
実際には大したことがない。
よろよろと組み手をしている様子は、かなり滑稽であり、
彼が名ばかりの監督兼コーチであることが瞬時に理解できる演出になっている。
競走馬の飼育に専念する母親と対立しているが、競馬がイギリスのスポーツであることをふまえれば、
これはイギリス(元宗主国)とアメリカ(元植民地)の関係を上手く表現したものだと言えよう。

(https://www.major-j.com/upload/info/images/campaign_photo704.gif)
ほぼ素人のデュポンが監督兼コーチである点からお察しの通り、
次第にフォックスキャッチャーのメンバーは、退廃した生活を送るようになる。
デュポン自体が兄からの自立を促し、コカインを勧めるという
どこの不良だとツッコミを入れたくなる指導?をマークに行う。
(スピーチ直前で緊張している彼を元気づけるつもりだったらしいが)
結果的に半中毒者となり、髪を伸ばし、練習をさぼりがちになるマークとメンバーたち。
だが、それはマークにとっては初めての自立であり、兄への反抗だった。
ただでさえ母親に自分を認めてもらえず、苛立ちを隠せない時に
チームの自堕落な様子を見てかんしゃくを起こすデュポン。
マークに、一度は断られたデイブを再度スカウトするよう求める。
それはすでに終わったことと断るマークを殴りつけ、恩知らずの猿と罵倒し、
兄のほうを雇うべきだったと彼のプライドを傷つける言葉を吐く。
その日、マークは髪を刈り上げ、デュポンに与えられた偽りの自立を捨てる。

(http://i.ytimg.com/vi/zWNHlt3mEOk/0.jpg)
内心、いつもデイブの弟としか見られないことにコンプレックスを抱いていたマーク。
デイブにもデュポンにも敵意を見せ、自力で試合に臨もうとする。
が、案の定、コーチがいないため、思うように結果が出せない。
いろいろあって、マークはデイブと和解し、彼の指導を受けることにする。
この映画でデイブは父性と母性を表している。
親の代わりに弟を育ててきた人格者であり、
選手としてもオリンピックで金メダルを取得し、
コーチとしても的確な指導をし、選手を勝利へと導く超人でもあるデイブ。
美人の妻と可愛い子供を持つマイホーム・パパであり、
家族を守ることを何よりの喜びとする。
態度の悪い弟に対しても一度も罵声を浴びせず、
ただひたすらにデュポンと何かあったのかと心配する。
まさに完全にして完璧な父親である。
聖書、放蕩息子と検索してほしい。まさにデイブとマークは放蕩息子の親子そのものだ。
(アメリカがプロテスタントの国家であることを踏まえると、この描写はかなり興味深い)

(http://ww3.sinaimg.cn/large/9e520155jw1envnf00063j20go0b4abq.jpg)
結局、マークはデイブという神の愛なしに勝つことができなかった。
弟ではない自分になれなかった。それがマークの自己嫌悪と不調へとつながっていく。
ソウルオリンピックでデイブとデュポンの指導を受けながら、
結果を出せず敗北してしまうマークは二人の父親に振り回される息子のようだ。
国家や教会の掲げる愛と正義に振り回され、孤立していくアメリカ人。
本作でマークが自力で勝利するシーンはわずかワンシーンしかない。
あとはひたすら負け、負け、負けだ。
弱いアメリカをここまで描いた作品はそうはないと思う。

(http://eigakansou.com/wp-content/uploads/2015/01/foxcatcher.jpg)
フォックスキャッチャーを辞め、兄とも別れを告げ、
異種格闘技(ようするに賭け試合)で生計を立てるマーク。
それは、かつて仲間に「ああはなりたくないものだな」と侮蔑された生き方だった。
「U.S.A!U.S.A!」という歓声を受けながらリングに上がるところで物語は終わる。
結局のところ、この作品は
デュポンが示す「アメリカの愛」とデイブが示す「キリストの愛」の板挟みに悩まされ、
挫折によって、双方から解放される様をドラマティックに描写したものなのだろう。

(http://u.jimdo.com/www58/o/sd2b0ec37a12ecd48/img/i87ff6a0b309a4737/1411048038/std/image.jpg)
この作品は、シュルツを殺害するデュポンの狂気が全面的に押し出されて宣伝されているが、
実際には、気難しい人物といったぐらいの演出で、言われるほど異常性は強調されていない。
マークとデュポンの関係も、オーナーと選手以上のものではなく、
お互いに信頼しあっているわけでも、理解しあっているわけでもない。
むしろ、デュポンと絶交してからマークは彼と全く会話せず、
問題のシーンまでデュポンの影は薄い。ようするに空気だ。
誰よりも父親であることに憧れ、指導者である自分にこだわったデュポン。
それはアメリカそのものであり、彼の愛するイーグルや銃はアメリカの正義のシンボルでもある。
勝利にこだわるあまりにデイブを雇ったデュポンだが、それは父親の役割を自ら売り渡すことだった。
もはや、彼を父と慕う者はいない。マークは去った。
アメリカの夢は敗北をもって終わったのだ。
デュポンの殺害動機は本作の最大の謎の1つだが、しいて言うならば、
それはアメリカの敗北を認められない愛国者の最後のあがきだったのかもしれない。

以上が「弱いアメリカ」を描いた意欲作『フォックスキャッチャー』の感想だ。
正直、娯楽性は大してない。面白い作品ではない。
だが、アメリカの傀儡国家イラクでアメリカの敵を次々と撃ち殺す凄腕の射手を描いた
『アメリカン・スナイパー』(直球すぎるタイトルだ!)よりは本作のほうが価値がある。
日本でも弱い日本兵を描いて古参の右翼のブーイングを受けた映画、
『永遠の0』があるが、これは内容自体は逆に右傾化を促すものであり、
『フォックスキャッチャー』のように反省を迫るものになっていない。
この辺の違いが、なんだかんだで
アメリカのほうが健全な言論を発信している何よりの証拠なのかもしれない。
(アメリカ批判として有名なチョムスキーもサイードも
アメリカ在住の人間だ。アメリカでは言論の自由は確かに約束されている。
問題は、まともな意見が発信されても政府や社会が全力で無視していることだ)
わかりやすいのが鬱エンディングで有名なパニック映画『ミスト』で、
霧の中、怪物に囲まれ孤立無援となった絶望的状況を州軍が簡単に解決してしまう。
独裁→アメリカ軍介入→民主化&万事解決というイデオロギーが戯画化されているのだ。
同様にハリウッド版ゴジラでも、何かと犠牲を強いられ、時には敗北を喫する
日本版と違い、アメリカ版は特に犠牲も苦労もなく簡単にゴジラを倒してしまう。
極めつけが冒険活劇『インディ・ジョーンズ』シリーズで、
ナチスやソ連といったアメリカの敵に勝利する物語がそこでは描かれている。
2作目は一応、舞台はインドで変な宗教集団が敵になっているが、
これは見る人が見れば、ベトコンのメタファーであることにすぐに気づく。
このシリーズでは、悪役はことごとく悲惨な最期を迎えており、
2作目ではインディの活躍により邪教徒に支配された村々が解放され、
自由な社会へと生まれ変わるというわかりやすいアメリカン・ヴィクトリーが描かれている。
まさに、強いアメリカは弱者の指導者となり、正しい結果をもたらすのだ。

(http://youtu.be/M_8_o_2sc0Eより)
2月14日より公開されている映画『フォックスキャッチャー』は
弱いアメリカを描いた稀有な、それだけに価値ある作品の1つだ。
主人公であるマーク・シュルツはオリンピック・金メダリストなのだが、
これといった援助を受けることができず、貧しい暮らしを送っていた。
まず、このアメリカの勝利の象徴である金メダリストが
国に守られず、惨めな生活をしているという描き方が斬新。
上の写真を見ても、スポンサーのジョン・デュポン(右)が堂々としているのに対して
体力的に圧倒的に優位に立っているはずのマーク・シュルツ(左)はどこか情けない。
マークはアメリカの大財閥、デュポン社の御曹司(といっても中年の男性)である
ジョン・デュポンから自身が所有するチーム「フォックス・キャッチャー」に
入団することを条件に、多額の資金援助をするという誘いを受ける。
アメリカは救うべき人間を救わないとジョンは言う。
結果を出したにも関わらず、何の恩恵も受けていないマークにとって
ジョンの言葉は、深く心に響いてくるものだった。
ジョンは兄であるデイブにも入団を勧めるが、デイブは誘いを断る。
事実上の育ての親でもあり、名コーチでもある兄と離れ離れになることを
悲しみながらも、マークは恵まれた環境でトレーニングを積み、見事、国際試合で優勝する。
とまぁ、ここまではトントン拍子なのだが、
この辺からジョンがレスリングチームを作ったのは、
自分の手で強いアメリカを生み出すこと、それを母親に見せて自分を認めてもらうこと
という思いっきり個人的な理由があったからだということが次第にわかってくる。

(http://i.ytimg.com/vi/Fi1m6wdJEK4/mqdefault.jpg)
デュポンを一言で表すならば、
アメリカ版三島由紀夫である。
自分のことを「イーグル(アメリカの象徴はワシ。ちなみに中国は竜、ロシアは熊)」
と呼ばせたがり、愛国者を自称し、自分の手でアメリカに勝利をもたらすことを夢見ている。
父親を演じることに憧れ、自分が作らせたドキュメンタリー番組では
自分が選手の第二の父親であり、主導者なのだということを高らかに宣言する。
ミリタリー・マニアでもあり、部屋にはライフルや拳銃のコレクションがあり、
戦車まで揃えるほどの熱の入り様だ(おまけに機関銃が取り付けられていないと文句まで言う)
軍人?らと共に射撃訓練に興じ、時にはトレーニングルームの天井を撃ち、
周囲の注目を浴びようとする典型的な劇場型の人間。それがデュポンだ。
彼自身もレスリング大会に出場し優勝トロフィーを獲得しているが、
実は、スポンサーである彼を気遣って勝たせてもらっているだけであり、
実際には大したことがない。
よろよろと組み手をしている様子は、かなり滑稽であり、
彼が名ばかりの監督兼コーチであることが瞬時に理解できる演出になっている。
競走馬の飼育に専念する母親と対立しているが、競馬がイギリスのスポーツであることをふまえれば、
これはイギリス(元宗主国)とアメリカ(元植民地)の関係を上手く表現したものだと言えよう。

(https://www.major-j.com/upload/info/images/campaign_photo704.gif)
ほぼ素人のデュポンが監督兼コーチである点からお察しの通り、
次第にフォックスキャッチャーのメンバーは、退廃した生活を送るようになる。
デュポン自体が兄からの自立を促し、コカインを勧めるという
どこの不良だとツッコミを入れたくなる指導?をマークに行う。
(スピーチ直前で緊張している彼を元気づけるつもりだったらしいが)
結果的に半中毒者となり、髪を伸ばし、練習をさぼりがちになるマークとメンバーたち。
だが、それはマークにとっては初めての自立であり、兄への反抗だった。
ただでさえ母親に自分を認めてもらえず、苛立ちを隠せない時に
チームの自堕落な様子を見てかんしゃくを起こすデュポン。
マークに、一度は断られたデイブを再度スカウトするよう求める。
それはすでに終わったことと断るマークを殴りつけ、恩知らずの猿と罵倒し、
兄のほうを雇うべきだったと彼のプライドを傷つける言葉を吐く。
その日、マークは髪を刈り上げ、デュポンに与えられた偽りの自立を捨てる。

(http://i.ytimg.com/vi/zWNHlt3mEOk/0.jpg)
内心、いつもデイブの弟としか見られないことにコンプレックスを抱いていたマーク。
デイブにもデュポンにも敵意を見せ、自力で試合に臨もうとする。
が、案の定、コーチがいないため、思うように結果が出せない。
いろいろあって、マークはデイブと和解し、彼の指導を受けることにする。
この映画でデイブは父性と母性を表している。
親の代わりに弟を育ててきた人格者であり、
選手としてもオリンピックで金メダルを取得し、
コーチとしても的確な指導をし、選手を勝利へと導く超人でもあるデイブ。
美人の妻と可愛い子供を持つマイホーム・パパであり、
家族を守ることを何よりの喜びとする。
態度の悪い弟に対しても一度も罵声を浴びせず、
ただひたすらにデュポンと何かあったのかと心配する。
まさに完全にして完璧な父親である。
聖書、放蕩息子と検索してほしい。まさにデイブとマークは放蕩息子の親子そのものだ。
(アメリカがプロテスタントの国家であることを踏まえると、この描写はかなり興味深い)

(http://ww3.sinaimg.cn/large/9e520155jw1envnf00063j20go0b4abq.jpg)
結局、マークはデイブという神の愛なしに勝つことができなかった。
弟ではない自分になれなかった。それがマークの自己嫌悪と不調へとつながっていく。
ソウルオリンピックでデイブとデュポンの指導を受けながら、
結果を出せず敗北してしまうマークは二人の父親に振り回される息子のようだ。
国家や教会の掲げる愛と正義に振り回され、孤立していくアメリカ人。
本作でマークが自力で勝利するシーンはわずかワンシーンしかない。
あとはひたすら負け、負け、負けだ。
弱いアメリカをここまで描いた作品はそうはないと思う。

(http://eigakansou.com/wp-content/uploads/2015/01/foxcatcher.jpg)
フォックスキャッチャーを辞め、兄とも別れを告げ、
異種格闘技(ようするに賭け試合)で生計を立てるマーク。
それは、かつて仲間に「ああはなりたくないものだな」と侮蔑された生き方だった。
「U.S.A!U.S.A!」という歓声を受けながらリングに上がるところで物語は終わる。
結局のところ、この作品は
デュポンが示す「アメリカの愛」とデイブが示す「キリストの愛」の板挟みに悩まされ、
挫折によって、双方から解放される様をドラマティックに描写したものなのだろう。

(http://u.jimdo.com/www58/o/sd2b0ec37a12ecd48/img/i87ff6a0b309a4737/1411048038/std/image.jpg)
この作品は、シュルツを殺害するデュポンの狂気が全面的に押し出されて宣伝されているが、
実際には、気難しい人物といったぐらいの演出で、言われるほど異常性は強調されていない。
マークとデュポンの関係も、オーナーと選手以上のものではなく、
お互いに信頼しあっているわけでも、理解しあっているわけでもない。
むしろ、デュポンと絶交してからマークは彼と全く会話せず、
問題のシーンまでデュポンの影は薄い。ようするに空気だ。
誰よりも父親であることに憧れ、指導者である自分にこだわったデュポン。
それはアメリカそのものであり、彼の愛するイーグルや銃はアメリカの正義のシンボルでもある。
勝利にこだわるあまりにデイブを雇ったデュポンだが、それは父親の役割を自ら売り渡すことだった。
もはや、彼を父と慕う者はいない。マークは去った。
アメリカの夢は敗北をもって終わったのだ。
デュポンの殺害動機は本作の最大の謎の1つだが、しいて言うならば、
それはアメリカの敗北を認められない愛国者の最後のあがきだったのかもしれない。

以上が「弱いアメリカ」を描いた意欲作『フォックスキャッチャー』の感想だ。
正直、娯楽性は大してない。面白い作品ではない。
だが、アメリカの傀儡国家イラクでアメリカの敵を次々と撃ち殺す凄腕の射手を描いた
『アメリカン・スナイパー』(直球すぎるタイトルだ!)よりは本作のほうが価値がある。
日本でも弱い日本兵を描いて古参の右翼のブーイングを受けた映画、
『永遠の0』があるが、これは内容自体は逆に右傾化を促すものであり、
『フォックスキャッチャー』のように反省を迫るものになっていない。
この辺の違いが、なんだかんだで
アメリカのほうが健全な言論を発信している何よりの証拠なのかもしれない。
(アメリカ批判として有名なチョムスキーもサイードも
アメリカ在住の人間だ。アメリカでは言論の自由は確かに約束されている。
問題は、まともな意見が発信されても政府や社会が全力で無視していることだ)