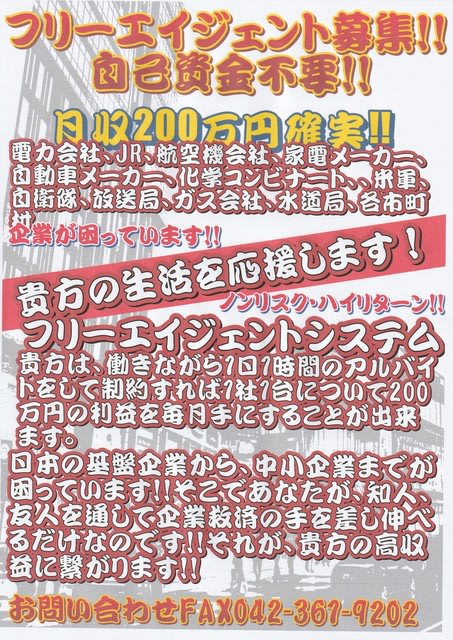固定観念を捨て去って新たな仕組みに順応しなければ生き残ることが出来ない未来が来る!!
車は路上を走るもの、列車は線路上を走るもの、船は水面を走るものという固定観念は崩れ去ります・・・。
不幸の始まりは、規制の路線から外れることが出来なかった人々から、淘汰は始まることである!!
既に学業を通して優劣に区分され、尚且つ528Hzの音楽を聴く者たちと、440Hzの音楽に熱狂する者達に分類されて440Hzを好む者達のDNAは破壊され破局への道を歩むように仕向けられています・・・。
主権在民?
政を司る者達が、国民に苦痛を与えてどうする気なのか!!
日本のあらゆる仕組みが、「国民弾圧」のための仕組みに大きく変貌していることに国民は気づいて、対策を講じなければ淘汰されてしまいます・・・。
日本人は「人口減」で起こる危機を甘く見ている 最低賃金を上げ、自ら変わらねばならない
東洋経済オンラインを愛読している読者の中にはご存じの人も少なくないだろう。『日本人の勝算』(東洋経済新報社)の著者、デービッド・アトキンソン氏は日本在住30年のイギリス人。
現在は国宝・重要文化財の補修を手がける小西美術工藝社社長として、日本文化をサポートしている。
そのような立場から、アトキンソン氏はこれまでにも自著を通じて日本の将来を案じてきたが、今回、その語り口にはこれまで以上の緊張感がみなぎっているようにも思える。
その場しのぎの楽観論を唱えている場合ではない
人口減少と高齢化が進む日本には大変厳しい未来が待ち構えています。
これは脅しでもなんでもなく、人口動態などのデータを冷静かつ客観的に分析すれば見えてくる、ほぼ確実な日本の未来です。
今すぐにでも対応を始めないと、日本は近い将来、三流先進国に成り下がることは確実です。
いや、下手をすると、日本は三流先進国どころか途上国に転落する危険すらあるのです。(「はじめに 日本人の勝算」より)
ところが日本国内に蔓延しているのは、「今までの仕組みを微調整して対応すればなんとかなる」というような、その場しのぎの楽観論ばかり。
危機感がまったく伝わらないからこそ、アトキンソン氏としても焦燥感を禁じえないというわけだ。
2019年10月に予定されている消費税の引き上げについても同じだ。
その問題に関しては「社会保障の負担が重く、税収を増やさなければいけない。
そのためには、税率を上げる必要がある」と説明されているが、それはアトキンソン氏の目には「固定観念にとらわれた、非常に次元の低い理屈」としか映らないという。
理由はいたってシンプルだ。日本の社会保障制度に関していえば、究極的には税率以前の問題だからだ。
たしかに、日本の消費税の税率が他の先進国に比べて安いのは事実です。
しかし、そもそも消費税の課税対象となる消費、そしてそれを増やすために不可欠な日本人の所得をいかにして上げるかが、この問題の根本の議論であるべきです。
それに比べたらたった2%の税率の引き上げなど、些末な話でしかありません。
大きなパラダイムシフトが起きている以上、今までにない、もっと根本的かつ大胆な政策が求められているのです。(「はじめに 日本人の勝算」より)
いま求められているのは、これまでの常識から距離を取り、前提条件にとらわれずに解決策を見いだす思考だとアトキンソン氏は言う。
そこで本書においてもさまざまな角度からこの問題に斬り込んでいるのだが、特に興味深いのは第5章「最低賃金を引き上げよ」から第6章「生産性を高めよ」につながる流れだ。
第5章で「世界経済の成長が『生産性向上』に依存するようになりつつあるからこそ、最低賃金を引き上げれば生産性をつり上げることができる」ことを示したのち、第6章では、日本における「賃上げ」の重要性を説いているのだ。
根底にあるのは、人口減少・高齢化に対応するためには、全企業が賃上げに向かうことが不可欠だという考え方である。
問題は、経営者をどう動かすか
これからは高齢化によって、無職の人が激増することになる。つまり、彼らの年金を払う予算が必要になってくるわけだ。
それだけではない。高齢者だからこそ医療負担も大きいため、その財源も必要なのである。
しかしその一方、給料をもらっている世代は激減する。だとすれば、その税負担のために生産年齢人口の給料を増やすことが必須となる。
所得増加を実現するには生産性向上が必要条件であり、これが大きな政策転換になるということである。
具体的に計算してみましょう。社会保障に費やしているコストを生産年齢人口で割り、さらに年間平均労働時間(ここでは2000時間とします)で割ると、「1人・1時間当たりの社会保障費負担額」を計算できます。
これは2018年には約817円でしたが、2040年には1642円となり、2060年には2150円にまで膨らみます(ここでは、2040年までに社会保障コストが190兆円まで膨らみ、その後横ばいとなると仮定しています)。
今の最低賃金では、とても対応できません。(213ページより)
だが、悲観する必要はないとアトキンソン氏は言う。なぜなら、日本の人材評価は世界第4位と非常に高いのに、現在の生産性は著しく低いから。
日本では、人材の潜在能力がまったく発揮されていないということだ。
日本の生産性はあまりにも低迷している期間が長く、他の先進国とのギャップが開きすぎている。よって、日本的経営や日本型資本主義、あるいは文化の違いを理由として正当化したり、ごまかしたりすることは不可能。
これを解決することは日本にとって喫緊の課題だが、そこでの唯一の問題は、経営者をどう動かすかにあるというのである。
本来であれば、ここまで人材の評価の高い国であるならば、人材を上手に活かしさえすれば、大手先進国で最高水準の生産性と所得水準を実現するのも可能なはずです。
にもかかわらず、現在の体たらくに、長年の人口増加が生み出した日本の経営者の無能さや国民の甘えが如実に表れています。
日本以外の国では、生産性と人材評価の間に強い相関関係があります。
また、人材評価と最低賃金にも深い関係があります。
しかしながら、日本だけは人材評価が高いのに、最低賃金が低く、生産性も低いのです。
異常だと言わざるをえません。(225〜226ページより)
しかしアトキンソン氏は、この現実を別の角度から捉えると、そこに希望が見えてくるとも記している。
生産性を向上させるため、最低賃金を引き上げる政策を実施すれば、それに十分耐えられる人材はすでに存在するというのがその理由だ。
言い換えれば、最低賃金を引き上げたとしても、日本人の実力をもってすればなんの問題も生じないという考え方である。
最低賃金を引き上げることの6つのメリット
そのように主張するアトキンソン氏が最低賃金の引き上げに期待することは、「強制力」だという。全企業に対して直接的・間接的に影響を与えることができるため、企業部門を動かす効果が期待できるということだ。
そして、そのメリットとして次の6つを挙げている。
① 最低賃金と企業規模拡大
優秀な労働者を豊富にかつ安く調達し、使うことができれば、技術開発への投資意欲が減退し、人間の力に依存した経営になる。スキルが高く、本来高い給料を払わなければ雇えない人材を安く雇えるのなら、給料の支払い能力が低くても会社をつくることが可能。その結果、企業の数は増え、小規模化するということだ。
人のコストが高くなると、企業規模が小さく支払い能力の乏しい企業では払えなくなる。
そこで規模の経済を利かせるために他社と統合し、規模を大きくする動機が生まれる。その生産性向上効果は絶大だというのだ。
② デフレと最低賃金
人口が減って需要者が減少すると、その悪影響を受ける企業では、需給のバランスが崩れて価格競争が始まる。
すると経営者は、社員の給料に手を出すようになる。生き残るための価格競争の源泉が、労働者の給与になるということ。
しかし、社員の給料に手をつけたとしても限界がある。その制限こそ、最低賃金。最低賃金を引き上げることによって、それ以上は価格競争ができないようにすることが可能になる。
企業は利益と価格と給料しかコントロールできないからだ。
価格を下げても給料を上げられなければ、経済が成長しない以上、その企業は規模を縮小するか破綻するしかなくなる。
よって国が最低賃金を引き上げれば、需要者の減少によって企業部門が引き起こすデフレ圧力を緩和できる可能性が高いという考え方である。
③ 最低賃金と女性活躍
海外でも日本でも、最低賃金で働いている最も多くの労働者は女性だ。つまり女性活躍にとって何より大事な政策が、最低賃金の引き上げ。
よって、安倍政権が本当に女性活躍を実現したいなら、最も早く効果が出る最低賃金の引き上げを実施すべきだという。
なお最低賃金を引き上げるなら、いわゆる「150万円の壁」を撤廃することが重要。
本来なら、専業主婦を優遇すること自体をやめ、子どもの数を基にピンポイントで優遇する、真の少子化対策をとることが望ましいとしている。
先進国として日本は最も改革しにくい国
④ 最低賃金と格差社会
最低賃金は、格差社会を是正するための政策でもある。日本の場合、上位層の収入上昇より、明らかに収入の低い労働者の増加によって格差が拡大してきたが、格差社会是正の早道は最低賃金の引き上げ。
現状の日本の最低賃金の水準はあまりにも低いだけに、これを大きく引き上げれば大きな成果が期待できるわけだ。
⑤ 最低賃金と地方再生
アメリカは州別に導入しているが、欧州の場合は全国一律が基本。日本の現行の最低賃金も都道府県別に決められているのでアメリカに近いが、そもそもアメリカと日本とではさまざまな規模が異なる。
日本は国土も狭いうえに、交通網が整備されていて、人口もアメリカの3分の1程度。
そのような国で最低賃金を都道府県ごとにバラバラに設定したら、労働者は最低賃金の低いところから、最も高い東京に集中してしまって当然で、事実そうなっている。
この悪循環から脱却するためにも、最低賃金を全国一律にすることを真剣に検討すべきだとアトキンソン氏は言う。
⑥ 最低賃金引き上げは「少子化対策」にもなりうる
日本の社会は厳しく、懸命に仕事をしてももらえる給料は少なく、楽しみもあまりない。
そして、老後の生活も不安だらけだ。そんな中、今の社会制度に対する抵抗として子どもをつくらない選択をしている人も相当数いるはず。
だからこそアトキンソン氏は、最低賃金を引き上げ、その最低賃金のすぐ上の層にも段階的な効果が出れば、少子化問題も緩和されるのではないかという仮説を立てているという。
計算機をたたいてみれば、今の日本経済のあり方を変えないと国が滅びてしまうことはすぐにわかる。
にもかかわらず、それに本格的に取り組んでいる人は少ないとアトキンソン氏は言う。
諸外国に比べてより改革が必要なのに、先進国として日本は最も改革しにくい国だとも。
だから、誰かが「日本人の変わらない力は異常」と言っていたことにも同感するのだそうだ。
これだけの危機に直面していても自ら変わろうとしないのは、普通の人間の感覚では理解できず、異常以外の何物でもないと言い切るのである。
残念ながら、そこには共感するしかないだろう。
なぜ、こんなにも頑なに変わろうとしないのか。
変わる必要がないと思っている人たちは、こんな理屈を述べ立てます。
日本は世界第3位の経済大国である!!
戦後、日本経済は大きく成長してきた!!
日本は技術大国である!!
日本は特殊な国である!!
よって、日本のやり方は正しいし、変える必要はない。
そして、アトキンソン氏が「変える必要がある」と指摘すると、次のような反論が返ってくるのだという。
日本はお金だけじゃない、もっと大切なものがあるんだ!!
前例がない!!
海外との比較は価値観の押し付けだ!!
今までのやり方は日本の文化だ!!
見えない価値がある!!
データ、データと言っても、データはいらない!!
さらに、本音を言う人は「俺はこれ以上がんばるつもりはないよ」と言います。
動かない日本を動かす方法
確かに、どこかで聞いたことのあるフレーズばかりだ。
それはともかく興味深いのは、アトキンソン氏が耳にしたという「こうした偏屈ともいえる意見を持つ人が少なくないのは、日本人の平均年齢が上がっていることに原因があるという人もいる」という意見だ。
40歳を過ぎると人間はなかなか変わろうとしないものだし、新しい考え方を受け入れなくなる傾向がある。
日本は国民の平均年齢が40歳に近いので、社会全体が変化しづらくなってきているということだ。
しかし、仮にそうだったとしても、私たちは大きく意識を変えなければならない時期にきているのかもしれない。
そして重要なのは、かたくなに動こうとしない日本という国を、どう動かすか、動かせるか。
日本企業は、自由にさせておくと、生産性を向上させる方向に向かわないだろう。
アトキンソン氏も言っているとおり、それは歴史を振り返ってみれば明らかだ。
だとすれば、手段はひとつしかないことになる。
すなわち、強制的にやらせることだ。
そのためには、最低賃金の引き上げが最適だという考え方なのである。
以上
企業は、賃金が高くても日本国民を採用し、国民は多少高くても国産品を愛用することが当面の課題である・・。
クリックして応援を宜しくお願いします!!