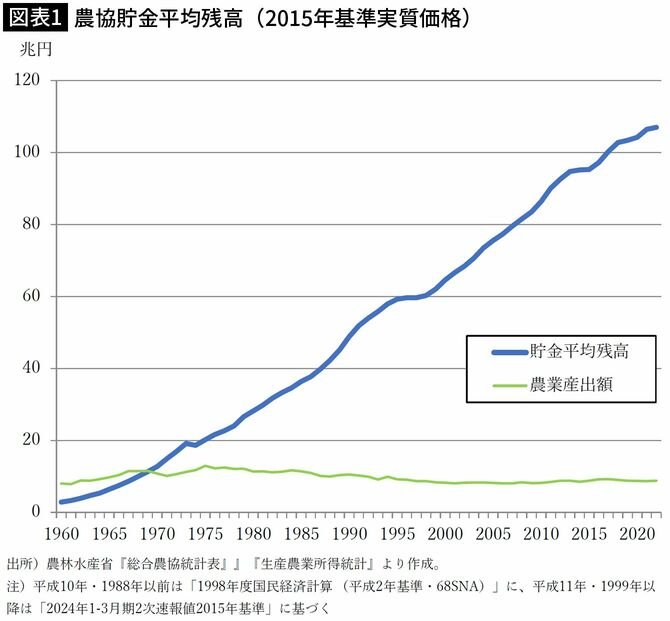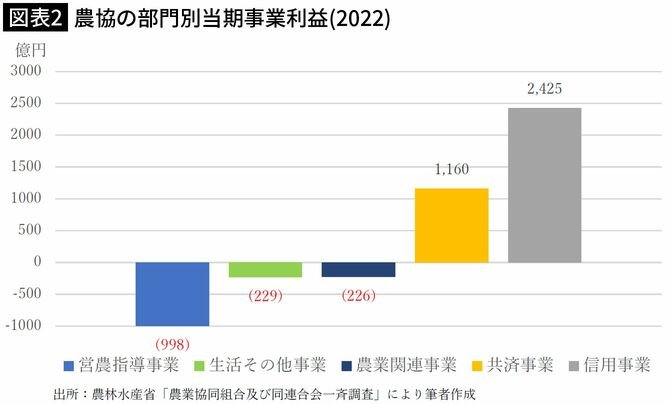2025年日本列島を襲う「疾病X」、「巨大地震」、「異常気象」は人為的に起こされる!!

不気味な病気がアフリカ中部で蔓延している。コンゴ民主共和国で発生した「疾病(しっぺい)X」と呼ばれる原因不明の病(やまい)だ。
同国保健省によると「重度のマラリア」とされるが、’24年11月には380人ほどが発症し70人以上が死亡したという。
「けっしてアフリカでの他人事ではありません。日本でも『疾病X』が蔓延する危険性は十分あるんです」
こう警鐘を鳴らすのは、元東京大学医科学研究所特任教授で医療ガバナンス研究所の上昌広(かみまさひろ)理事長だ。
よくもまあ手を変え品御変えて次々「ウイルス」をバラまくものだ!!
ただの風邪だからな!!
国民はあらゆる方法で立ち上がり戦わなくては、このままではじり貧ですぞ!!
コンゴの謎の感染症でパンデミック
 </button>
</button>
 </button>
</button>
「おそらく感染症でしょう。」
「拡大の速さから考えると、サルや鳥などを介するのではなく人から人へ感染していると思われます。」
「潜伏期間中で無症状の感染者が入国したら、防ぐことはできない。」
「あっという間に日本全国に蔓延します。」「
原因不明なので、今のところ有効な治療法や薬について何もわかりません。」
「日本が大パニックに陥(おちい)る恐れがあるんです」
「疾病X」にかかると、高熱、頭痛、咳(せき)、貧血を起こし嘔吐して死に至るケースが多数報告されている。
「感染力の強さや致死率の高さなどは不明ですが、パンデミック(世界的大流行)を引き起こす可能性があります。」
「新型コロナウイルスを上回る猛威となるかもしれません」
2025年に日本を襲うかもしれない災いは、原因不明の病気だけではない。
30年以内に70〜80%の確率で発生するといわれる、マグニチュード(M)9クラスの南海トラフ地震の脅威も高まっている。

「30年以内に起きるとすれば、当然、時間が経つほど発生確率が上がります。」
「南海トラフ地震は、すでにいつ起きてもおかしくない状態にあるんです」
政府の想定では、南海トラフ地震の最大死者数は32万人だ。
「被害はもっと大きくなるでしょう。」
「被災地で一人暮らしをする高齢者が支援を受けられず亡くなるなど、災害関連死が予想以上に多くなると思われるんです。」
「高齢者のリスクは、それだけではありません。」
「南海トラフ地震では、巨大な津波が時速数十㎞の猛スピードで襲ってきます。」
「しかも約6時間のうちに、50分ほどの間隔で何度も押し寄せてくる。」
「高齢の方が、数分以内に高台まで避難するのは相当難しいでしょう」
’24年は正月早々、能登半島をM7超の大きな地震が襲った。
「人口17万人ほどの能登地域でも、500人近くの方が亡くなりました。活断層は日本全国にあります。」
「東京や大阪などの大都市を、能登半島で起きたような大地震がいつ襲ってもおかしくない。」
「被害は能登半島の100倍に及ぶでしょう」
温暖化による異常気象も、さらに激化しそうだ。
「’24年は35℃を超える殺人的な猛暑に悩まされましたが、大量の二酸化炭素やメタンガスなどにより気温はさらに上がるでしょう。」
「40℃超えが頻発する可能性は十分ある。」
「日本では熱中症などで年間1000人ほどが亡くなっていますが、その数はもっと増えると思われます」
海水温も上昇し大量の水蒸気が発生するため、夏は豪雨、冬には気温0℃以下となり豪雪が列島を襲う。
「勢力の強い巨大台風が、北海道や東北に上陸する可能性もあります。」
「通常、台風は偏西風に乗って移動します。」
「しかし最近の偏西風は蛇行し日本のはるか北にある。」
「迷走する台風がノロノロと移動し、対策をほとんどしていない北日本で被害が拡大するかもしれません」
前代未聞の事態が続発する地球。
’25年の日本はその被害をまともに受けそうだ。
南海トラフ地震臨時情報(調査中) 発表
きょう13日午後9時19分頃、地震がありました。
震源地は日向灘(北緯 31.8度、東経 131.6度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は6.9と推定されます。
この地震の発生で、気象庁では、今回発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しました。
南海トラフ地震で被害が想定される地域の方は、個々の状況に応じて身の安全を守る行動を取ってください。
 </button>
</button>
●南海トラフ地震臨時情報(調査中)
きょう13日午後9時19分頃、地震がありました。震源地は日向灘で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は6.9と推定されます。
この地震の発生で、気象庁では、南海トラフ地震臨時情報の発表条件に合致したため、今回発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しました。
このため、13日午後10時30分から南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を開催します。
発表条件は、
・南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲監視領域内にて
・マグニチュード6.8以上の地震が発生
となっています。
調査開始は、2024年8月8日の午後4時43分頃、日向灘を震源とする地震(マグニチュード7.1、最大震度6弱)以来になります。
●南海トラフ地震臨時情報とは
南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。
情報名の後にキーワードが付記され、南海トラフ地震臨時情報(調査中)等の形で情報発表されます。
気象庁において、マグニチュード6.8以上の地震等の異常な現象を観測した後、5~30分後に南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されます。
その後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合における調査結果を受けて、該当するキーワードを付した臨時情報が発表されます。
政府や自治体から、キーワードに応じた防災対応が呼びかけられますので、呼びかけの内容に応じた防災対応をとってください。
●南海トラフ地震臨時情報が発表されたら
南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合は、個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始し、今後の情報に注意してください。
また、地震発生から最短2時間後に観測された異常な現象の調査結果が発表されます。
政府や自治体からキーワード(巨大地震警戒、巨大地震注意または調査終了)に応じた防災対応が呼びかけられますので、それぞれの内容に応じた防災対応をとってください。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をする必要があります。
地震発生後の避難では間に合わない可能性のある住民は1週間の事前避難を行う必要があります。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合は、事前の避難は伴いませんが、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をしましょう。
南海トラフ地震臨時情報(調査終了)が発表された場合は、地震の発生に注意しながら通常の生活を行いましょう。
ただし、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しておきましょう。
南海トラフトもDSの匙加減一つで、いつでも地震を起こせるのですがいよいよのようです!!
北海道や東北にも巨大台風が上陸!

 </button>
</button>
「雪爆弾」が襲来
 </button>
</button>
日本人皆殺しは、着実に進行しています!!
アメリカも、イスラエルも、資金が必要なんです!!
日本を植民地から解放して、戦後の賠償金として20京を日本から奪うしかないんです!!
これにより「アメリカ」は再生します!!
トランプと言えども「DS」を滅ぼすことはできません!!
争そうとDS達は、地球を破壊してしまいます!!
証券会社や銀行で、金融商品や株に変えても履歴が残りますから追跡されてすべてをデジタル化で奪い去ってしまいます!!
全ての金融商品、コインをクラッシュさせて人々の資金を奪い去ってしまい大災害を引き起こします。
緻密な金融庁の罠から逃れられるすべはただ一つ!!
それは国家のライフラインに関わるしかもアメリカと組んだ確実な事業に参加することです。
緊急情報 時間がない資産防衛を急げ!!
-
コロナを証明した論文はありません!!新型コロナは存在しません!!
-
ワクチンには予防効果、発症効果、重症化を防ぐ効果もありません!!
-
ワクチンの中身の正体は
-
酸化グラフェンによる血栓と、M-RNA修飾ウリジンを使った遺伝子組み換えで免疫破壊兵器です!!
-
ワクチンや食品に含まれる社会毒を排泄、無毒化する!!
-
松葉茶・ヨモギ茶・琵琶種粉末・ムクナ豆粉末・非加熱の塩・味噌・シソ・ショウガ・ワサビ
ビタミンB2・ビタミンC・ビタミンE・コエンザイムQ10・フルーツ・沢庵・はちみつ・クルミ
きのこ類・梅干し・胡麻ナッッ・オリーブオイル・寒天・アーモンド・シソ・ショウガ・沢庵・ヌカズケ・海藻類・ヌカズケ
納豆・ニンニク・ゆで卵・ゴーヤ・トマト・ブロッコリー・
-
スパイク蛋白質を体内から除去するのは、納豆キナーゼ・ブロメライン・クルクミン
心ある者達は「極度の国難」に備えよ!!














 </picture>
</picture>





 </button>
</button>