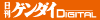今年の1月23日
キノコ カバノアナタケ=チャガー
という記事を掲載した。
その記事が最近になってまた注目を浴びているようで(記事ではなくチャガーが)再度わたしの体験も踏まえて掲載することにした。
まずわたしの体験談をご披露しようと思う。
25才ころから様々な皮膚の疾患を経験してきた。
最近では手の平に小さな水疱がたくさんできてかゆい。指先があかぎれのように割れて痛い。爪の根元から第2関節まで紫色に変わりジクジクとしている。爪が正常に生成されず凸凹。体全体にも小さな赤い湿疹ができ痒みがある。医師からはアトピーと診断されている。
そんな折昨年11月よりカバノアナタケ茶を飲み始めた。
途中3回ほど好転反応と思われる鼻水とくしゃみに襲われる。
年を明けて明らかにきれいな皮膚を取り戻し、水疱や割れもなくなった。
これで治ると思った。
春を迎えストーブも消されていくとそのまま「お茶」も降ろされ飲まなくなってしまった。
6月ころからまた元の木阿弥。今まで「お茶」のことを忘れてしまった。
また思い出して今月1日から飲み始めたところ、2日目で手の平に変化が見え始めた。今日は6日目だが1時間ほど鼻水とくしゃみが襲った。やっぱり効いているんだと実感した次第です。
お求めは下記写真の電話番号へどうぞ。

チャーガマガジン (chaga-magazine.com) より
がんやアレルギー疾患の抑制効果を期待できるカバノアナタケ・チャーガマッシュルーム
チャーガマッシュルーム(chaga mushroom)という名前は、日本ではあまりなじみがないかもしれません。北海道では和名のカバノアナタケとして北海道土産として売られているキノコです。
このカバノアナタケを採取しやすいロシアなどではさかんに研究が行われており、カバノアナタケによるがんの抑制効果や免疫を活性化する効果、ウィルスに対抗する効果などが証明されています。今回は、今までの研究から明らかになっているカバノアナタケの効果についてまとめます。
カバノアナタケ/チャーガマッシュルームとは
カバノアナタケとは、サルノコシカケ科に属するきのこで主にロシアを中心とした寒い地域で育ちます。日本でも、以前は北海道で見つけることができたといわれていますが、最近では乱獲が進み、ほとんど発見困難になっています。
カバノアナタケは和名ですが、チャーガとよばれることもあります。学名はFuscoporia obliqueと表記します。寒さに強く、マイナス20℃でも生育でき、白樺の木などに寄生し、樹液を栄養分として吸い取り10-15年以上かけて大きくなります。
見た目は黒く、ゴツゴツしているためこぶの様で、大きいものでは直径30センチになることがあります。最終的に白樺の木の栄養分を全て奪い、枯らしてしまうため「白樺のがん」とよばれていました。
しかし、カバノアナタケの研究が進むにつれて、その成分の健康効果が認識されるようになり、現在は発見することが難しい貴重なきのことなったため「幻のきのこ」、「森のダイヤモンド」とよばれるようになっています。
カバノアナタケの成分
カバノアナタケには、がん細胞を抑制する効果だけでなく、免疫力やウィルスに対する抵抗力を上げる効果があるといわれています。なぜ、そのような多岐にわたる効果を期待できるかというとカバノアナタケに含まれている特別な成分のためです。
カバノアナタケは、タンパク質、脂質、食物繊維、糖質、ビタミン類、ミネラル類、フラボノイド、リグニンなどを含みますが、特に注目されているのはβDグルカンとSOD酵素です。βDグルカンには、免疫細胞のはたらきを活性化させ、免疫力を増強させる効果があるといわれています。
カバノアナタケに含まれるβDグルカンは他のきのこに比べて多く、タンパク質を30%以上含むので吸収率が高いことがわかっています。SOD酵素は、体の中の余分な活性酸素を除去する効果があります。
活性酸素は、本来は細菌やがん細胞と戦うために必要ですが、過剰に産生されると正常な細胞まで傷つけてしまいます。過剰な活性酸素は、がんや老化、生活習慣病の原因になることが明らかになっており、活性酸素を除去できるSOD酵素にはがん細胞抑制効果があるといえます。
カバノアナタケにがん細胞を抑制できる効果があるのは、豊富に含まれたSOD酵素によると考えられています。
カバノアナタケの効果
ロシアには、カバノアナタケをお茶代わりに飲んでいる村人はがんの発症率が低いという言い伝えがありました。この事実に注目した研究者たちは、カバノアナタケに含まれる成分とその健康効果を次々に明らかにしていきました。
カバノアナタケの研究は、1951年にソビエト連邦科学アカデミー植物研究所と第一レニングラード医大が協力して始まりました。
当時のソビエト連邦では、臨床研究後にカバノアナタケのエキスが連邦薬局法指定公認の薬として、手術不能ながん、胃腸や十二指腸潰瘍、慢性胃炎、胃腸のポリープ治療に推奨されていました。その後も、多くの研究によりカバノアナタケの効果が示されました。
現時点で、抗がん効果、免疫力の強化作用、活性酸素除去作用、抗エイズウィルス作用、抗インフルエンザウィルス作用、O-157などに対する抗菌作用、糖尿病や高血圧の予防と改善作用、アレルギー疾患の予防と改善作用、慢性肝炎や慢性腎炎の予防と改善作用、ダイエット効果などが国内外の研究によって報告されています。
カバノアナタケによってがん細胞を撃退できる理由
がんは、喫煙、飲酒、ストレス、バランスの悪い食生活、不規則な生活、遺伝などによって引き起こされることがわかっています。遺伝が原因で発症するがんもありますが、多くのがんは毎日の生活習慣による免疫力の低下によって引き起こされるのではないかと考えられています。
実は健康な人の場合でも、体の中では毎日3000-5000個のがんの芽が発生しているといわれています。しかし、私たちの体が健康な場合には、もともと備わっている免疫力によってがんの芽を摘み取るようになっています。
つまり、免疫力を低下させるような生活習慣を繰り返していると、がんを発症しやすくなる可能性があるといえます。
がんに対する治療法は、外科療法、放射線療法、化学療法の3つが基本となっていますが、どの治療法も正常な細胞まで傷つける可能性があるため副作用や合併症が起きることがあります。
一方で、注目される免疫療法は、人間が本来もっている免疫力を高めることでがんを撃退するので正常な細胞を傷つける可能性は低いといえます。
カバノアナタケには、免疫力を高める効果に加えて、がんの犯人と考えられている活性酸素を除去する効果や抗酸化作用があるため、がん細胞を抑制することができると考えられています。
免疫細胞を活性化させるカバノアナタケ/チャーガ
具体的には、カバノアナタケにはβDグルカンとよばれる多糖類が豊富で、免疫細胞を活性化する効果を期待できます。またカバノアナタケに含まれる食物繊維も免疫力を活性化させることが知られています。
カバノアナタケに含まれるSOD酵素とメラニン色素は、活性酸素除去効果や抗酸化作用があるためがん細胞を攻撃、排除することを期待できます。活性酸素は、本来は体に必要なものですが、過剰に体内で産生されると正常の細胞まで傷つけて、がんや老化を招くといわれています。
カバノアナタケに含まれるSOD酵素は、がんの原因となる活性酸素を除去し、がんを起こしにくくすると考えられています。また、カバノアナタケに含まれるメラニン色素には抗酸化作用と遺伝子保護作用があることが明らかになっています。
メラニン色素には紫外線から肌を守る重要な役割がありますが、女性にとってはシミの原因となるので敵に感じるかもしれません。
しかし、メラニン色素は人間にとって欠かせない防御システムを担っており、メラニン色素がないと皮膚がんをはじめとするがんを発症しやすくなることがわかっています。
このようにカバノアナタケには、免疫力を活性化させる効果と活性酸素を除去する効果の両方が期待できるため、がんを撃退できるのではないかと注目されています。
実際に、ロシアからの報告では、乾燥したカバノアナタケとその他のきのこを投与したところ、カバノアナタケを投与したグループにおいてがんの転移の阻止率が高かったことが明らかにされています。
カバノアナタケが癌だけでなく、ウィルスにも効く理由
1993年の日本エイズ学会で、カバノアナタケはがんだけでなく、エイズウィルスにも有効であるという事実が発表されました。その後もカバノアナタケによるエイズウィルス抑制効果に関する研究や報告が続きました。
また、1999年には第51回北海道公衆衛生学会でカバノアナタケはHIVウィルスだけでなく、インフルエンザウィルスが体内で増殖することを抑制する効果があると発表されました。
なぜ、カバノアナタケにウィルスの増殖抑制効果があるかというとリグニンという成分が含まれるからです。ウィルスが体の中で悪さをするためには、ヒトの細胞に対して酵素を出し、細胞膜を溶かして浸入する必要があります。
しかし、カバノアナタケに含まれるリグニンはウィルスが出す酵素を吸収し、ウィルスが攻撃できないように阻害します。ウィルスはヒトや動物の細胞に寄生しないと生きることができないので、リグニンによって侵入を阻まれたウィルスは死滅するしかありません。
このように、カバノアナタケはリグニンという有効成分によって抗ウィルス作用を発揮するといわれています。
アレルギー性疾患を抑制する可能性もあるカバノアナタケ
カバノアナタケによる健康効果は、免疫増強効果、がん細胞を抑制する効果、抗酸化作用、抗ウィルス作用など多岐にわたりますが、アレルギー疾患にも効くのではないかと期待されています。
アレルギーは、肥満細胞とよばれる細胞からヒスタミンが遊離されることにより起きるといわれています。マウスを対象に行われた研究では、カバノアナタケから抽出したエキスによってヒスタミンの放出が抑制され、アレルギー反応を低下させたことがわかっています。
難治性の皮膚病にも効果を期待できるカバノアナタケ
皮膚がんなど、さまざまながんに移行する可能性があるとされている皮膚病として乾癬(かんせん)が知られています。乾癬とは、長期にわたる経過をとる皮膚病で、人によって症状や発症する場所が異なります。
典型的な症状としては、皮膚から少し盛り上がった赤い発疹の上に、銀白色のフケのようなものが付着し、ぼろぼろと剥がれ落ちます。乾癬では、炎症を起こす細胞が活性化しているので、皮膚は常に赤みを帯びているような状態になります。
日本では1000人に1人が発症するといわれていますが、現時点でも原因不明です。治療は塗り薬や飲み薬、紫外線を当てる光線療法、生活習慣の改善などですが、あまり効かない人もいます。
カバノアナタケのエキスを乾癬の患者に投与した研究では、規則正しく飲用すると3か月で最大の効果が得られたそうです。多くの患者において、皮膚の発疹が消滅し、乾癬によって変形した爪も2-3か月で改善傾向となりました。
患者の中で数名が、症状が改善した後にカバノアナタケのエキスの飲用をやめたところ、皮膚に再び症状が出たため飲用を再開し改善したことが認められました。
今回の研究では、カバノアナタケの乾癬に対する治療効果のメカニズムは明らかになっていませんが、カバノアナタケの免疫力増強作用や抗酸化作用によって体の中から体質が改善したことが関連しているのかもしれません。今後のさらなる研究が期待されています。
カバノアナタケの副作用
カバノアナタケは、古くからロシアの家庭薬として親しまれてきました。多くの薬は、効能がある一方で副作用を起こす可能性があります。しかし、カバノアナタケは長い歴史の中で目立った副作用は報告されていません。
つまり、多くの人が副作用を気にせず安全に摂取できるといえます。ただし、どのような薬や食べ物でも、人によって合わないことがあります。もし、カバノアナタケを摂取後に体に異変を感じた場合には早めに医師に相談するとよいです。
カバノアナタケの摂取の仕方
では、具体的にカバノアナタケは1日どれくらい飲めばよいのでしょうか。ロシアでは、カバノアナタケをお茶代わりに飲んでいる村ではがんが少ないといわれていました。
健康維持を目的とする場合には、1日約10-20gを目安にするとよいと言われています。がんなどの治療中の方の場合には、体調を見ながら量を増やして調整することも可能です。ロシアでは、ハーブティーと同じ感覚でカバノアナタケのお茶が飲まれているといいます。
例えば、細かく砕いた約5g程度のカバノアナタケをティーバッグに入れ、2Lのお湯で煮出して何度かに分けて飲みます。温かくても冷たくても飲むことができます。
カバノアナタケを飲むタイミングは、寝る前が理想的と考えられています。
なぜなら、免疫細胞は寝ている間につくられるため、免疫を活性化する作用のあるカバノアナタケを寝る前に飲めば効率がよいと考えられているからです。しかし、大切なのは自分の続けやすいタイミングで毎日継続して規則正しく摂取することです。
効き目に関しては、早い人では1週間程度、遅くても1か月程度で体の変化を感じるといいます。なるべく継続して摂取した方が、体調を改善できると考えられています。
カバノアナタケの最新エビデンス(論文・根拠)
カバノアナタケに関する研究結果は国内外から報告されており、その効果は明らかなようです。以下に最新のエビデンスについてまとめます。
○カバノアナタケのエキスががんの進行を抑制
マウスを対象とした研究では、カバノアナタケのエキスを3週間連続で投与するとがんを60%抑制した。また、がん細胞の増殖やがんの増殖に必要な血管の新生を阻害し、がんの進行を抑えた。興味深いことに、カバノアナタケのエキスはマウスの体温を上昇させることがわかり、代謝を上昇させることによってがんの進行を抑制する可能性があることが明らかになった。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27441282
○カバノアナタケのエキスが酸化ストレスによる肝障害を改善
ラットを対象とした研究では、カバノアナタケのエキスを酸化ストレスによる肝障害に対して投与したところ肝機能の改善を認めた。カバノアナタケによる抗酸化作用によると考えられた。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853962
○カバノアナタケによる大腸がん細胞の増殖抑制効果
大腸がん細胞を対象とした研究では、カバノアナタケの成分であるエルゴステロールペルオキシドががん細胞の増殖を抑制することがわかった。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26210065
○カバノアナタケに含まれる多糖類が脳腫瘍細胞の増殖を抑制する
カバノアナタケのエキスに含まれる多糖類が、ヒトの脳腫瘍細胞の増殖を抑制することがわかった。腫瘍細胞の抑制が起きるメカニズムとしては、カバノアナタケが細胞死(アポトーシス)を起こすカスパーゼ3の発現を促進することが考えられた。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24940902
○カバノアナタケがアレルギー反応を抑制した
アナフィラキシーショックを起こさせたマウスを対象とした研究では、カバノアナタケの抽出液を投与するとアレルギーに関与するIgEのレベルが低下することがわかった。今回の研究から、カバノアナタケは抗アレルギー効果のある食材として有効である可能性が示された。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23535020
○カバノアナタケがヘルペスウィルスの侵入を防いだ
細胞を用いた研究で、カバノアナタケの抽出液を投与するとヘルペスウィルスの侵入を制御できることがわかった。ウィルスの糖タンパク質に対してはたらきかけ、細胞内への侵入を防ぐことが明らかになった。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510282
○カバノアナタケが炎症性腸疾患を改善した
炎症性腸疾患を発症したマウスにカバノアナタケの抽出液を投与したところ、炎症に関わる物質の抑制によって腸の炎症性病変を改善することが明らかになった。炎症性腸疾患に対するサプリメントとしてカバノアナタケは有効である可能性が示唆された。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22819687
○カバノアナタケは認知機能障害と酸化ストレスを改善する
認知機能の障害を起こさせたマウスに対して、カバノアナタケを投与すると認知機能障害に関連する物質と酸化ストレスを抑制することが明らかになった。カバノアナタケが、脳の学習や記憶などの機能に良い影響を与える可能性が示唆された。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779570
○カバノアナタケは炎症性腸疾患患者のDNA傷害を抑制する
炎症性腸疾患患者のリンパ球を採取し、カバノアナタケの抽出液をかけたところ傷ついたDNAの数が減少することが明らかになった。今回の研究から、カバノアナタケは炎症性腸疾患患者におけるDNA傷害を改善することがわかり、サプリメントとしてカバノアナタケが有効な可能性が示された。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997282
参照URL
http://www.wakasanohimitsu.jp/seibun/tyaga/
https://www.sup-pedia.com/ingredients/charga/
ライター紹介:大塚真紀
東京大学大学院医学系研究科卒。腎臓、透析、内科の専門医。医学博士。
東京で内科医師をしていましたが、現在は主人の留学についてアメリカに滞在中。医師歴は10年で、腎臓と透析が専門です。アメリカでは専業主婦をしながら、医療関連の記事執筆を行ったり、子供がんセンターでボランティアをして過ごしている。医師としての記事の監修、医学生用のコンテンツ作成経験有。
******************
チャーガ(カバノアナタケ)に含まれる成分一覧と安全性・副作用について
チャーガはどのような成分が含まれているのか?副作用はあるのか調べました。
チャーガ【別名:カバノアナタケ】は身体に物凄く効果があると近年で有名になっていますが、効果があるといっても詳しく知らない人にとっては身体に良いことくらいで大雑把にしかわからないですよね。
そんな人間が体内にもつSODの量には個人差が見られ、尚且つ、SODの力は年とともに弱まっていくと言われています。 チャーガ(カバノアナタケ)にはホウレン草の250倍・野菜ジュースの175倍・アガリクスの23倍の抗酸化力があります。
チャーガ(カバノアナタケ)にはSOD活性が非常に高いことが確認されています。主な有効成分がどのような効果を持っているのか詳しく書いていきたいと思います。
・チャーガに含まれる成分一覧まとめ
免疫力アップ、便通改善、美肌効果、抗酸化力アップ、ウイルス抑制などが言われている。
チャーガの主な成分とどのような効果を持っているのかまとめました。
β―グルカン・・・キノコ類に含まれる免疫細胞を活性化させる成分
ベツリン酸・・・ガン細胞を死滅させ、成長を抑制させる
サポニン・・・コレステロール減少、肝機能向上、便通改善、二日酔予防、脂肪代謝促進
リグニン・・・抗菌、抗酸化作用、ウイルス抑制作用
ナトリウム・・・細胞の浸透圧を維持し、血液などの体液を中性に保つ
カルシウム・・・骨粗鬆症を予防したり筋肉が正常に働くように助ける
マグネシウム・・・動脈硬化や心疾患の予防
亜鉛・・・生殖能力の向上、皮膚炎予防、味覚低下予防
マンガン・・・活性酸素を消去したり血中脂肪酸を減少させる
ポリフェノール・・・抗酸化作用
フラボノイド・・・活性酸素除去、高血圧安定、抗アレルギー作用
エルゴステロール・・・コレステロール低下させたり抗ガン作用
トリテルペノイド・・・血管新生阻害作用、毒物による肝障害から肝臓を保護する作用
アルカロイド・・・脳の疲労をやわらげ、動脈内の血流をスムーズにする
プテリン・・・抗酸化作用があり活性酸素を除去
アガリチン酸・・・NK活性の増加
イノシトール・・・血液の流れをよくし、蓄積してしまった脂質を取り除く作用
その他含まれる成分・・・タンパク質・脂肪・灰分・食物繊維・糖質・ビタミン類・ミネラル類
それでは上記の中でも特に抑えて置きたいチャーガの成分を詳しく解説していきたいと思います。
・免疫力を高めるβ-グルカン
きのこ類に豊富に含まれている成分の1つ「β-グルカン」と言われる多糖類ですが、この成分は、免疫力を高める働きがあります。
身体の中にガン細胞が出来てしまうと、必ず免疫と呼ばれる生体防御でがん細胞を駆逐しようとします。この免疫力が弱いと段々とがん細胞を排除できなくなってしまい、様々な部位で悪さをしてしまうようになるのです。
その免疫力を高める成分であるβ-グルカンですが、アガリクス茸等に含まれるβ-グルカンは水溶性のヘテロβ-グルカンのみに対し、チャーガは不水溶性であるホモβ-グルカンも併せ持っており、多岐にわたるきのこ類の中でもこの2種類のβ-グルカンをもつきのこは、チャーガ(カバノアナタケ)以外には見られないほど希少なものなのです。
ですので、チャーガ(カバノアナタケ)は β-グルカンの含有量も他のものよりも秀でており、天然のアガリクス茸と比べると3~4倍も含まれていると言われています。
チャーガ(カバノアナタケ)に含有される水溶性多糖類と不溶性多糖類の2つともに、抗腫瘍活性が確認されています。
ロシアではチャーガ(カバノアナタケ)の抽出液から作られた「ベフンギン」という抗ガン剤が公式な薬として国に認可されてもいるのです。
ロシアでは民間療法としてのチャーガ(カバノアナタケ)の歴史は長く、当然安全性・効能は素晴らしく、副作用についても天然成分ゆえに、一部の免疫抑制剤などを使われている方などを除き、心配要りません。
医薬品全般を否定するものではありませんが、化学生成物は副作用の心配がつきまといます。また、チャーガ(カバノアナタケ)のβグルカンは免疫力が弱い人には免疫強化し、強すぎる人には抑制する働きがあります。
つまり人体の免疫細胞を強化して免疫力を上げるだけではなく、人体のバランスも整えてくれるお薦めの効能をふんだんに成分として持つのがチャーガの特徴となります。
更にチャーガの特徴としてチャーガ(カバノアナタケ)にはβグルカンの中でも特に有用なβ1,3グルカンを多く含んでいます。
β1,3グルカンの研究論文の一部
- 1963年 βグルカンが、がん細胞の縮小に効果を持つことが初めて発表された。
- 2001年 酵母細胞壁β1,3Dグルカンは免疫細胞だけでなく、ヒトの皮膚線維芽細胞上の受容体に結合して皮膚組織修復を促進する、という実験結果が米免疫・感染症医療誌「Infection and Immunity」69(6)で発表された。
- 2005年 米外科医療誌[Neurosurgical Review]2005年28(4)号では、H.カヤリ博士、M.F.オズダグ博士等の研究陣が酸化ストレス状況に置かれたラットを使って実施したベータグルカンの抗酸化作用の実証実験が発表された。
- 2009年12月 宮崎忠昭教授の研究チーム(北海道大人獣共通感染症リサーチセンター)の実験結果から、インフルエンザウイルスに感染したマウスへβグルカンとEF乳酸菌の組み合わせを投与すると、インフルエンザウイルスに対する免疫力が高まり重症化を防ぐ効果があるという結果が発表された。
ウィキペディアより引用
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%921,3-%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3
・がん細胞に栄養を与えないように制御するベツリン酸
チャーガ(カバノアナタケ)に含まれている成分で注目されているこのベツリン酸という成分は、そもそもチャーガが寄生している白樺の樹皮に多く含まれているものです。
そしてチャーガ(カバノアナタケ)は、白樺の樹液を養分として育ち、白樺のガンとも言われるように、白樺を枯らしてしまうほど白樺の樹液の養分を10年20年とかけて小さな体内に取り込みます。
白樺の樹皮に多く含まれるベツリン酸(betulinic acid)には、がん細胞にアポトーシスを誘導する作用や、血管新生阻害作用などが報告されています。
ベツリン酸が、がん細胞のミトコンドリアの外膜の透過性を高めさせてアポトーシスを誘導する作用が報告されているのです。
アポトーシス誘導とは、固体をより良い状態に保つために行われる働きで、細胞死と呼ばれるメカニズムで不具合が起こっている細胞を自滅させ、優良な細胞だけを残していくということを指します。
このアポトーシス誘導があるおかげで、ガン細胞も死滅させ大きくなっていくことを抑制させます。ベツリン酸は、正常細胞には効きにくく、ガン細胞に特にアポトーシス誘導をするということが報告されており、ガンの治療薬としても期待されています。
ベツリン酸は、今現在問題になっている抗がん剤に抵抗性をもったがん細胞のに対して抗がん剤を効きやすくさせる効果があるとも報告されています。
血管新生阻害作用というのは、そもそも細胞の維持や増殖のため栄養を隅々まで送り届ける必要があるので、既存の血管から新しく血管を作るという作用を阻害するもので、血液から酸素や栄養を取り込まなければ血管を新たに作ることはできず 血管ができなければガン組織は1~2mm以上の大きさにも成長できません。
癌抑制遺伝子は血管新生を負に制御している。さらに、MMP阻害薬、VEGF受容体阻害薬及びPDGF受容体阻害薬などの薬物や可溶性VEGF受容体は血管新生阻害作用を示す。 サリドマイドが奇形を引き起こすのは、胎児の手足の末端の血管新生が阻害されて十分に成長しないためである。現在では、この作用を利用して抗がん剤としての利用が試みられている。 出典 ウィキペディア
なのでチャーガ(カバノアナタケ)に多く含まれるベツリン酸は、すぐにガン細胞と見極め血管新生を阻害する働きをする効果があるとして今後更に研究が加速することでしょう。
・SOD様物質による抗酸化作用
チャーガは「最高の抗酸化力をもつキノコ」と言われています。
参考 https://www.sup-pedia.com/ingredients/charga/
SODとはスーパー・オキシド・ディムスターゼという酵素のことです。
私達の体内にて、有害な活性酸素(有益な活性酸素も存在します)を分解する働きがあり、その主なものがSODです。
人間が体内にもつSODの量には個人差が見られ、尚且つ、SODの力は年とともに弱まっていくと言われています。
そこで嬉しいことに チャーガにはSODと同じような働きをするSOD様物質が含まれいるのです。
SOD様物質のおかげで チャーガ(カバノアナタケ)にはホウレン草の250倍・野菜ジュースの175倍・アガリクスの23倍の抗酸化力があります。
また、チャーガ(カバノアナタケ)にはSOD活性が非常に高いことが確認されています。最新の学術研究では、ウィルス以外でのいわゆる病気の90%は、有害な活性酸素が原因だそうです。
代表的な例としてがん、心筋梗塞、脳血管障害、動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病、肝炎、痴呆、しわ、シミ、吹き出物などの肌トラブルも活性酸素が関係していると言われています。活性酸素は常に体内で発生していますが、さらに大気汚染、化学物質、食品添加物、ストレスなどにより、多くの活性酸素が体内で発生するといわれています。現代病の主要因と言えそうです。
そういった現代病と闘わざるを得ない、現代人の必須成分であるSOD様物質を多く含むチャーガの効能がとても有益だと思われます。
特に天然100%であれば、安全生・副作用の心配は非常に少ないはずです。
・チャーガには食物繊維が豊富です
食物繊維の効能として、
1.有害物質を体外に出す。
2.第二の脳とも呼ばれる腸の働きを整える。
3.コレステロール値を下げる。
などが上げられます。
特に重要なことは チャーガにはリグニンという食物繊維が含まれていて、ポリフェノール以上に生活習慣病予防・発ガン性物質の活性を抑える・抗菌・抗酸化作用・ウィルス抑制作用があります。
ガンの原因として遺伝や生活習慣などが上げられますが、実はウイルスや細菌が深く関与するガンも存在します。
主なものとして子宮頸がんや肝臓がん、成人T細胞白血病などは、特定のウイルスへの感染が原因です。と言うことは、ウイルス性のがんは「ウイルスに感染しなければ、発症する可能性はほとんどない」ということになります。
チャーガに含まれるリグニンの効能でウィルス感染が防げる可能性が高まります。さらにチャーガから抽出されたリグニンで、強いHIV(エイズ)ウィルス抑制作用がある事が報告されています。
・副作用のないチャーガ
チャーガは毒性や副作用はなく、トラウマ、不安、肉体的疲労などのストレスへの抵抗能力を高める働きのある天然のハーブであるとされる「アダプトゲン」とされています。
ウィキペディアで「アダプトゲン」を調べると、アシュワガンダ、冬虫夏草、党参、エゾウコギ (シベリア人参)、ホーリーバジル、高麗人参 、イボツヅラフジ 、アマチャヅル、甘草(カンゾウ) 、マカ 、霊芝(レイシ)、ルージァ・カルタモイデス 、ロディオラ 、朝鮮五味子、チャーガ、シラジットと様々なストレスへの抵抗能力を高める働きのある天然のハーブが出てきます。
アダプトゲンとは「体に悪影響を与える物理的、化学的、または生物学的なストレスの原因を、非特異性の抵抗力を高めることによって撃退するもの」と定義されています。
▽アダプトゲンの定義
1 毒性 (副作用)がない。
2 作用が特定の臓器に限定されない。
3 正常化作用を持っている。
副作用はないと言われているチャーガですが、キノコアレルギーを持っている方は避けたほうがいいでしょう。またチャーガエキスを濃縮したロシア薬局方指定医薬品の「ベフンギン」というエキスタイプの抗がん治療薬では過敏症も禁忌としています。
引用 ロシア医薬品百科事典 http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4255.htm
チャーガは特に副作用や毒性がないため、飲み過ぎて良くないということは基本的にはありません。普段のティータイムや、私生活の飲料水の代用として健康のためにお茶として飲まれています。ノンカフェインで子供でも安心して飲めます。






































 ウドの実。
ウドの実。