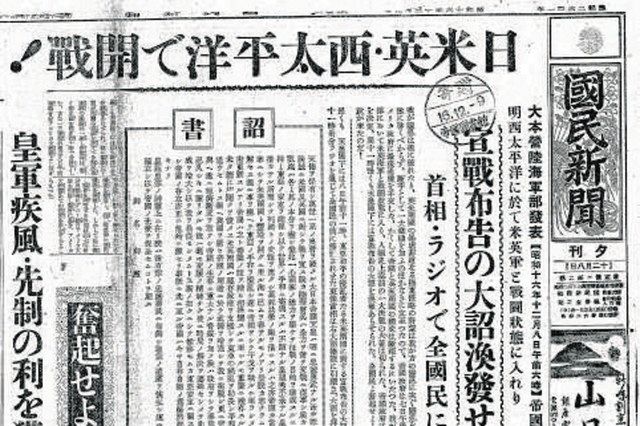マガジン9 2022年12月14日
「物価が何もかも上がっていて、本当に大変です」
「とてもじゃないけど年金では生活していけません」
「ただでさえ生活保護費が引き下げられて大変なのにこの物価高で限界です」
「水道料金の滞納で水道を止められ、それがきっかけで住む場所を失いました」
これらの言葉は、この数ヶ月で私が耳にしたものだ。
これを読んでいるあなたも、物価高は日々感じていると思う。何しろ総務省の消費者物価指数によると、今年10月の物価(生鮮食品のぞく)は前年同月比で3.6%上昇。これは1982年以来、40年ぶりの上昇率だという。食品だけでなく、電気・ガス代も上昇。このような状況を受け、毎週土曜日に東京都庁前で開催されている「もやい」と「新宿ごはんプラス」による食品配布には、11月末、過去最多の644人が並んだ。長引くコロナ禍と物価高というダブルパンチが今、庶民の家計を圧迫している。
そんな中、岸田政権がトンデモないことをブチ上げた。今後5年間の防衛費を、1.5倍超にするというのだ。その額、43兆円。社会保障費などについては常に「財源がない」ことを理由に削減してきた自民党政権だが、なぜか防衛費に関しては財源論はスルーされる。いや、スルーどころではない。岸田政権は財源の不足は増税により賄うことで合意したというではないか。いや、なに勝手に「合意」しちゃってんの?
東京新聞によると、物価高の影響で2022年の家計支出は前年比で9万6000円増えており、来年度はさらに4万円増えるという。そこに増税なんてされてしまったら。しかも来年には、フリーランスを潰すようなインボイス制度まで始まろうとしている。もう、本当にどうしてくれるのだろう。っていうか、岸田首相って、「聞く力」とか言ってなかったっけ? その力、どこ行った? あと、ここまで何も決められなかったのに、なんで国葬と防衛増税だけはそんなにすぐに決められるの?
さて、そんな憤りの中、ある記者会見に参加した。12月9日のことだ。それは生活保護基準部会の報告書に関する記者意見。
生活保護基準は5年ごとに社会保障審議会生活保護基準部会でそのあり方を議論され、来年度が生活保護基準見直しとなるのだが、その部会の報告書についての記者会見だ。
報告書は、75歳以上の保護利用者の生活扶助基準引き下げが懸念される内容となっているため、会見では、くれぐれも引き下げないこと、この物価高では保護基準の引き上げこそが必要だということがおのおのから訴えられた。
ちなみに物価高は今年に入って始まっているわけだが、部会でのもろもろの検証は19年の全国家計構造調査の結果を用いて行われており、現在の物価高はまったく考慮されていないという。これでは、実態をまったく反映していない。
それでも、「物価が上がったからといって急に保護基準を上げるのは難しい」という声もあるだろう。が、過去には年度途中で保護基準が引き上げられた事例がある。1973年から74年にかけての「狂乱物価」と言われた時期、年度の途中だが緊急的に保護基準が引き上げられたのだ。
ちなみに生活保護基準は第二次安倍政権下で史上最大の引き下げが強行されて13年から段階的に削減。それが今も保護利用者を苦しめている。これに対しては全国で引き下げを違憲とする裁判がなされ、大阪、熊本、東京、神奈川では引き下げに対して違法という判決が下されている。
この日、会見の席には生活保護を利用する2人の男性が登壇。どちらも引き下げ違憲訴訟の原告で、苦しい生活を語ってくれた。
58歳の男性は糖尿病がある身。ただでさえ13年からの引き下げで生活は苦しく、一週間の食費を1500円でやりくりしているという。そうなると、1日2食、お茶漬けと卵焼きという生活になる。しかし、この物価高でそれも厳しくなり、豆腐や納豆という生活に。体重は5キロ落ち、糖尿病の数値も悪化して医者には食生活の改善を指導されるものの、生活が苦しいのでどうにもならない。光熱費や通信費などの固定費はなかなか削れないため、食費を削るしかないという。
もう一人、54歳の男性もやはり食費を削っていることを語ってくれた。現在のように寒い時期は室内でもダウンを着て暖房費を削っているという。電気代の値上がりも痛い。去年は3000〜4000円だった夏の電気代が今年の夏は倍の7000円になったという。
「生活保護基準を上げてほしい」
二人は切実な声で訴えた。
保護基準引き上げに関しては、本当に人命に関わることなので喫緊の課題として国に取り組んでほしい。
さて、貧しい人を踏みにじるような施策はこれだけではない。
10月には、あまりにもひどい通知が厚生労働省から出た。それはホテル利用に関する事務連絡。
コロナ禍では、多くの人が家賃滞納でアパートや寮から追い出されるなどして住まいを失った。この2年半、そんな人たちの生活保護申請に私も少なくない数、同行してきたのだが、このような状態で生活保護申請をするとどうなるか。
コロナ以前であれば、「無料低額宿泊所」に入れられることが多かった。相部屋で、生活保護費のほとんどを取り上げられてしまうような劣悪なところも多いことで有名な施設だ。多くの人が逃げ出し、路上に戻る人が後を絶たないのだが、一度このような経験をすると「生活保護を受けるとまたあの施設に入れられる」と強い忌避感を持つことになってしまう。
それがコロナ禍で一変した。東京では、住まいがない人が生活保護申請した場合、1ヶ月ほどビジネスホテルに泊まることができるようになったのだ。その間にアパートを探し、転宅するという流れである。このようにして路上やネットカフェ生活からアパート暮らしに移った人がコロナ禍、多く生まれた。住まいがあれば、住民票も取れて仕事の幅もぐっと広がる。こうして、多くの人がピンチをチャンスに変えるようにして生活再建をしたのだ。
しかし、10月に厚労省から出た事務連絡は、そのホテル利用を著しく制限するような内容だった。これによって再び無料低額宿泊所に入れられる人が増えているという。その背景には、旅行支援によってホテルが埋まり、値段が高騰していることもあるようだ。
住まいのない人の唯一の命綱のような場を奪い、余裕がある人の旅行は支援する。これほど格差社会を象徴するグロテスクな光景はないだろう。この件については12月2日、困窮者支援団体らが東京都に要請をした(私も参加予定だったがコロナ陽性で行けなかった)。
もうひとつ、同日に都に要請されたことがある。それは、東京都では水道料金の滞納による給水停止が昨年より倍増している件について。共産党の和泉なおみ都議の質問によって明らかになったのだが、昨年の給水停止が10万5000件だったのに対して、今年の4〜9月だけで9万件にものぼっているのだという。
その背景には、検針員が水道料金を払えない人のもとに訪問して催告を行い、困窮者は福祉につなげる委託事業を「業務の効率化」を理由にやめたこともあるという。そうして現在、郵送による催告となったことが給水停止の倍増という事態を招いているというのだ。
その話を知って、最近、駆けつけ支援をした人のことを思い出した。私も所属する「新型コロナ災害緊急アクション」に、住まいも失い、残金もほぼゼロ円とSOSメールをくれた人のもとに11月、駆けつけたのだが、その人が住まいを失ったきっかけは水道の停止だった。コロナ禍はじめに宣伝された、水光熱費の支払い猶予の措置を覚えている人も多いだろう。多くの人が「助かった」と口をそろえる制度だが、減免措置が終わったとしても困窮している人の状況は変わらない。やむを得ず料金を払えずにいたところ、水道を止められてしまったのだという。
水道の停止は、命に関わることである。それが昨年と比較して倍増している事実を、どれほどの人が知っているだろうか。
さて、ここまでのことをまとめると、この国の政治の残酷さが浮き彫りになってこないだろうか。
防衛費は増やすけれど、水道は容赦なく止める。お金を持ってる旅行者は支援するけれど、住まいがない人のホテル利用は厳しく制限する。どんなに物価が上がっても、生活保護費を上げるという議論はない。そして実質賃金が7ヶ月連続で下がり続けているというのに「増税」などとブチ上げる。庶民の声を聞く気などさらさらありません、と言っているようなものではないか。
最近、ドイツの制度に詳しい人にある話を聞いた。
ドイツでは、家賃を滞納すると大家さんが行政に連絡するのだという。そうして役所の人が訪れて、家賃を滞納した人が福祉に繋がれるようにするそうだ。
翻って日本の場合、黙って追い出されるだけだ。水道だって黙って止められる。これまで、家賃滞納やライフラインの停止は絶好の「困窮を発見するチャンス」だと多くの人が指摘してきたし、私も書いてきた。が、「個人情報の壁」という言い訳で、発見できたはずの困窮は放置されてきた。
そんな状況を思うたびに、「国には、本気で命を守ろうという気概があるのだろうか」と疑問を持つ。そんな国で、防衛費を増やすことで命が守れると誰が本気で思うだろう。やるべきことは、その前にたくさんあるはずだ。
さて、そろそろ年末年始が迫っている。今年も相談会などの「命を守る」越年現場に張り付く予定だ。「聞く力」があるという岸田首相はぜひそのような現場を訪れ、厳しい状況に置かれた人々の声に耳を傾けてほしい。
今日は一日天気も悪く、時々吹雪く状態で外出もやめた。
昨日は雨も降り、積雪も少なくなったが、これからの予報ではずっと⛄マークが続いている。しばらく外出不能か?