新年を祝ったとばかり思っていたが、今日はもう1月の半ばです。なんとも駆け足の毎日です。
私のふるさと語で言うと、1月15日は「どんど焼き」の日です。住んでいる東京では何というのでしょうか。お正月、年神さまをお迎えするために、飾り付けた正月の縁起物をしまい。松などは焚き上げて始末をするのです。
わが家の属する町会はD八幡様が氏神様ですが、ここでは氏子たちのためのどんど焼きはしないようです。お隣の氏神様のH神社が「お焚き上げ」と表現して、15日10時からと案内をしていました。
神様は、地図の線引きで差別はなさらないだろうと、我が家は住み始めてすぐから、このH神社に持って行くことにしています。
昨年は15日が、確か大雪だったか冬の嵐だったか、出かけるのをあきらめたのでした。1年間、ビニール袋という仮住まいで、お過ごし願ったのでした。昨日は今年の分とまとめてよっこらしょと運んだのでした。
神は見放しはなさいませんでした。道中半分もいかないうちに、後ろから救いの声。「お手伝いしましょうか。自転車に積んで持って行きましょう、入り口に置いておきますよ」。息子と同じくらいのイケメン男子。縁起良し。
10時ピッタリから、神主さん二人での神事。独特な口調と、お辞儀。昔家を建てる時、地鎮祭をしたら、この動作がおかしいと、子供二人が、笑ってはいけないと真っ赤になってこらえているのが、こちらにも伝染して困ったことを思い出しました。
神事が終わって持ち寄ったもので小高く出来上がった小山に火がつくと思ったら、今日は神聖な炎を起こします。と写真の火おこしが始まりました。神主見習いさんが汗をかくほどに熱心にやるけれども、昨夜の雨は湿度を置いていったのか火がつかない。煙のみであきらめざるをえないよう。

私は留守番の夫が気になりそこで帰宅。本番はどうなったのやら。
下は一昨年のお焚き上げの炎。
子どものころ、ふるさとのどんど焼きで、書初めを練習した古新聞を、火にくべ、炎の付いたものを、竿の先で高く掲げ、放り上げて、字の上達を祈ったこともおいだしました。半紙は無く、古新聞に書いたのでしたね。



















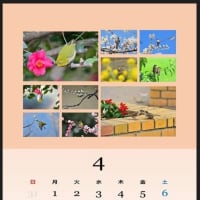


近くはすぐ帰宅も出来るのですが不精になったのか
忘れているのか?どちらかと言うと後者が多いでしょうか?
今朝も15日、小正月を忘れいつも朝食は小豆粥なのに
facebookの思い出を見て思い出しました。先が不安です。
私の故郷では個人の家単位で
お飾りなどを燃やしていました
その事実だけは僅かに覚えていますが
それがいつまで続いたのか・・
今でも古式ゆかしい「どんど焼き」が行われている
その事に、驚き感動しました。
素晴らしい景色を見せて頂き
有難うございました
ヤマグチに立派な八幡様があるのですね。朝倉のはささやかなものだったと覚えていますが。
懐かしい記事を読ませていただきました。ありがとうございます。