2月から始まった介護職研修も中盤に差し掛かった
今日からは実技中心の研修です。
今日の実技研修カリキュラム
①食事介護
研修者同士でペアを作って交互に介助者と介助される側に
なって食事を。介助者は半身まひの設定で口にテープを貼って
口があまり開かないようにして食べさせてもらう。これが
中々難しい、障害者の立場に立って、その不都合さが身を
持って体験できたし、介助側はどうあるべきかを理解できた。
②口腔ケア
口の中の清拭、歯磨きなどを体験、これもされる側とする側に
交互で実施、口の開け方が少ないので歯ブラシを差し込むのが
中々難しい。
③杖の介助(半身まひと視覚障碍者への介助)
実際に町にでて案内をしながら誘導することのむずかしさを
実体験した。歩道橋の渡り下りや歩道での誘導、杖の利用と
足の運び方。
結局は介助側とされる側のコミニュケーションが出来ていないと
うまくいかない、特に介護側がその人の尊厳と自立を介護すると
いう基本的なことを忘れないで実施することだと思う。
今後ますます多くなる高齢者と被介護者、そして2025年に
ピークとなる老々介護予想、介護する人と介護する施設の確保
などたくさんの問題も山積です。
なんだか疲れたがジムで一汗かいたらすっきりした、来週も
まだまだ続く・・・
今日からは実技中心の研修です。
今日の実技研修カリキュラム
①食事介護
研修者同士でペアを作って交互に介助者と介助される側に
なって食事を。介助者は半身まひの設定で口にテープを貼って
口があまり開かないようにして食べさせてもらう。これが
中々難しい、障害者の立場に立って、その不都合さが身を
持って体験できたし、介助側はどうあるべきかを理解できた。
②口腔ケア
口の中の清拭、歯磨きなどを体験、これもされる側とする側に
交互で実施、口の開け方が少ないので歯ブラシを差し込むのが
中々難しい。
③杖の介助(半身まひと視覚障碍者への介助)
実際に町にでて案内をしながら誘導することのむずかしさを
実体験した。歩道橋の渡り下りや歩道での誘導、杖の利用と
足の運び方。
結局は介助側とされる側のコミニュケーションが出来ていないと
うまくいかない、特に介護側がその人の尊厳と自立を介護すると
いう基本的なことを忘れないで実施することだと思う。
今後ますます多くなる高齢者と被介護者、そして2025年に
ピークとなる老々介護予想、介護する人と介護する施設の確保
などたくさんの問題も山積です。
なんだか疲れたがジムで一汗かいたらすっきりした、来週も
まだまだ続く・・・

















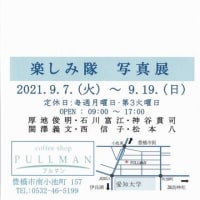

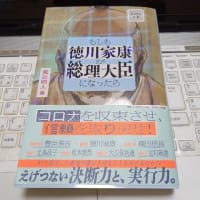

でも、本当にいい経験かと。
そういえばNHKで“ユマニチュード”という介護方法を紹介していましたが、わたし自身経験してきたことがそのままかなと思い見ていました。
コミュニケーションと信頼関係…難しいことですが、本当に大切なことですね。
本当に認知症は難しいですね、個人や家庭単位では
どうにもならないようにも思いますね。社会全体で支える
ことを問うた番組でもあるんですね。
厚生労働省の推計によりますと、その数は、今年全国で305万人と高齢者の10人に1人となる計算です。
そして、13年後の平成37年には470万人に達すると見込まれています」
この番組のフレーズは、
「見つめる」「話しかける」「触れる」「立つ」
“病人”ではなく、あくまで“人間”として接することで認知症の人との間に信頼関係が生まれ、周辺症状が劇的に改善する・・・そうありたいですね。