はじめに
世界が感嘆した日本人の国民性
平成23年3月11日、東日本の太平洋沿岸を未曾有の地震と津波が襲いました。
二万人を越える死者・行方不明者を出し、東京電力福島第一原子力発電所で
起こったあの深刻な事故が、日本国民の心を何日も衝撃と不安に揺り動かし続けました。
しかし、そうした中、この大災害に対処した日本人の冷静沈着な行動に対し、
世界中の人々が感嘆と称賛の声を寄せたことは、今なお記憶に新しいところです。
東京においても電車が全面ストップして帰宅難民があふれる中、やむをえず、
徒歩で家路を急ぐ人々に対して、沿道の企業や商店、学校などがロビーを開放して
休息所やトイレを進んで提供した事例が、テレビなどで数多く報道されました。
中には社員総出で帰宅する人々に、自社を開放していることを知らせ
「 皆さん頑張りましょう 」 と呼びかけた会社もあったといいます。
震災の翌朝、私が訪れた新宿駅では、帰宅が困難になった方々が階段に座って電車が
動き出すのを待っていました。しかし、誰が呼びかけた結果なのかよくわかりませんが、
座る場所もないくらい混雑している中でも、中央の通路だけは 「 通る人がいるから 」 と
空けてあったのです。
計画停電が実施された時には、電車の本数が削減されたこともあり、どの駅も乗客が
入れきれないような大混雑となりました。しかし、この時も一切混乱はありませんでした。
人々は文句をいうこともなく、ただひたすら駅員の指示に従い、整然と行列をつくって、
電車の来るのを静かに待ちました。
それを見たあるドイツ人が、「 日本国民はアーミーか 」 と叫んだそうです。
軍隊でしか考えられないような規律正しさを、日本国民は示したのです。
さらに、震災直後から続々と手を挙げたボランテイア希望者の数や義援金の総額など、
いずれも私の想像を越えるものでした。
こうした状況を、アメリカのニュース専門チャンネルCNNテレビは
「 住民たちは冷静で、自助努力と 他者との調和を保ちながら 礼儀を守っている 」 と報じ、
またハリケーン被害に遭ったニューオリンズのケースと比較しながら、
商店などの略奪行為について、「 そんな動きはショックを受けるほど皆無だ 」 と
仙台からリポートしています。
あるいは、中国の新華社通信の記者は、「 信号機が停電し、交差点に警察官も立っていない
のに、ドライバーはお互い譲り合い、混乱はまったくない 」 と驚きをもって伝えていました。
それだけではありません。中国国内では、避難所で十分な食料もない当初は、
被災者が順番を守り、列をつくって少ない食物を平等に分配し、しかも全員が
感謝の意を表しているニュース映像に、「 われわれ中国人は、モラル、道徳心の面では
まだまだ日本に遠く及ばない。被災した日本人に学ばなければならない 」 との声が
期せずして挙がったといいます。
日本人のDNAとなっている 「 教育勅語 」
私は大東亜戦争終結後、日本人は拠(よ)るべき心の支えを失い、「 このままでは、
日本は絶望的ではないか 」 という暗い気持ちになることも しばしばありました。
しかし、今回の大震災は、その廃(すた)れたと思っていた道徳心や倫理観が、
まだまだ日本人の心の中にDNAとして立派に生きていることを私に実感させてくれました。
それは、日本の美しい自然や風土の中で培われた先天的資質、という面も
あったかもしれません。しかし、やはり大部分は教育の結果だろうと思うのです。
昨年、「 トイレの神様 」 という歌が大ヒットしました。トイレ掃除が苦手な少女が
おばあちゃんからトイレには女神様がいるから、毎日一所懸命に掃除をすると
美人になれるよ、と教えられたという歌です。
聴いていて私などホロリとさせられた次第ですが、これと同じように震災に立ち
向かった人々の中には、道徳心や倫理観を大切にした戦前の教育を受けたおじいちゃんや
おばあちゃんから、息子、孫へと継承された 「 日本人の心 」 があったのだろうと思うのです。
それを培ったのは、戦前の 「 修身 」 教育であり、 「 修身 」 の骨格をつくった
「 教育勅語 」 だったと思います。こうした心の教育があって初めて、相手の思いやりや
礼儀正しさ、秩序を守る心などが育(はぐく)まれたのではなかったのでしょうか。
それと もうひとつ、今回の震災後の対応で感動的だったのが、わが身の危険も顧みず、
福島第一原発では現場に赴(おもむ)き、地震・津波の被災地では懸命に死者、行方不明者の
捜索・救援にあたった自衛隊員、消防隊員、警察官などの行動です。
例えば、自衛隊が福島原発での放水作戦に出動が決まった時のこと。
「 これはいわば覚悟の作戦だ。強制はしない。行ける者は一晩じっくり考えて
自分の気持ちを固めてほしい 」 と述べた上官の言葉に対して、
全員が躊躇(ちゅうちょ)なく 「 自分が行きます 」 と口をそろえて答えたといいます。
また、勤務先から直接、福島第一原発へ行くように出動命令が下った、ある消防レスキュー隊の
隊長が、家族に対して「 必ず帰ってくるから、それまで安心して待ってくれ 」 という
メールをしたところ、奥さんから 「 家族のことは心配なさらず、日本の救世主になって
ください 」 というメールが返ってきたという感動的な報道もありました。
まさに、自己犠牲をいとわず公のための任務を遂行するという、われわれのまぶたを
熱くするようなできごとがあったのです。
もちろん自衛隊員は、 「 事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、
もって国民の負託にこたえる 」 と宣誓して自衛官になっており、これは他の公務員とは
比較にならない重い義務だともいえるわけですが、その奥にあるのは、「教育勅語」にある
「 一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ、義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)シ 」 と
いう精神だったのだと思います。
こうした意識は、なにも自衛隊員や警察官などの公務員に限りません。
有名な話が、宮城県南三陸町職員で防災放送を担当していた遠藤未希さんです。
彼女は最後まで 「 皆さん、津波が来ます。逃げてください 」 という放送を続け、
最後に津波にのみこまれて亡くなりました。
たとえ自分の身は危険にさらされても、津波が来る瞬間までマイクを握り続けた姿は、
大東亜戦争の末期、樺太(からふと)の電話局で交換手をしていた乙女たちが、
ソ連軍が侵入してきたにもかかわらず最後まで職場を守り、 「 これが最後です。皆さん、
さようさら、さようなら 」 といって自決していった姿に重なります。
また、海水の侵入を防ぐために水門を閉めにいって津波に流された消防士も、
お年寄りを助けにいってそのまま波にさらわれ殉職した警察官もいました。
以下は岩手県の陸前高田市の市長さんから聞いた話です。
同市では六十八人の職員が亡くなられていますが、その大半が 「 危険だから行くな。
みんな避難しろ 」 という声を振り切って、市民を守るために職場を飛び出していった職員だった
とのことです。市長さんは 「 だから、亡くなった六十八人は、私にとって掛け替えのない
職員だったんです 」 と声をつまらせておられました。
自分の身を顧みず、勇気を奮い起こして 「 義勇公ニ奉シ 」 たこの人たちの姿は、
まさに 「 教育勅語 」 が説いた日本人の生き方そのものでした。
「 教育勅語 」 の精神が 今も精神のDNAとして日本人の心の中に残っていたとしか
考えられません。また、これらの話に感動した人たちも、そのことを思い起こしたのでは
なかったでしょうか。
このことは、アメリカ・ジョージタウン大学教授で日本文学の研究者でもある
ケビン・ドークさんが、
「 日本国民が自制や自己犠牲の精神で 震災に対応した様子は、
広い意味での日本の文化を痛感させた。日本の文化や伝統も米軍の占領政策などにより、
かなり変えられたのではないかと思いがちだったが、文化の核の部分は変わらないのだと
思わされた」( 『 産経新聞 』 三月二十五日 )
と論評していることとも重なり、とても的確な指摘だと感じました。
では、こうした日本人の良質な精神、行動を生み出した 「 教育勅語 」 とは、
どのようなものだったのか。改めてその成立過程から見ていくことにしましょう。
「 教育勅語は普遍的良心 」
http://thankfullife.blog.so-net.ne.jp/kyoikutyokugo
『 教育勅語 』 縦書き PDF ・ 書写用紙(A4)PDF
http://www.meijijingu.or.jp/kyouikuchokugo/pc/index.html#04
【 参考 】 漢字の検索 ( 筆順 )
http://kakijun.jp/main/kensakuyomi.html
世界が感嘆した日本人の国民性
平成23年3月11日、東日本の太平洋沿岸を未曾有の地震と津波が襲いました。
二万人を越える死者・行方不明者を出し、東京電力福島第一原子力発電所で
起こったあの深刻な事故が、日本国民の心を何日も衝撃と不安に揺り動かし続けました。
しかし、そうした中、この大災害に対処した日本人の冷静沈着な行動に対し、
世界中の人々が感嘆と称賛の声を寄せたことは、今なお記憶に新しいところです。
東京においても電車が全面ストップして帰宅難民があふれる中、やむをえず、
徒歩で家路を急ぐ人々に対して、沿道の企業や商店、学校などがロビーを開放して
休息所やトイレを進んで提供した事例が、テレビなどで数多く報道されました。
中には社員総出で帰宅する人々に、自社を開放していることを知らせ
「 皆さん頑張りましょう 」 と呼びかけた会社もあったといいます。
震災の翌朝、私が訪れた新宿駅では、帰宅が困難になった方々が階段に座って電車が
動き出すのを待っていました。しかし、誰が呼びかけた結果なのかよくわかりませんが、
座る場所もないくらい混雑している中でも、中央の通路だけは 「 通る人がいるから 」 と
空けてあったのです。
計画停電が実施された時には、電車の本数が削減されたこともあり、どの駅も乗客が
入れきれないような大混雑となりました。しかし、この時も一切混乱はありませんでした。
人々は文句をいうこともなく、ただひたすら駅員の指示に従い、整然と行列をつくって、
電車の来るのを静かに待ちました。
それを見たあるドイツ人が、「 日本国民はアーミーか 」 と叫んだそうです。
軍隊でしか考えられないような規律正しさを、日本国民は示したのです。
さらに、震災直後から続々と手を挙げたボランテイア希望者の数や義援金の総額など、
いずれも私の想像を越えるものでした。
こうした状況を、アメリカのニュース専門チャンネルCNNテレビは
「 住民たちは冷静で、自助努力と 他者との調和を保ちながら 礼儀を守っている 」 と報じ、
またハリケーン被害に遭ったニューオリンズのケースと比較しながら、
商店などの略奪行為について、「 そんな動きはショックを受けるほど皆無だ 」 と
仙台からリポートしています。
あるいは、中国の新華社通信の記者は、「 信号機が停電し、交差点に警察官も立っていない
のに、ドライバーはお互い譲り合い、混乱はまったくない 」 と驚きをもって伝えていました。
それだけではありません。中国国内では、避難所で十分な食料もない当初は、
被災者が順番を守り、列をつくって少ない食物を平等に分配し、しかも全員が
感謝の意を表しているニュース映像に、「 われわれ中国人は、モラル、道徳心の面では
まだまだ日本に遠く及ばない。被災した日本人に学ばなければならない 」 との声が
期せずして挙がったといいます。
日本人のDNAとなっている 「 教育勅語 」
私は大東亜戦争終結後、日本人は拠(よ)るべき心の支えを失い、「 このままでは、
日本は絶望的ではないか 」 という暗い気持ちになることも しばしばありました。
しかし、今回の大震災は、その廃(すた)れたと思っていた道徳心や倫理観が、
まだまだ日本人の心の中にDNAとして立派に生きていることを私に実感させてくれました。
それは、日本の美しい自然や風土の中で培われた先天的資質、という面も
あったかもしれません。しかし、やはり大部分は教育の結果だろうと思うのです。
昨年、「 トイレの神様 」 という歌が大ヒットしました。トイレ掃除が苦手な少女が
おばあちゃんからトイレには女神様がいるから、毎日一所懸命に掃除をすると
美人になれるよ、と教えられたという歌です。
聴いていて私などホロリとさせられた次第ですが、これと同じように震災に立ち
向かった人々の中には、道徳心や倫理観を大切にした戦前の教育を受けたおじいちゃんや
おばあちゃんから、息子、孫へと継承された 「 日本人の心 」 があったのだろうと思うのです。
それを培ったのは、戦前の 「 修身 」 教育であり、 「 修身 」 の骨格をつくった
「 教育勅語 」 だったと思います。こうした心の教育があって初めて、相手の思いやりや
礼儀正しさ、秩序を守る心などが育(はぐく)まれたのではなかったのでしょうか。
それと もうひとつ、今回の震災後の対応で感動的だったのが、わが身の危険も顧みず、
福島第一原発では現場に赴(おもむ)き、地震・津波の被災地では懸命に死者、行方不明者の
捜索・救援にあたった自衛隊員、消防隊員、警察官などの行動です。
例えば、自衛隊が福島原発での放水作戦に出動が決まった時のこと。
「 これはいわば覚悟の作戦だ。強制はしない。行ける者は一晩じっくり考えて
自分の気持ちを固めてほしい 」 と述べた上官の言葉に対して、
全員が躊躇(ちゅうちょ)なく 「 自分が行きます 」 と口をそろえて答えたといいます。
また、勤務先から直接、福島第一原発へ行くように出動命令が下った、ある消防レスキュー隊の
隊長が、家族に対して「 必ず帰ってくるから、それまで安心して待ってくれ 」 という
メールをしたところ、奥さんから 「 家族のことは心配なさらず、日本の救世主になって
ください 」 というメールが返ってきたという感動的な報道もありました。
まさに、自己犠牲をいとわず公のための任務を遂行するという、われわれのまぶたを
熱くするようなできごとがあったのです。
もちろん自衛隊員は、 「 事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、
もって国民の負託にこたえる 」 と宣誓して自衛官になっており、これは他の公務員とは
比較にならない重い義務だともいえるわけですが、その奥にあるのは、「教育勅語」にある
「 一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ、義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)シ 」 と
いう精神だったのだと思います。
こうした意識は、なにも自衛隊員や警察官などの公務員に限りません。
有名な話が、宮城県南三陸町職員で防災放送を担当していた遠藤未希さんです。
彼女は最後まで 「 皆さん、津波が来ます。逃げてください 」 という放送を続け、
最後に津波にのみこまれて亡くなりました。
たとえ自分の身は危険にさらされても、津波が来る瞬間までマイクを握り続けた姿は、
大東亜戦争の末期、樺太(からふと)の電話局で交換手をしていた乙女たちが、
ソ連軍が侵入してきたにもかかわらず最後まで職場を守り、 「 これが最後です。皆さん、
さようさら、さようなら 」 といって自決していった姿に重なります。
また、海水の侵入を防ぐために水門を閉めにいって津波に流された消防士も、
お年寄りを助けにいってそのまま波にさらわれ殉職した警察官もいました。
以下は岩手県の陸前高田市の市長さんから聞いた話です。
同市では六十八人の職員が亡くなられていますが、その大半が 「 危険だから行くな。
みんな避難しろ 」 という声を振り切って、市民を守るために職場を飛び出していった職員だった
とのことです。市長さんは 「 だから、亡くなった六十八人は、私にとって掛け替えのない
職員だったんです 」 と声をつまらせておられました。
自分の身を顧みず、勇気を奮い起こして 「 義勇公ニ奉シ 」 たこの人たちの姿は、
まさに 「 教育勅語 」 が説いた日本人の生き方そのものでした。
「 教育勅語 」 の精神が 今も精神のDNAとして日本人の心の中に残っていたとしか
考えられません。また、これらの話に感動した人たちも、そのことを思い起こしたのでは
なかったでしょうか。
このことは、アメリカ・ジョージタウン大学教授で日本文学の研究者でもある
ケビン・ドークさんが、
「 日本国民が自制や自己犠牲の精神で 震災に対応した様子は、
広い意味での日本の文化を痛感させた。日本の文化や伝統も米軍の占領政策などにより、
かなり変えられたのではないかと思いがちだったが、文化の核の部分は変わらないのだと
思わされた」( 『 産経新聞 』 三月二十五日 )
と論評していることとも重なり、とても的確な指摘だと感じました。
では、こうした日本人の良質な精神、行動を生み出した 「 教育勅語 」 とは、
どのようなものだったのか。改めてその成立過程から見ていくことにしましょう。
「 教育勅語は普遍的良心 」
http://thankfullife.blog.so-net.ne.jp/kyoikutyokugo
『 教育勅語 』 縦書き PDF ・ 書写用紙(A4)PDF
http://www.meijijingu.or.jp/kyouikuchokugo/pc/index.html#04
【 参考 】 漢字の検索 ( 筆順 )
http://kakijun.jp/main/kensakuyomi.html










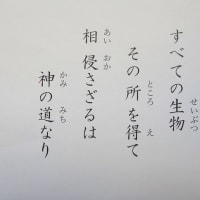
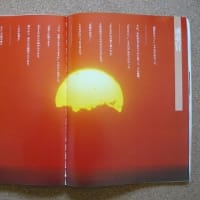
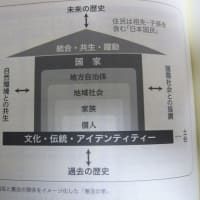


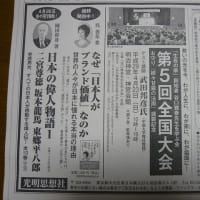
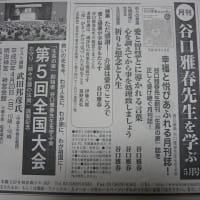
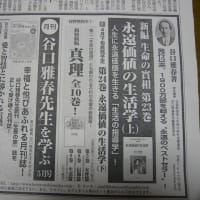



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます