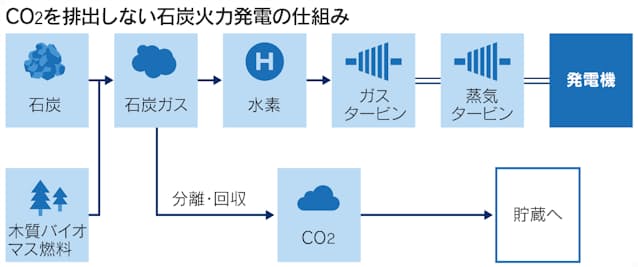関西電力の高浜原子力発電所。手前左から1号機、2号機と奥左から3号機、4号機(福井県高浜町)
三菱重工業は2025年3月期に原子力事業で過去最多となる約200人の採用を計画する。
東芝や富士電機も人員を増やす方針。福島第1原子力発電所の事故後、原子力を専攻する学生の減少に歯止めがかからない。
国の次期エネルギー基本計画で原発の新増設議論が進み、各社が事業拡大に備え始めるなか、技能伝承に必要な専門人員の確保が優先課題となってきた。
三菱重工の原子力事業の採用数(新卒とキャリア採用の合計)は24年3月期から約30%増え、過去最多となる見込み。
23年3月期の約100人に比べると2倍に増える。当面は200人規模の採用を継続する方針だ。
三菱重工の原子力事業の人員はグループ会社を合わせ約4400人。福島第1原発事故後は再稼働向け工事を中心に事業をつないできた。
政府が23年、グリーントランスフォーメーション(GX)基本方針に原子力活用を明記したのが転機となった。原子力事業は成長をけん引する「伸長事業」に位置づけが変わった。
原子力事業の売上高は24年3月期に3000億超となり、18年3月期の2000億円弱から1.5倍に拡大した。直近の24年4〜6月期も受注高が前年同期比28%増の686億円だった。堅調な成長が見込まれ、人材確保に力を入れる。
原発向け設備製造を手掛ける富士電機は関連事業の人員を増やす計画。
技術者の高齢化に加え「30年代の技術として注目される高温ガス炉の設備設計を担う人材獲得が急務」(同社)という。
事故を起こした福島第1原発と同じ型で、今秋にも事故後初の再稼働が予定される沸騰水型軽水炉(BWR)を手掛ける東芝も23年に比べ原子力関連部門の採用人数を増やす計画だ。
原発産業の景況感、大幅に改善
日本原子力産業協会(原産協、東京・千代田)が23年に実施した調査では会員企業など約240社のうち現在の原発産業の景況感を「普通」と答えた企業が44%と前年から15ポイント増加した。
「悪い」と答えた企業は48%と同20ポイント減少し景況感が大幅に改善している。

原発再評価は国内にとどまらない。原子力発電は気候変動対策に適した事業を分類する欧州連合(EU)の「EUタクソノミー」で条件付きで「適格」と認定された。
第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)で日米など22カ国が50年までに世界の原発設備容量を20年比で3倍にすることを表明するなど、各国が原子力活用にカジを切った。
米モルガン・スタンレーは6月、「原子力ルネサンスがやってくる」と題したリポートを発表した。
00年代後半に世界各国で建設計画が相次ぎ、原子力ルネサンスと表されたが、その再来との見立てだ。50年にかけて総額1兆5000億ドル(約210兆円)の投資が行われる可能性があるとした。
原発人材の減少が課題
原発が再脚光を浴びる一方、日本の原発人材の減少が課題だ。
原子力白書によると22年度の原子力関連学科入学者数は185人と福島第1原発の事故後最低になった。事故が起きた10年度の317人から4割減少した。
国内の原子力関係従事者自体は5万人程度で推移するものの、同白書は「国内での原子力発電所の新規建設が中断していることから、建設計画の従事経験者の高齢化が進み、技術継承が課題となっている」と指摘する。

人材が不足するメーカー各社も技能伝承に知恵を絞る。日立製作所はIT(情報技術)を原発建設作業の技術伝承や人材育成に活用する。
例えば、メタバース(仮想空間)空間内に原子炉建屋や原子炉をデジタルデータで構築し、工事手順の確認などの情報共有に生かせるようにした。
デジタル技術で技能伝承
日立の国内原子力部門の従業員数は約4000人で、定期採用を続けてきたことで人員数は微増傾向という。
国内の新設計画が途絶えたことで社内の建設技術は低下していくとの危機感が強く、デジタル技術を駆使して技能継承を急ぐ。
東芝は若手・中堅といった現場での経験が不十分な人材に対し、3DCAD(コンピューターによる設計)を活用して技術継承している。
原発の操作室を模したシミュレーターを設け、プラントの操作などを定期的に学べる。プラントが稼働していなくても、工事やエンジニアリング技術も3DCADから習得できるという。

電力会社はサプライチェーン(供給網)全体の技術継承支援に動く。
関西電力は7基の原発が立地する福井県内の企業を対象に定期検査や廃炉作業の工事に関する技能研修をしている。
講師役はプラントの電気計装事業などを手掛けるクリハラント(大阪市)の技術者らで、受講者の経験年数や技能レベルを勘案しながらポンプの分解や点検、溶接などの実技研修に取り組んでいる。5社28人が参加した。
「ベテラン社員の大量退職が続くなか、運転ノウハウの継承も課題」(関電の原子力事業本部)。特に原子炉の起動作業に重きを置き、炉の昇温や昇圧のさせ方、制御棒の操作など手順書やマニュアルにはない技能の共有に力を入れている。
原発の新増設を見据え人材獲得や技能伝承に力を入れる民間各社。40年度の電源構成を決める次期エネルギー基本計画は日本の原子力産業の再興を左右する。

村上芽日本総合研究所創発戦略センター チーフスペシャリスト
ひとこと解説
筆者が社会人になった25年前でもすでに「原子力学科」といえば相当レア人物に出会った、という感覚でしたし、人材プールの減少はいまに始まったことではなさそうです。
工事や発電以上に気になるのは、廃炉や放射性廃棄物の処理プロセスに関われる科学者、技術者がい続けてくれるのかということです。
自分にはとても学び直せそうにない分野だけに「誰か」頼みにはなってしまうのですが、負の遺産処理のイメージが強く、どうビジョンを描くのか、心配なことだらけです。
<button class="container_cvv0zb2" data-comment-reaction="true" data-comment-id="45976" data-rn-track="think-article-good-button" data-rn-track-value="{"comment_id":45976,"expert_id":"EVP01139","order":1}">
 24
24</button>
原発再稼働関連のコンテンツを集めたページです。柏崎刈羽原発や女川原発などの状況や課題点などをお伝えします。
日経記事2024.09.18より引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de0f42fcb12d2f61bd6c854d9ff49ae6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=51b3b79b08a262b01981a250fc5a25cd 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de0f42fcb12d2f61bd6c854d9ff49ae6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=51b3b79b08a262b01981a250fc5a25cd 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de0f42fcb12d2f61bd6c854d9ff49ae6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=51b3b79b08a262b01981a250fc5a25cd 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de0f42fcb12d2f61bd6c854d9ff49ae6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=51b3b79b08a262b01981a250fc5a25cd 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de0f42fcb12d2f61bd6c854d9ff49ae6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189207005082024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=51b3b79b08a262b01981a250fc5a25cd 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b9544baeb045931015e5c42c9282d13 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=661ba2ea2071e56c412a0067195e71fa 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b9544baeb045931015e5c42c9282d13 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=661ba2ea2071e56c412a0067195e71fa 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b9544baeb045931015e5c42c9282d13 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=661ba2ea2071e56c412a0067195e71fa 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b9544baeb045931015e5c42c9282d13 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=661ba2ea2071e56c412a0067195e71fa 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b9544baeb045931015e5c42c9282d13 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5189329005082024000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=661ba2ea2071e56c412a0067195e71fa 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>