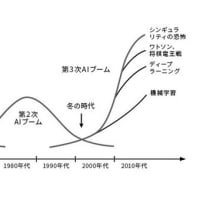太陽光はこれまで大型開発が中心だった(双日が出資する飯塚上三緒太陽光発電所、福岡県飯塚市)
太陽光開発の主軸がメガソーラーから小型発電所に移ってきた。
双日はメガソーラー中心の開発を転換し、2026年度までに出力が小さい発電所を3000カ所開発する。
メガソーラーは用地不足などで開発ペースが鈍化している。
伸びが期待される風力はインフレで導入コストが上昇する中、再生可能エネルギーの普及へ小型太陽光の重みが増している。
双日は26年度末までに平均出力100キロワット程度の小型発電所を開発する。
合計規模は30万キロワットで、出力1000キロワット以上のメガソーラー300カ所分に相当する。総事業費は500億円。開発は地元の施工会社に委託。すべての発電所を双日が一括で管理し、電気は企業向けに直接販売する。
既存の発電所に隣接した土地や遊休農地などを使う。
分散する小型発電所は管理コストが高くなりがちだが、デジタル技術でコストを抑える。時間ごとの発電量や異常の発生はリアルタイムで監視する体制を整える。

双日は12〜18年の累計で約30万キロワット分の太陽光を開発し、ほぼ全てがメガソーラーだった。
ただ、その後は固定価格買い取り制度(FIT)の価格が下がり、用地確保も難航したため、メガソーラーの新規開発は23年末に公表した1件のみ。担当者は「今後もメガソーラーは手掛けるが、主軸は小型にする」という。
経済産業省によると、23年度に政府の補助制度などを使って導入された太陽光は全国でピーク時の3分の1程度。メガソーラーは22年度と比べて4割減った。
山地が多い日本は適地が不足しており、近年は自治体も規制に動いている。福島市は土砂災害リスクや景観の悪化を懸念し、23年に「ノーモアメガソーラー(メガソーラーいらない)」を宣言し、25年4月に規制条例を施行する。
太陽光コンサルティングの資源総合システム(東京・中央)の杉渕康一上席研究員は「直近の大型案件の多くが過去に権利を取得していた発電所だ。
新規開発は難しくなっている」と話す。日本の限られた土地で太陽光を導入するには小型化が不可欠になっている。

保守サービスのデジタル化も小型シフトを後押ししている。
オリックスはドローンを使って点検し、異常を人工知能(AI)が自動で分析するサービスを手がける。太陽光発電所保守で最大手のスマートエナジー(東京・港)は遠隔自動監視のシステムや複数の発電所の業務を一括管理するサービスを展開、小型太陽光向けにも提供する。
こうした背景から小型発電所に軸足を移す企業は多い。ENEOSホールディングス(HD)やレノバも今後の開発は小型を主軸にする。
東京ガスが出資する新電力TGオクトパスエナジー(東京・港)も施工企業に出資して進出し、3年で数百カ所以上を開発する。30年までの開発の中心を小型が担う見通しだ。

中規模の開発には主に遊休地などを使う(レノバの太陽光発電所)
資源エネルギー庁によると、太陽光が全電源の発電電力量に占める割合は9.8%(23年度、速報値)で、再生エネで最も普及している。
再生エネ開発で風力が多い欧州に対し、日本はメガソーラーが主導して導入量を増やしてきた。日本は平地面積あたりの太陽光の導入量は21年度時点で1平方キロメートルあたり514キロワットと、ドイツの2倍以上で世界最大規模だ。
政府が示す30年時点の電源構成の見通しは、発電電力量ベースで太陽光は22年度の1.4〜1.6倍に対し、風力は5.5倍。
今後の伸び率が高い風力はインフレで導入コストが上昇しており、再生エネの普及には太陽光の充実も欠かせない。
30年時点でも再生エネ全体では太陽光が最大規模を維持する。
今後は小型太陽光のほか、薄く折り曲げられ、既存の太陽光パネルが設けられない場所にも設置できる次世代電池「ペロブスカイト型太陽電池」などの導入拡大も期待されている。
日経記事2024.12.02おり引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=99c9b054f1d6c98cd92baf4486e05989 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f5f7a55e25bdd85cbd2bcf62b91edc51 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=99c9b054f1d6c98cd92baf4486e05989 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f5f7a55e25bdd85cbd2bcf62b91edc51 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=99c9b054f1d6c98cd92baf4486e05989 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f5f7a55e25bdd85cbd2bcf62b91edc51 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=99c9b054f1d6c98cd92baf4486e05989 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f5f7a55e25bdd85cbd2bcf62b91edc51 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=99c9b054f1d6c98cd92baf4486e05989 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5464773009102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f5f7a55e25bdd85cbd2bcf62b91edc51 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4a7a9c64dfdf5e6efc36b5d9a821a768 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=95422e14c84d0a98ff61d2a6fa611e9b 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4a7a9c64dfdf5e6efc36b5d9a821a768 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=95422e14c84d0a98ff61d2a6fa611e9b 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4a7a9c64dfdf5e6efc36b5d9a821a768 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=95422e14c84d0a98ff61d2a6fa611e9b 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4a7a9c64dfdf5e6efc36b5d9a821a768 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=95422e14c84d0a98ff61d2a6fa611e9b 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4a7a9c64dfdf5e6efc36b5d9a821a768 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5465848009102024000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=95422e14c84d0a98ff61d2a6fa611e9b 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=15bbd76f3243be1ea691228e83fe4f4e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=993&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8ec483ed7eefdace3895ad4d16fcd882 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=15bbd76f3243be1ea691228e83fe4f4e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=993&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8ec483ed7eefdace3895ad4d16fcd882 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=15bbd76f3243be1ea691228e83fe4f4e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=993&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8ec483ed7eefdace3895ad4d16fcd882 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=15bbd76f3243be1ea691228e83fe4f4e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=993&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8ec483ed7eefdace3895ad4d16fcd882 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=15bbd76f3243be1ea691228e83fe4f4e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5497862017102024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=993&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8ec483ed7eefdace3895ad4d16fcd882 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>