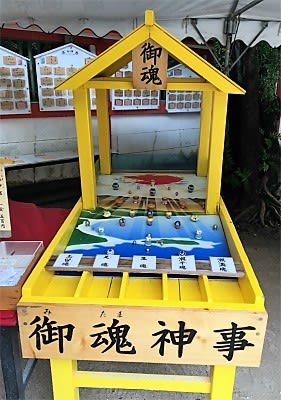その1からの続きです。
● 鵜戸神宮へ
この日の東京は朝から大降りの雨。
羽田空港に着いた時には傘はずぶぬれになっていましたが、宮崎に来てから急速に乾いています。
そもそも、こちらのみなさんがさしているのは日傘。
ピーカンの下で雨滴がしたたる傘を持つ私は、突然どこかから時空を超えてきた異星人のようです。
バスは堀切峠を越え、サンメッセを抜けました。
鵜戸神宮で途中下車します。
前々から、ここに参拝したかったんですよね~。
最寄りのバス停についてから本宮までは、山をひとつ越えていく、かなり大変な道のり。
階段を上って鵜戸岬隧道を通り、八丁坂を下っていきます。

茅野輪があったので、ぐるぐる周ってお参りします。
海からの強い風にあおられ、眼下の岩には荒波が打ち付けます。

太平海の荒波が打ち付ける岩壁の上に建つ神宮。
こんなに海際に立っている神社も、ダイナミックで珍しいですね。
朱塗りの橋の欄干から、広々とした太平洋を見渡せます。

● 洞窟の中の本殿
本宮入口に着いてからも長い参道が続き、かなり歩いた末に、本殿にたどり着きました。
海辺の崖にできた狭い洞窟の中に、こっそり隠れるかのようにありました。

薄暗い中、周りをぐるりと一周します。
頑丈な岩に守られているので、保存状態もよく色彩鮮やか。
全面に立派な彫刻が施されています。
● 運玉投げ
洞窟内の本殿だけでなく、海に面した亀石そばのお社も鮮やかな朱色。
潮風や波による色落ちが早い場所で、この美しい色を保つのは大変だろうと思います。

霊石の亀石に向かって、大勢の人たちがワイワイと運玉を投げています。
場内ピッチャーが多すぎだし、一人旅だし、なにより球技がすこぶる下手な私は、静かに見学に徹します。
亀石の背中の桝形の窪みはとても小さく、そこめがけて運玉を投げるなんてどだい無理そうでしたが、皆さんかなりの確率で、入れていました。
すごいわ!さすがはプロ野球チームのキャンプ地!(関係ないか)

うねるように押し寄せてくる荒波が、お宮前の岸壁に当たり、しぶきが辺りに飛び散ります。
ごうごうとした海の音と強風にあおられ、(長居は危険)という警報が心の中に鳴り響きます。
脚を踏ん張って海を眺めるだけでも、激しい自然を前に、ドキドキが止まりません。

いつか言ってみたいセリフ:「ご武運を」
● ウとウトウ
鵜戸(うと)神宮の名前に、青森にある善知鳥(うとう)神社を思い出します。
ウもウトウも、どちらも海鳥ですし、響きが似ているので。

鵜戸神宮は、聞きしに勝るすばらしい場所でした。
青島神社も、鵜戸神宮も、かなり危険と隣り合わせの、ワイルドな自然の中にあります。
さすがは神話のふるさと、宮崎県の聖地は、シチュエーションがダイナミックですね~。
韓国・中国の人たちが大勢参拝に来ており、日本人よりも多いようでした。
にぎやかな団体行動なので、そう感じたのかもしれませんが。
● 日南市のマンホール
メジロと梅の花がデザインされた、きれいなマンホール。
これは2009年に合併された新・日南市の鳥がメジロだからだそう。

旧・日南市の市の鳥はカワセミで、市の合併に伴ってマンホールの鳥が変わったことになります。
新・日南市となった旧・北郷町町の鳥がメジロで、そのまま市の鳥に格上げになったようです。
メジロとカワセミ、どちらのマンホールもあったら、道を歩くのが楽しくなりそうですが、行政上はそういうわけにもいかないんでしょうね。
カワセミバージョンは、どんどん減っていき、もうなくなっているかもしれません。
市町村合併があると、マンホール好きは生き急がなくてはならないのです・・・!
● 九州の小京都、飫肥
ここから再びバスに乗り、日南海岸沿いにさらに南下します。
海岸沿いのカーブ道をバスは結構なスピードで走り続け、荒々しい波をずっと眺めていきます。
次は終点まで乗っていきました。
降りたのは、飫肥。・・・読めませんね。オビです。

ここは藤原氏南家の子孫、飫肥藩・伊東氏の5万1千石の城下町として栄えた町。
武家屋敷を象徴する門構え、風情ある石垣、漆喰塀が残る町並みは、昭和52年に重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

城跡を訪ね、武家屋敷を巡ります。
昔ながらの町並みが残されていて、時が止まったままのようないい雰囲気。
その美しさから、「九州の小京都」と呼ばれています。

朝ドラ「わかば」(2004年)の舞台にもなったそう。
● かつおめし
気がつけば3時になっていたので、飫肥天で知られる「蔵」でランチにしました。

飫肥の名物、おび天と宮崎の郷土料理、かつおめし。
カツオのお刺身茶漬けにゴマと海苔をまぶした、素朴な味です。

● 鯉と城下町
食後、はらごなしにまた町を散策。
遊泳地には、鯉が泳いでいました。
鯉が泳ぐ城下町を散策した場所は、島根の津和野、長崎の島原、そしてここ飫肥になります。
忘れている場所はなかったかな?とネット検索しましたが、ほかの場所はヒットしません。
ということは、もしかするとこの三カ所だけなのでしょうか。なんだか貴重な気がしてきました。

「鯉と城下町」という言葉から「恋とマシンガン」の歌を思い出して、LaLaLa~♪と口ずさみました。
フリッパーズ・ギター、なつかしい!
予定より1時間遅れのバスに乗ってきたため、ここの観光を1時間減らして、帳尻を合わせます。
ゆっくり過ごしたいすてきな場所なので、後ろ髪を引かれる思いですが、
4時発の宮崎駅行きの最終バスに、どうしても乗らなくてはいけないのです。

● 木のバス停
ところが、帰りのバス停が見つからずに、車通りをうろうろ。
どっちに行けばバス停があるのか、わかりません。
刻々とバスの時間は近づいてきています。
乗れなかったら、どうしよう・・・!
地元の人に聞きたくても、通りには誰も歩いていません。
困って、間口の狭い洋菓子屋さんに飛び込み、「すみませ~ん」と奥に声をかけて、たずねました。
「普通のバス停よりも背が低くて、木でできているから、見落とさないでね」
と三角巾姿のおばさんに教えてもらいます。

今度こそ見つけなくちゃと、目を皿のようにして探していくと、それらしいものがありました。
探し求めていたバス停です。ああよかった。
たしかにうっかり通り過ぎてしまいそうなほど、目立たちません。
通りの向こうからバスがやってきます。それになんとか間に合いました。
● 二つの駅

渋いJR日南線の日南駅の駅舎。駅前に銅像が立っていました。
服装から、伴天連さんかと思ったら、遣欧天正少年使節の伊東マンショでした。
彼の名前は伊東さん・・・そう、飫肥藩の日向伊東氏一族だったんですね。
次に、真っ赤な駅舎の前を通ります。
ここはJR日南線の油津(あぶらつ)駅。

駅名よりも大きく書かれたCarpの文字。壁にはカープ君も描かれています。
カープの赤が駅舎の色になっているんですね。
日南市は広島カープのキャンプ地。
「キャンプ地最寄りの油津駅を日本一のカープ駅にしたい!」という地元カープファンの夢を、JR九州が実現したそうです。
● 波乗りサーファー
終バスなのにしばらく私一人の貸し切り状態でしたが、鵜戸神宮前からは満員バスになりました。
あいかわらず波は高く、行きにはいなかったサーファーの姿もちらほら見るようになりました。

黒い点がサーファーです。今日の波の荒さは特別かも。

まるでイメージ画像。日南海岸は、絵になりますね~。

普段見慣れた横浜や湘南の海とはまた違う、宮崎の海。
もっとワイルドで荒々しい感じがします。
この辺に住んでいたら、サーフィンをやりたかったなあと思います。
湘南はサーファー人口が高いし、ファッション化されているし、人の目も現地ルールもありそうですが、こちらではそういうことは気にせず、のびのびやれそうなので。

● 平和台公園
宮崎空港でバスを降り、ここから路線バスに乗り換えます。
橘通り二丁目で乗り換えて、終点の平和台で降りました。
ここにある巨大な石の塔を、見たいと思ったのです。
1940年の建造当時は日本一の高さだったという、37メートルの塔。
見ようによっては蟻塚に見えなくもありませんが(!)、塔の四方に4人の巨人の像が立ち、各方角を守っています。
「勇」「親」「愛」「智」の四魂を表している、4.5mの像だそう。

塔には『八紘一宇』と書かれています。
日本書紀に見られる世界平和を意味する造語ですが、当時は大東亜共栄圏のための戦争スローガンとして使われた言葉でした。
第二次世界大戦終了後、GHQは八紘一宇の碑文と塔の像を撤去したそうです。
今はどちらも変換されて「平和の塔」として静かに存在しています。
平和の塔というにはかなり厳めしい武骨な形ですが、歴史(戦争)遺産として重要な建築物です。
謎めいた巨大な遺跡は、メキシコのピラミッドのようでもあります。

塔から宮崎市街を眺めると、地球が丸く見えました。
● はにわの森
公園の奥には、はにわの森がありました。
辺りに点在する無数のはにわたちは、400体くらいいるそうです。

ユーモラスなはにわがたくさんいるエリア。
ファンシーですが、夕暮れ時に彼らと向き合うのは、ちょっとこわいです。

少しずつ光が陰っていく、うっそうとした森の中。
「こっちだよ」と彼らに引っ張られたら、このまま人間の世界に戻れなくなりそう。

同じ形のものが集まって、ゲシュタルト崩壊しているところもありました。
(だるまさんが転んだをしているみたい)と思って彼らを見ると、みんな同じ格好をしたまま、ピクリとも動きません。
なんだかゾ~ッとしました。
かといって、彼らがガサガサと動いたら、もっと怖かったはずですが!
先ほどの塔の広場まで、ほんの数十メートルしか離れていないのに、ここは私と埴輪たちしかいない異世界。
(暗くなる前にこの森から出よう)と、早足で人のいる方に戻りました。
● すみません、回送中です
公園発のバスに乗ったのは、中国人の観光客と私の3人だけ。
町の中心部で乗り換えます。

走ってきた回送中のバスには「すみません、回送中です」との表示が出ていました。
これまで「回送中」の3文字しか見たことがありませんでしたが、謝ってくれてる!
優しいですね。宮崎の人のイメージが高まります。
● ボンベルタ
町の中心部の道路はとても混雑していました。
「ボンベルタ」というバス停の響きがとても引っ掛かります。
(猪木ボンバイエみたい)と愉快な気分になりました。
ここでほとんどの乗客が降りたので、町の中心地なのでしょうか。
周りの建物を見ても、ボンベルタなる店名は見つけられませんでした。

後で調べたら、「ボンベルタ橘」という百貨店がある場所だそうです。
● フェニックス号
日暮れ近くなってきました。観光できない夜の間に長距離移動をしようと、宮交シティから19時発の福岡行きフェニックス号に乗りました。
ここでいうフェニックスとは、不死鳥のことではなく、ヤシの木のことですね。もうわかりますよ。

宮崎駅、夜空に浮かび上がる満月とフェニックス。
バスに揺られて4時間半。眠っているうちに23時半に博多に到着し、寝ぼけまなこで駅前のホテルにチェックイン。
一日バスに揺られて、GWの神奈中バスの日々を思い出した一日になりました。
2日目に続きます。
<script type="text/javascript" src="chrome-extension://hhojmcideegachlhfgfdhailpfhgknjm/web_accessible_resources/index.js"></script>