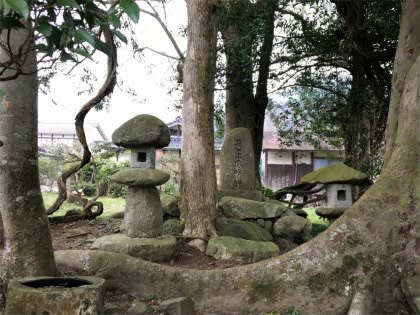2日目からの続きです。
● 東山通を歩く
3日目-4日目は、京都大学で行われる学会に参加します。
朝早く起きると、気持ちのいい天気。
そこでバスには乗らずに、七条から京大まで歩いてみようと思いました。
京都の中心街を東西に横切る通りは、一条から十条まで数の名前がついています。
私が歩くのは、智積院~清水寺~八坂神社~熊野神社~京都大学を結ぶ、いつも車が混雑するルート。
その京都府道143号、別名東山通(東大路通)を歩いて行きます。
距離は5キロ、歩くと1時間ほどかかる予定。
バス通り沿いなので、途中で無理だと思ったら、そこからバスに乗ればいいですね。
では出発~。思ったよりも歩きやすい道で、嬉しくなります。
出発地点の智積院付近は、京都駅から緩やかな坂を上った小高い場所にあるため、祇園まではゆるやかな下り道が続いて楽なのです。
● 朝の消防訓練
東山消防署では朝から隊員たちが訓練をしていました。

ここ、いつも通るたびに大がかり練習をしています。
消防隊員は常日頃、訓練を重ねているのかしら?バス通りだから目に留まるのかな?

知恩院の参道

琵琶湖疎水と十石舟
朝なので、車道も歩道もまだ混んでいません。
快適に歩き始めてからちょうど30分で、東山駅前に着きました。
● 京都大学吉田寮
さらにまっすぐ道を進み、熊野神社前を越えて、1時間ほどで京都大学に到着。
撤去問題で噂になっている学生自治下の吉田寮は、思ったより新しい感じ。

希望者は見学もできるようです。
建物を眺めながら、森見登美彦の小説『四畳半神話大系』のカオスな空間を連想していると、学生が寮から出てきました。
神話大系に取り込まれそうになったので、そろそろと後ずさって元の通りに戻りました。
● 京都大学の時計台
京都大学に到着。1年ぶりの百周年時計台記念館。

去年も京大の学会に参加しましたが、今回はポスター発表をします。
受付の人に「先生」と呼ばれて、慣れない呼び名にドキドキしました。
● カフェ・コレクション
午前中は口頭発表に参加し、昼には顔見知りの人たちとランチ。
森見登美彦の小説にも登場する、農学部前のカフェ・コレクションに行きました。

森見さんはたらこパスタが好きだったようですが、私は名物のオムライスを注文。
巨大なオムの登場にビックリ。これで680円というコスパの良さに、二度ビックリ。

店内はシックですが1Fは喫煙OKというのが、古くからの喫茶店ぽい感じ。
みごとに愛想がない店員ばかりで、塩対応の洗礼を受けます。
これもまた学生街っぽい感じ。

カフェの本棚にあったのは坂口安吾作品集で、森見作品はありませんでした。
モリミー、がんばれ!
● ポスターセッション
ビッグなオムでおなかいっぱいになって大学に戻ります。
午後はポスターセッション。
始まるまではガチガチに緊張していましたが、いざ発表時間になってみると、大勢の人に説明をし、受けた質問に答え、意見交換をしているうちに時間が経ちました。
終わってみればあっという間の体験。
A1サイズのポスターをしょってきた甲斐がありました。
結果オーライでよかったよかった。
(でも写真を撮る心の余裕はありませんでした!)
● モダンな大学寮
発表が無事に終わり、その後の参加者セッションに参加して、この日のプログラムは終了。

もう日が暮れかかる時間になっていました。
帰りのバス停には、参加者たちの長い行列ができていたので、連れの参加者2人と出町柳駅まで歩いていくことにします。
レトロモダンな建物がありました。
京都大学YMCA会館の地塩寮です。
大正2年、ヴォーリズの設計。
素敵ですね。吉田寮よりもこちらに入りたいなあ。

連れのリクエストで、鴨川の土手道を少し歩いてみることにしました。
「神田正輝がいるかもしれない!」と言うので
「え、カッパみたいに?」と驚いて聞くと
「いやいや、棲んでるわけじゃないから!」と笑われます。
なんでも2時間推理ドラマで、事件解決後に神田正輝と片平なぎさがのんびり鴨川のほとりを歩くエンディングシーンが多いんだそう。
でもこの日は風が強く、とても寒い日。
ピューピュー吹きすさぶ川風に、身体の芯から冷えます。
「寒くて無理!正輝もなぎさもいないよ!」
地下の京阪ホームへの階段に避難しました。
● 繁華街で遭難
そのまま京阪に乗って四条駅で降り、新京極へ向かいます。
歩いている途中、ふと足を止めました。
あの居酒屋は、たしか池田屋だった場所に建ったもの。
前に「坂本龍馬 遭難の地」を訪ねたことがあったのです。

京都を歩いていると、ところどころに「●●遭難の地」と書かれた碑があります。
遭難とは、山奥で方角を見失って力尽きることだと思っていましたが、こんな街の中でも遭難するものなんですね~。
「難に遭う」という文字通りの意味なのでしょう。
● インパクトパフェ
そして、パフェ専門店のようなカフェ、からふね屋珈琲を見つけました。

一見おしゃれなお店ですが、パフェに、エビフライが載ってる~~!!??
よく見ると、ほかにもたこ焼きとか、アメリカンドッグが載っています。
あれやこれや、スゴすぎ~!

こちらの画像は一見マトモに見えますが、右上はかぼちゃ、右下は大学芋。
どうしてこれでパフェを作ろうと思ったの…?
● ナイトミュージアム
錦市場に着きました。タコ焼きを食べようと、カリカリ博士に行きましたが、お店は少し暗い照明になっていました。
「材料がなくなったので、今日は閉店です」と言われてがっかり。
周りにはまだたこ焼きを食べている人が大勢います。
あと5分早く着けば、食べられたかもしれないと思うと、なおさら残念。
早い時間から賑わう錦市場。夕方には多くのお店が店じまいしています。
賑やかな時にばかり歩いているので、夜になるにつれぐっと寂しい通りになるとは知りませんでした。
ところで、さまざまなお店のシャッターに伊藤若冲の絵が描かれていることに気がつきました。

「鳥獣花木図屏風」
まあすてき!彼は錦市場の八百屋のボンボンだったんですよね。
これなら、お店に入れなくても、シャッター通りを楽しめます。まるでナイトミュージアム。

「竹虎図」

「樹花鳥獣図屏風」
● ディナー難民
お次に、錦市場を突っ切った先にある讃岐手打ちうどんの英多朗に行きました。
ところが行列ができており、「50分ほどかかります」と言われたので、あきらめました。
うどん屋さんで50分待ちってー!飲みタイムになっているのでしょうか。

さて、それならどの店に行こう。
土曜日の夜なので、町は賑わい混んでいます。

からくり時計が上がっていくところでした。
調べてみたところ、ここは四条堺町通りにある野村証券京都支店。
そのビルにからくり時計が掛かっています。
最後の一瞬しか見られませんでしたが、定刻になると、和のBGMが流れて、祇園祭のシンボル、長刀鉾が登場するのだそう。
2時間おきに見られるそうです。
● 玉さま公演
3人で何を食べようかと考えながら、人混みに揉まれて四条大通りを東へ。

鴨川を渡ったところにある南座では、坂東玉三郎特別公演が開催中。
玉さま~!チケットがあったら、観に行きたーい!
● おかるのうどん
「おかる」といううどんやさんに入りました。
場所柄か、店内には外国人のお客さんもちらほら見かけます。

舞妓さん行きつけのお店だそうで、ずらりと舞妓さんの名前が書かれたうちわが並んでいます。

逆側の壁には、有名人のサインがびっしりと飾られていました。
そのほとんどが芸人さん。
本気か冗談か、ジャルジャルの色紙には「おかるさんへ」ではなく「かおるさんへ。あ、ごめんなさい」と書かれていました。

その中に、ピスタチオのサインを発見。
イトコがファンなので、パチリ。(でもここでは割愛します、笑)
祇園名物、ちーず肉カレーうどん(キツネ入り)をいただきました。
辛口が苦手な私は、外でカレーを食べると、思わぬ辛みの洗礼を受けることがありますが、ここのは出汁がおいしく、濃すぎずマイルドな味で食べやすかったです。

店員さんたちは全員男性で、近くに出前もしていました。
外国人客の「相席じゃなくて2人席がいい」といった注文もちゃんと理解していました。英語理解力ばっちり!
● 夜カフェの巨大スコーン
食後のお茶をしに、再び鴨川を渡って四条通りを西に戻り、ティーハウス リプトンに入りました。
ここはロイヤルミルクティーを日本で初めて提供したサー・トーマス・リプトンのティーハウス。
京都のみ、3店舗しかないようです。東京にはありません。

英国クリームティセットを頼むと、紅茶とスコーンが出てきました。
そのスコーンの大きさにびっくり。
ちょっとこれ、相当巨大じゃない?
イギリスで食べたスコーンも、こんなに大きくなかったけど?

でももちろん嬉しいことです。ほかほかの暖かいスコーンに、この店オリジナルのマスカルポーネとクロテッドクリームを混ぜたクリームとイチゴジャムをつけて、いただきました。
連れは、ケーキも頼みましたが、これでもうおなかいっぱい。

ケーキと比較すると、大きさがわかるでしょう。
10時近くまで夜カフェを楽しんで、宿に戻りました。
部屋のこたつの中で、のんびり温まってから寝に着きました。
明日はもう発表はないので、気楽です。
4日目に続きます。
● 東山通を歩く
3日目-4日目は、京都大学で行われる学会に参加します。
朝早く起きると、気持ちのいい天気。
そこでバスには乗らずに、七条から京大まで歩いてみようと思いました。
京都の中心街を東西に横切る通りは、一条から十条まで数の名前がついています。
私が歩くのは、智積院~清水寺~八坂神社~熊野神社~京都大学を結ぶ、いつも車が混雑するルート。
その京都府道143号、別名東山通(東大路通)を歩いて行きます。
距離は5キロ、歩くと1時間ほどかかる予定。
バス通り沿いなので、途中で無理だと思ったら、そこからバスに乗ればいいですね。
では出発~。思ったよりも歩きやすい道で、嬉しくなります。
出発地点の智積院付近は、京都駅から緩やかな坂を上った小高い場所にあるため、祇園まではゆるやかな下り道が続いて楽なのです。
● 朝の消防訓練
東山消防署では朝から隊員たちが訓練をしていました。

ここ、いつも通るたびに大がかり練習をしています。
消防隊員は常日頃、訓練を重ねているのかしら?バス通りだから目に留まるのかな?

知恩院の参道

琵琶湖疎水と十石舟
朝なので、車道も歩道もまだ混んでいません。
快適に歩き始めてからちょうど30分で、東山駅前に着きました。
● 京都大学吉田寮
さらにまっすぐ道を進み、熊野神社前を越えて、1時間ほどで京都大学に到着。
撤去問題で噂になっている学生自治下の吉田寮は、思ったより新しい感じ。

希望者は見学もできるようです。
建物を眺めながら、森見登美彦の小説『四畳半神話大系』のカオスな空間を連想していると、学生が寮から出てきました。
神話大系に取り込まれそうになったので、そろそろと後ずさって元の通りに戻りました。
● 京都大学の時計台
京都大学に到着。1年ぶりの百周年時計台記念館。

去年も京大の学会に参加しましたが、今回はポスター発表をします。
受付の人に「先生」と呼ばれて、慣れない呼び名にドキドキしました。
● カフェ・コレクション
午前中は口頭発表に参加し、昼には顔見知りの人たちとランチ。
森見登美彦の小説にも登場する、農学部前のカフェ・コレクションに行きました。

森見さんはたらこパスタが好きだったようですが、私は名物のオムライスを注文。
巨大なオムの登場にビックリ。これで680円というコスパの良さに、二度ビックリ。

店内はシックですが1Fは喫煙OKというのが、古くからの喫茶店ぽい感じ。
みごとに愛想がない店員ばかりで、塩対応の洗礼を受けます。
これもまた学生街っぽい感じ。

カフェの本棚にあったのは坂口安吾作品集で、森見作品はありませんでした。
モリミー、がんばれ!
● ポスターセッション
ビッグなオムでおなかいっぱいになって大学に戻ります。
午後はポスターセッション。
始まるまではガチガチに緊張していましたが、いざ発表時間になってみると、大勢の人に説明をし、受けた質問に答え、意見交換をしているうちに時間が経ちました。
終わってみればあっという間の体験。
A1サイズのポスターをしょってきた甲斐がありました。
結果オーライでよかったよかった。
(でも写真を撮る心の余裕はありませんでした!)
● モダンな大学寮
発表が無事に終わり、その後の参加者セッションに参加して、この日のプログラムは終了。

もう日が暮れかかる時間になっていました。
帰りのバス停には、参加者たちの長い行列ができていたので、連れの参加者2人と出町柳駅まで歩いていくことにします。
レトロモダンな建物がありました。
京都大学YMCA会館の地塩寮です。
大正2年、ヴォーリズの設計。
素敵ですね。吉田寮よりもこちらに入りたいなあ。

連れのリクエストで、鴨川の土手道を少し歩いてみることにしました。
「神田正輝がいるかもしれない!」と言うので
「え、カッパみたいに?」と驚いて聞くと
「いやいや、棲んでるわけじゃないから!」と笑われます。
なんでも2時間推理ドラマで、事件解決後に神田正輝と片平なぎさがのんびり鴨川のほとりを歩くエンディングシーンが多いんだそう。
でもこの日は風が強く、とても寒い日。
ピューピュー吹きすさぶ川風に、身体の芯から冷えます。
「寒くて無理!正輝もなぎさもいないよ!」
地下の京阪ホームへの階段に避難しました。
● 繁華街で遭難
そのまま京阪に乗って四条駅で降り、新京極へ向かいます。
歩いている途中、ふと足を止めました。
あの居酒屋は、たしか池田屋だった場所に建ったもの。
前に「坂本龍馬 遭難の地」を訪ねたことがあったのです。

京都を歩いていると、ところどころに「●●遭難の地」と書かれた碑があります。
遭難とは、山奥で方角を見失って力尽きることだと思っていましたが、こんな街の中でも遭難するものなんですね~。
「難に遭う」という文字通りの意味なのでしょう。
● インパクトパフェ
そして、パフェ専門店のようなカフェ、からふね屋珈琲を見つけました。

一見おしゃれなお店ですが、パフェに、エビフライが載ってる~~!!??
よく見ると、ほかにもたこ焼きとか、アメリカンドッグが載っています。
あれやこれや、スゴすぎ~!

こちらの画像は一見マトモに見えますが、右上はかぼちゃ、右下は大学芋。
どうしてこれでパフェを作ろうと思ったの…?
● ナイトミュージアム
錦市場に着きました。タコ焼きを食べようと、カリカリ博士に行きましたが、お店は少し暗い照明になっていました。
「材料がなくなったので、今日は閉店です」と言われてがっかり。
周りにはまだたこ焼きを食べている人が大勢います。
あと5分早く着けば、食べられたかもしれないと思うと、なおさら残念。
早い時間から賑わう錦市場。夕方には多くのお店が店じまいしています。
賑やかな時にばかり歩いているので、夜になるにつれぐっと寂しい通りになるとは知りませんでした。
ところで、さまざまなお店のシャッターに伊藤若冲の絵が描かれていることに気がつきました。

「鳥獣花木図屏風」
まあすてき!彼は錦市場の八百屋のボンボンだったんですよね。
これなら、お店に入れなくても、シャッター通りを楽しめます。まるでナイトミュージアム。

「竹虎図」

「樹花鳥獣図屏風」
● ディナー難民
お次に、錦市場を突っ切った先にある讃岐手打ちうどんの英多朗に行きました。
ところが行列ができており、「50分ほどかかります」と言われたので、あきらめました。
うどん屋さんで50分待ちってー!飲みタイムになっているのでしょうか。

さて、それならどの店に行こう。
土曜日の夜なので、町は賑わい混んでいます。

からくり時計が上がっていくところでした。
調べてみたところ、ここは四条堺町通りにある野村証券京都支店。
そのビルにからくり時計が掛かっています。
最後の一瞬しか見られませんでしたが、定刻になると、和のBGMが流れて、祇園祭のシンボル、長刀鉾が登場するのだそう。
2時間おきに見られるそうです。
● 玉さま公演
3人で何を食べようかと考えながら、人混みに揉まれて四条大通りを東へ。

鴨川を渡ったところにある南座では、坂東玉三郎特別公演が開催中。
玉さま~!チケットがあったら、観に行きたーい!
● おかるのうどん
「おかる」といううどんやさんに入りました。
場所柄か、店内には外国人のお客さんもちらほら見かけます。

舞妓さん行きつけのお店だそうで、ずらりと舞妓さんの名前が書かれたうちわが並んでいます。

逆側の壁には、有名人のサインがびっしりと飾られていました。
そのほとんどが芸人さん。
本気か冗談か、ジャルジャルの色紙には「おかるさんへ」ではなく「かおるさんへ。あ、ごめんなさい」と書かれていました。

その中に、ピスタチオのサインを発見。
イトコがファンなので、パチリ。(でもここでは割愛します、笑)
祇園名物、ちーず肉カレーうどん(キツネ入り)をいただきました。
辛口が苦手な私は、外でカレーを食べると、思わぬ辛みの洗礼を受けることがありますが、ここのは出汁がおいしく、濃すぎずマイルドな味で食べやすかったです。

店員さんたちは全員男性で、近くに出前もしていました。
外国人客の「相席じゃなくて2人席がいい」といった注文もちゃんと理解していました。英語理解力ばっちり!
● 夜カフェの巨大スコーン
食後のお茶をしに、再び鴨川を渡って四条通りを西に戻り、ティーハウス リプトンに入りました。
ここはロイヤルミルクティーを日本で初めて提供したサー・トーマス・リプトンのティーハウス。
京都のみ、3店舗しかないようです。東京にはありません。

英国クリームティセットを頼むと、紅茶とスコーンが出てきました。
そのスコーンの大きさにびっくり。
ちょっとこれ、相当巨大じゃない?
イギリスで食べたスコーンも、こんなに大きくなかったけど?

でももちろん嬉しいことです。ほかほかの暖かいスコーンに、この店オリジナルのマスカルポーネとクロテッドクリームを混ぜたクリームとイチゴジャムをつけて、いただきました。
連れは、ケーキも頼みましたが、これでもうおなかいっぱい。

ケーキと比較すると、大きさがわかるでしょう。
10時近くまで夜カフェを楽しんで、宿に戻りました。
部屋のこたつの中で、のんびり温まってから寝に着きました。
明日はもう発表はないので、気楽です。
4日目に続きます。