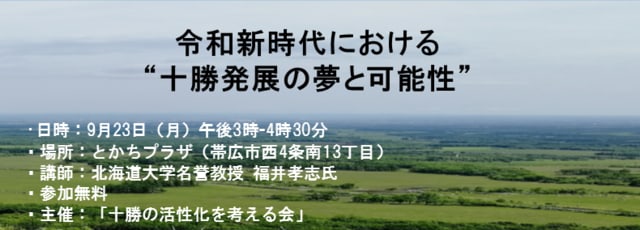世界のベストセラーになっている「ホモ・デウス」の本には、以下のことが書かれていた。
『歴史学者が過去を研究するのは、過去を繰り返すためではなく、過去から解放されるためなのだ。
歴史を学ぶ目的は、私たちを押さえつける過去の手から逃れることにある。歴史を学べば、祖先には想像できなかった可能性や祖先が私たちにしてほしくなかった可能性に気づき始めることができる。歴史を学んでも、何を選ぶべきか分からないであろうが、少なくとも選択肢は増える。歴史を学ぶ理由がここにある。単一の明確な筋書きを予測して視野を狭めるのではなく、視野を拡げ幅広いさまざまな選択肢に気づいてもらうことが本書の目的だ』。
日本の国は、二度とあやまちは繰り返しませんと誓ったはずだ。そのことが、これからの日本の果たす役割のひとつだと思う。なお、人口問題研究所の予想では、日本の人口は2045年に約9千万人、80年後の2100年には約6千万人が予想されている。
「十勝の活性化を考える会」会長

注) 国立社会保障・人口問題研究所
国立社会保障・人口問題研究所は、厚生労働省の施設等機関である。人口研究・社会保障研究はもとより、人口・経済・社会保障の相互関連についての調査研究を通じて、福祉国家に関する研究と行政を橋渡しし、国民の福祉の向上に寄与することを目的としている。
沿革
少子高齢化や経済成長の鈍化により、人口と社会保障との関係は以前に比べて密接となり、両者の関係を総合的に解明することが不可欠となってきたことを受け、厚生省(当時)は時代に応じた厚生科学研究の体制を整備するため厚生省試験研究機関の再編成を検討し、厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所を統合、国立社会保障・人口問題研究所を設立した。
5年周期で、出生動向基本調査、人口移動調査、生活と支えあい調査、家庭動向調査、世帯動態調査を行っている。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』)