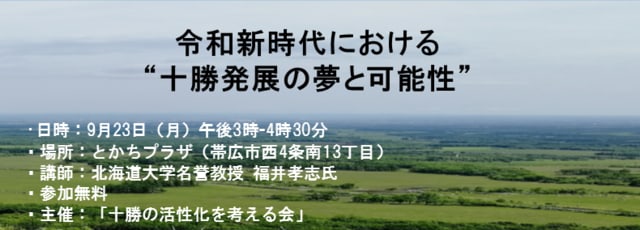先日、澤田洋太郎著「沖縄とアイヌ」の本には、以下のことが書かれていた。
『アイヌをこよなく愛した松浦武四郎は、1858年に十勝の山道でいくつかの石の矢尻や石の斧を発見している。これらはアイヌの祖先が使ったものであるが、その後の研究により、北海道では本州より少し遅れて縄文時代が始まったことが判明している。
しかし、稲作を伴う弥生文化は北海道には伝わっておらず、西暦紀元以降でも「続縄文」と名づけられる文化が、七~八世紀ごろまで続いていたのである。 この文化は北海道だけでなく、津軽海峡をはさんだ青森県のものとも共通しており、この両地域には同じような人びと、つまり弥生文化を持つ倭人によって本州の中央部方面から、いわば追い詰められて来た列島先住民がいたことを意味していると思われる。
と言うことは、北海道の「続縄文文化人」が、後にアイヌと呼ばれる人びとになったとすれば、彼らの先住民は本州の先住民で、弥生文化を拒絶した者たちの子孫であり蝦夷(エミシ)の生き残りということになり、蝦夷とアイヌを結びつける証拠となるわけである。
一般に、縄文土器を使う新石器時代が始まった今から1万2千年前よりも以前の旧石器時代には、土器は使用されていなかったので、その時代は「先土器時代」とよばれている。そして、近年までは「日本列島には先土器時代はない」というのが日本の考古学の定説とされていた。
しかし1952(昭和27)年に、群馬県の岩宿で相沢忠洋氏が関東ローム層の赤土の中から縄文以前の旧石器を発見したことによって、この定説は破られてしまう。そして、北海道でもその翌年には、赤土層から旧石器が発見されたのである。
以降、湧別川にそった白滝遺跡など多くの場所から続ぞくと旧石器が見つかっている。
白滝遺跡の住民の生活は、2万年から1万6千年前ごろまで続いていたものと推定されている。当時は気候が寒冷で「海退期」に相当していたから、北海道から本州・四国・九州まで陸つづきであり、動物も人間も自由に行き来しており、その文化は日本列島全域に共通するものであったはずである。
しかも、樺太を経て大陸とも接続するものであった。したがって、1万年前ごろ海面上昇が始まり、北海道が島になってからは、縄文文化は二つの地域で、それぞれ独自に展開されることになったわけである。(後略)』
以上のように北海道人は、縄文人⇒弥生人⇒蝦夷(エミシ)⇒アイヌ⇒北海道人 と続くのであるが、弥生人が大陸方面からきて、北(アイヌ)と南(沖縄人)に追いやられて道産子が生まれたのである。私は青森県に住んでいたのであるが、当時、青森県には津軽アイヌコタンや下北アイヌコタンが沢山あった。DNA検査でも、沖縄人とアイヌのDNAが似ているそうで、沖縄人とアイヌの顔が似ているのもそこから来ている。もっと言えば、日本人と韓国人、日本人と中国人、日本人とアジア人の顔が似ているのもDNAから来ているのである。
「十勝の活性化を考える会」会員