世界三大宗教は、①キリスト教(約20億人)、②イスラム教(約16億人)、③仏教(約4億人)と言われるが、信徒数で見れば約11億人のヒンズー教もある。日本の政治・経済・気象が異常になってきたので、後世は「宗教」にすがるほかは無いかもしれない。
哲学者西田幾多郎は、「哲学は、宗教を語ることによって帰結する」といっている。「宗教」は帰着点を示したものだということである。
ところで戦争は、人類の歴史においていつも起こるが、民族のほかに宗教も関係している。ボスニアヘルツェゴビナ紛争やイスラエルのガザ地区における紛争も、民族と宗教が関係している。16世紀中頃から17世紀にかけて「宗教戦争」という長い戦争があったが、これからの日本の歴史において、再び戦争を起こしてはならないと思う。
「十勝の活性化を考える会」会員
注) 宗教戦争
16世紀中頃から 17世紀にかけて,ヨーロッパの各地でキリスト教の諸宗派の間に行われた一連の戦争。
宗教改革によって生れたルター主義,ツウィングリ主義,カルバン主義,アングリカニズム (イギリス国教会主義) など,プロテスタンティズムの諸教会が,いずれも政治権力との結びつきのもとで領域支配を実現したのに対し,カトリック教会側もいわゆる反宗教改革を通じて政治的に自己の勢力再建をはかろうと努めたことから起った。
ドイツのシュマルカルデン戦争とカルル5世の治世晩年におけるプロテスタント諸侯の反乱、フランスのユグノー戦争、オランダ独立戦争、スペインの無敵艦隊 (アルマダ) とイギリス海軍の戦い、初期の三十年戦争などがその代表的なもの。
これらは,カトリシズムを奉じるハプスブルク家という超大勢力を一方の軸として行われたところから、互いに多かれ少なかれ関連をもっており、通商上の経済的利害ともからみ合って海上でのゲリラ戦をも伴った。
戦争の形態としては、イタリア戦争の場合と同様,典型的な傭兵戦争の性格をもち、国土の破壊や住民からの略奪が著しく、この政教紛争の経験を通じて宗教的寛容の思想が強まることとなった。
(出典:ブリタニカ国際大百科事典 )

注) ガザ地区
ガザ地区パレスチナ南西端,シナイ半島の北東に接し地中海沿いに長さ約 45km,幅6~10kmに延びる細長い区域で,中心都市はガザ。ガザは聖書時代から知られた港町であったが,パレスチナ戦争 (第1次中東戦争 ) 後エジプトの軍政下におかれ,六日戦争 (第3次中東戦争) 以降イスラエルの占領下にあった。本来の人口は 10万人程度であったが,パレスチナ戦争後多数のパレスチナ人がガザの難民キャンプに移り住み,1992年には約 60万人と超過密状態となった。農耕に適した土地が少なく,またイスラエルは地場産業の発展を厳しく抑制してきたため,住民の多くはイスラエルへの日雇い労働と国連パレスチナ難民救済事業機関 UNRWAの援助でかろうじて最低限の生活を維持してきた。このためイスラエルの占領支配に対する抵抗も強く,インティファーダも 1987年 12月ガザにおける衝突が発端である。 1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構 PLOの間で調印されたパレスチナ暫定自治協定に基づき,1994年ヨルダン川西岸のエリコ地区とともにパレスチナ人による先行自治が始まった。面積 365km2。人口 157万4000(2011推計)。
(出典:ブリタニカ国際大百科事典 )

















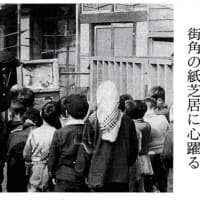


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます