脳出血を罹患した人は、次のように言っています。
『私は、定期的に医療や福祉サービスを受けています。医療(健康保険)や福祉(介護保険)をはじめとして多くの社会組織には、「施す」側と「受ける」側の存在があります。そこには自ずと、上位にある側と下位にある側との関係があります。医療では医師と患者、福祉では健常者と障害者といった具合です。
障害のない人から見て、多くの人は障害があるから「できない」という思い込みは、気づかないうちに行動や言動に表れるもので、私は何回もそういう状況を経験しました。
最近、人が人を世話したり、支えたりすることは一体どのようなことか、そして人として、そこにどのような課題があるかを考え始めました。このことは、立場が入れ替わったときにはじめて気づくものです。自分を支えてくれる地域は、自分が支える地域でありたいとつくづく思っています。そして、「互酬」(お互いさま)に基づき、誇りと尊厳をもって人間らしく自分らしく生きられる社会を創り出したいと考え活動しています。中途障害を持ったからこそ気づいたこと、障害があるからこそ果たせる役割があると思い行動しています。
私にとってのエンパワメントは、社会的障壁や不平等をもたらす社会的メカニズムを変革することです。
人権問題は、障害のある人の特別な権利でなくすべての人の権利ですので、障害を人権問題とするなら、そこには当然、義務(責任)が発生します。
障害があることによる差別や偏見、社会的障壁は、社会の思い込みや誤解により生じることに気づきます。』
「十勝の活性化を考える会」会員

注)互酬
互酬は、文化人類学、経済学、社会学などにおいて用いられる概念。
人類学においては、義務としての贈与関係や相互扶助関係を意味する。
互酬は、集団の対称性を特徴とする。集団間における財やサービスの運動によってギブ・アンド・テイクを促進し、相互依存の関係を作る。互酬を行う集団は対称的なサブグループを組織するので、3つ以上の集団も参加できる。その場合は相互にではなく、類似の関係にある第3のサブグループとやりとりを行う。集団において経済組織が分離していない場合は、互酬は親族を中心に行われるため、親族関係が複雑となる。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















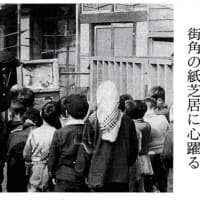


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます