新型コロナ禍で日本中が大変なことになっているが、国土の“緑化プロジェクト ”のことも忘れないでほしい。緑化は、地球温暖化を食い止めることにつながるので大切である。
さて1950年代、森林伐採で“襟裳砂漠”と呼ばれた襟裳岬の緑化プロジェクトをテーマにした映画、「北の流氷」(仮題)の映画製作が進んでいるそうだ。えりも町や高山植物で有名なアポイ岳がある様似町、十勝管内広尾町などの4町が中心になって、官民挙げた協力体制も整いつつある。
漁業資源に恵まれたえりも岬地区は、明治時代以降に入植者が急増、燃料用などで木が伐採され山肌がむき出しの砂漠と化した。赤土が海に流れ込み、漁業は困難に陥った。地元の漁師らが立ち上がり、1953年から半世紀にわたって、国と共同で浜の緑化と漁業の再生を成し遂げている。
映画はこの実話がベースで、「人間と自然の共生」がテーマになっているそうである。海底の砂を洗い流す奇跡の流氷や、その存在を話すアイヌ民族などが重要な役割で登場する。当映画の田中監督は、「自分たちの町は自分たちで守るというエネルギーを感じる。この映画で全国、世界に伝えたい。」と語っている。大西えりも町長も、「地球温暖化の問題や持続可能な開発目標(SDGs)の推進で、今後の指針になるような映画に」と期待しているそうだ。
なお「襟裳岬」は、歌手 森進一がレコード大賞を取ったのは、47年前の1974年。襟裳岬のあるえりも町の人々は、「襟裳の春は何もない春です」という歌詞に一時反感を持ったが、襟裳の知名度アップに貢献したということで、えりも町から森進一に感謝状が贈られたそうだ。また、エリモはアイヌ語であり、鼠(ねずみ)と訳し、襟裳岬は別名「ねずみ岬」という。
北海道で出生率が一番高い街として知られる“えりも町”。えりも町が高い出生率(最新データ:1.75)を誇っている理由の一つに、漁業を中心とするえりも町の産業が大きく影響しているといえる。特に、えりも町でもっとも普及しているコンブ漁は、家族全員が協力しなければならない。祖父、父、息子が海に出てコンブを取り、祖母、母、娘はコンブの選定作業を行なうことで、製品になり市場にでまわるのである。そのような安定した産業基盤があるからこそ、えりも町では安定した出生率が得られているのである。
「十勝の活性化を考える会」会員
注) 襟裳岬の緑化プロジェクト
『死んだ大地に、ゼロから木を植え、森を作る。半世紀にわたって繰り広げられた、世界でも例のない壮大なプロジェクトがある。北海道襟裳岬の、200ヘクタールに及ぶ砂漠緑化プロジェクトは、襟裳の人々にとって、かけがえのない故郷を蘇らせる闘いでもあった。
昭和28年、えりも岬の人々は困窮を極めていた。町の広大な砂漠の砂が海に流出し、生活の糧昆布を死滅させようとしていた。番組では、昆布漁師の飯田さんの家族の半世紀にわたる物語を軸に、壮大な自然の再生のドラマを、再現映像と写真を多用して描く。』
(情報元:NHKアーカイブスHPより)

















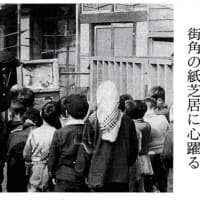


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます