先日、乃南アサ著「チーム・オベリベリ」の本を読んだ。 この本の内容について書かれているアマゾンの文章は、以下のとおりである。
『約140年前、その女性は、北海道十勝の原野へわたった。
オベリベリ━━和人たちによって「帯広」とされた新天地
明治の先進教育を受けた彼女は、いかに生き抜こうとしていたのか
開拓に身を投じた実在の若者たちを基にした、著者が初めて挑む長編リアルフィクション
<明治維新という大きな時代の変わり目を体験した上に、それまでとまったく異なる世界に身を投じる若者たちの姿は、今、世界的な新型コロナウイルスの流行により、またもや大きな時代の変わり目を経験しなければならない私たちに何を思わせ、感じさせることだろうか>━━乃南アサ
文明開化の横浜で時代の最先端にいた女性は、“その地”でいかに生きたか。私たちの代が、捨て石になるつもりでやっていかなければ、この土地は私たちを容易に受け入れてはくれない。』
“オベリベリ“はアイヌ語なので、日本語に直せば“チーム・オビヒロ”になる。十勝モンロー主義に通じるような「チーム・十勝」に本の名前を変えてもよいだろう。
モンロー主義とは、アメリカの第5代大統領 モンローが、自国とヨーロッパは相互不干渉でいこうと言い出したものであるが、「十勝モンロー主義」とは、他の地域とは関係なく、十勝の仲間だけで上手くやっていこうというものである。地元への愛着や結束力の強さから、十勝以外から来た人や企業にとって十勝モンロー主義は、起業や商売が難しい地域というネガティブに解釈されることもある。
しかし、全国各地から団体を組んで十勝へ入植したが、十勝の冬の寒さは厳しく、お互いに助け合っていこうとする開拓者魂が培われたのである。
明治16年、十勝に入植した民間団体“晩成社”の代表で、十勝開拓の祖とも言われる依田勉三が詠んだ俳句、“開拓の はじめは豚と ひとつ鍋”というものがある。 この俳句にも、豚と一緒になって頑張ろうというような入植に当たっての力強いメッセージを感じるのは、私だけであろうか。
チーム・オベリベリの本は、“晩成社”幹部の一人であった渡辺勝の妻の視点で書かれた本で、渡辺カネは英語も流ちょうに話すなど才能豊かな才女であった。なお、依田勉三は、いまNHK大河ドラマでやっている“青天を衝け”の日本資本主義の父 渋沢栄一に通じるものがある。
「十勝の活性化を考える会」会員T
注) 渡辺カネ
渡辺 カネ(安政6年4月14日〈1859年5月16日〉 - 1945年〈昭和20年〉12月1日)は、日本の開拓者、教育者。
北海道開拓を目的とした団体「晩成社」の一員として、北海道十勝地方・帯広の開墾に従事し、その傍らで私塾を開いて入植者の子どもたちに読み書きを教え、帯広の教育の基礎を築いた。
晩成社としての開拓は成功したとはいえないが、開拓に伴ってカネが子どもたちに施した教育は、のちの十勝の住民に受け継がれ、十勝の発展の基盤となった。
「帯広教育の母」「女性入植者のさきがけ」「十勝開拓の母」とも呼ばれる。北海道の先住民族であるアイヌたちと親交を深めたことでも知られる。夫は晩成社三幹部の1人である渡辺勝、兄は同じく晩成社三幹部の1人である鈴木銃太郎。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















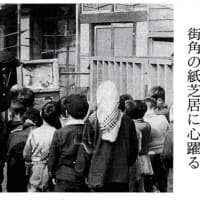


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます