令和2年12月19日、民放テレビ「北海道の広報番組」で、第3回目“今こそ地域の力を”と題して、斜里町の世界自然遺産“知床”の取組みを紹介していた。
番組の中では、知床自然センターや約1キロの所にある“フンペの滝”も紹介していた。フンペの滝は、地元ではホロホロと流れ落ちるさまが涙に似ていることから「乙女の涙」という愛称で親しまれており、川がなく知床連山に降った雪と雨が地下に浸透し垂直に切り立った約100メートルの断崖の割れ目から流れ落ちてくるそうです。
また番組では、コロナ禍で加速している企業におけるリモートワークの取組みも紹介していた。働きを示す“ワーク”と休暇を示す“バケーション”を合わせたワーケーションが、これからの時代だというのである。自然の中に見を置くことにより発想が豊かになり、集中力も増して仕事がはかどるのである。
働き過ぎと言われる日本、働いたからこそ物質的に豊かになった日本。これからは、精神的にも豊かになる必要があろう。しかし、人間には価値観の多様性があるから一概には言えないが、 “幸せって何だろう”と思う。
この多様性について、総合研究大学院大学長 長谷川眞理子氏が、2018年6月9日(7面)付け北海道新聞に、次のように書いていた。
『今、ダイバーシティー(多様性)が求められている。生まれた場所や性別などを問互いに尊重せず、いろいろな人たちが一緒に暮らせる社会を目指そうと言われている。人それぞれに働き方も多様にしよう。これからはダイバーシティーだ。
しかし、なかなか進まない。移民の受け入れに対する抵抗感は相変わらず強く、女性の社会進出も諸外国に比べてまったく進んでいないのが現状である。たとえば、世界の国会議員が参加する列国議会同盟による各国議会の女性進出に関する報告書では、日本は193カ国中158位だった。
人それぞれ、暮らし方も好みもいろいろなのは当然だろう。主義主張も異なる。そのような人々が一緒に社会を作っていくしかない。それがうまくいくためには何が必要か? 私は、それは「互いに異なることを認めあった上で互いに尊重する」という態度だと思う。英語で「agree to disagree」という概念だ。しかし、どうやらそれが日本にはないらしい。
日本は「村社会だ」、「集団主義だ」などとは、古くから言われているが、そうなる原因は、人々がどういう思考様式を取るからなのだろうか?集団主義の対局は個人主義であり、村社会の対局は流動的な社会だ。では、このような二極の違いは、本質的には何なのだろう。
私が思うに、それは、「自分が何者であり、何を欲するのか」ということを、まずは自分中心に考えてそれを表明するのが個人主義であり、まずはほかの人たちは何を考えているのかを見計らった上で表明するのが集団主義なのではないか。
この違いは、そこから連鎖してさまざまな社会のあり方を変えていく。集団主義では結局のところ「agree to disagree」ができないのだ。
「空気が読めない(KY)」という言葉がはやった。みんなの意向を察することができない人のことだが、なぜそれが嫌がられるのか?
それは、誰もが自分の考えを表明する前に、他人は何を考えているかを察し、それとかけ離れたことをしてはいけないと思っているのに、あいつは何なのだ、ということだろう。
そうならば、そう指摘すればよいのに、表面化させることを嫌うので、指摘しない。そして、ああ嫌なやつだと陰で思うことになる。私は、KYが悪いのではなく、KYの人に意見を言えないという状態が問題だと思う。
誰でも、自分の考えや思いはあるものだ。まるで考えたことがない事柄でない限り、何らかの意見は持っている。さらに、世の中のいろいろな意見に、疑問を持つことはあるはずだ。すべてに満足して疑問のない人などいない。
社会意見や疑問を皆がそれぞれ持っているということは、個人主義の社会でも集団主義の社会でも変わりはない。問題は、それをどのように表明するか、なのだ。
皆が自分の考えを述べれば意見の対立が表面化し、議論をすることになる。議論の過程で意見が変わることもあるが、最終的に対立がすべて解消することは少ない。規則などは、最大多数が納得できるものに落ち着くだろう。
しかし、考えの違いは残る。そこで、ある時点で「違いを認めあった上でお互いに尊重する」という態度を皆が取らないと、コミュニティーは成り立たない。皆が同じ意見や好みであれば、それは対立もなく平和だろう。しかし、社会が大きくなり、流動性が高くなるほど、皆が同じではなくなる。
今は、世界的にそのような方向に向いている。そのような社会では、人々は、世間一般に対して自分がどんな人間であるかを表明し、意見の対立について議論し、違いを認めあった上で互いに尊重することで、社会一般に対する信頼を保っていくことになる。
日本人は他者の考えを気にして物を言うし、身内でない一般的他者」に対する信頼が低い。果たして、この文化を変えることができるのだろうか。』
なお、これと同じようなことを令和2年9月16日付けブログに、丹羽宇一郎著 “死ぬほど読書”で書いています。
「十勝の活性化を考える会」会長
十勝の活性化を考える会」会員募集

















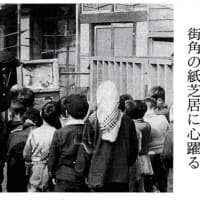


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます