北海道 十勝の深掘り
全国の読者の皆様に、「北海道十勝ってどんなところ?」の疑問に深掘りしてお伝えしてまいります。
ナウマン象のまち

絶滅したナウマン象は、約2〜3万年前の
新生代更新世後期まで日本列島や東アジア大陸に
生息していたと言われています。
現代のアジア象と比べるとやや小型で体高は2.5m〜3m。
氷河期時代の寒冷な気候に順応するため、全身は体毛で
覆われていて皮下脂肪が発達していたと
伝えられています。
「カチン!」
それは、忠類村(当時)の歴史を大きく変える衝撃の音でした。
日本で初めて全身骨格の復元に成功したナウマン象の化石は、1969(昭和44)年7月、忠類晩成地区の農道工事現場で偶然に発見されました。
側溝掘り作業の際、アルバイトの少年がツルハシを地面に打ち下ろした先に、湯たんぽのような模様がある楕円形の塊(かたまり)が出てきました。少年はそれが理科の教科書に載っているゾウの歯によく似ていることに気づきました。
そして、専門家による調査の結果、その掘り起こされた塊が、なんとナウマン象の臼歯だということが分かったのです。
http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/nauman/index.html
忠類ナウマン象記念館
https://tokachibare.jp/post_spot/post_spot-1794/
忠類ナウマン象記念館は、1969年(昭和44年)7月に偶然発見されたナウマン象の軌跡とその雄姿を末永く後世に伝えるため、太古のロマンを秘め1988年(昭和63年)8月にオープンしました。この建物は、上から見るとナウマン象の姿を想像したデザインになっており、中央の丸いドームの部分が胴体、四隅の展示室などが足、正面入口が頭部、玉石を埋め込んだ外壁は象の肌、「時の道」と呼ぶ長い歩道は鼻と牙を表現しています。また、この「時の道」の両側の円柱では、古生物の誕生から人類までの進化を伝え、現代空間から太古の世界へと大きな時の流れを表現しており、いつしか次第にナウマン象の世界へと誘い込むタイムトンネルをイメージしています。



















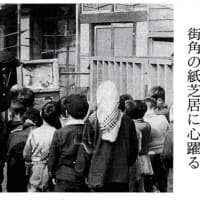


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます