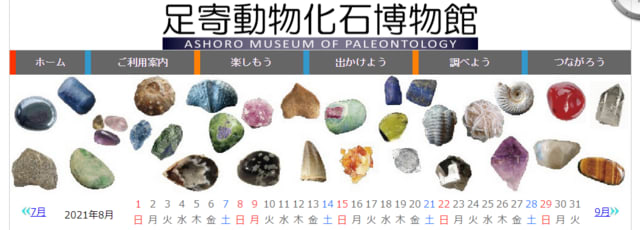先日、三人の対談集である“この国の「公共」はどこへゆく”の本を読んだ。対談者のうち二人は、文部科学省 キャリア官僚 寺脇研氏と前川喜平氏で、あとの一人は、城南信用金庫理事長であった吉原毅氏 であった。この本には、「公共」のことが書かれており、その抜粋は次のとおりである。
『 オウム真理教事件の時もそうでしたが、社会に重要な出来事をやり過ごすだけの人々ばかりでした。社会の動きに無関心でいる人々がすごく多くなった気がします。
かつては、社会や政治について考えようという姿勢は多くの人々にあったのではないでしょうか。街を守る、国をどうする、という庶民層が考えていて、行動して、自分たちと考えの違う活動家の学生たちとも対話しようじゃないかという姿勢があった。当時は社会が若かった。戦後の、国土再建という時代のテーマの中で多くの人々は生き、同じ国民としての連帯、繋がりがあった。そういうことは、今はない。
つまり自分たちの生存を支える「公」について考えていたということですね。自分たちが生きる日々のあり方に「公」が直結する可能性があった。そして貧富の格差はよくない。教育格差はいけない、戦争はよくない、平和は大事だとか、そうした価値観を持って議論し、行動していたと思います』と。
この「公共」について、憲法12条には次のように書かれている。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
私たちは、生まれながらにして持っているのが基本的人権であり、不断の努力によってこれを保持しなければならないとされている。他人の人権を奪ってまで、自分の人権が保障されても良いのだろうか。人権と人権を調整するのが「公共の福祉」であり、全ての人権には公共の福祉による他人の人権への配慮が必要である。個人の自由と権利は大切であるが、「公共」の立場からどのように考えていけば良いかが、今後の課題となろう。
公共交通のことを例にすると、わずかな人しか利用しなくなった場合、その交通機関を経営している民間会社では、補助金が出なければ金繰りに行き詰まり撤退するだろう。しかし、切り捨てではなく公共の福祉の面から、バスや乗り合いタクシーなどの代替手段に変わっていっているのが実情である。現在の課題である新型コロナの早い収束をするには 、“公共の福祉”という面からも考える必要があろう。
公共経済を主張したのは、アメリカの経済学者 ガルブレイス氏である。日本は貧しい国になってしまったので、道路・水道などの「公共施設」を今後、いかに維持していくかも問題になる。市場経済に任せれば資源の有効活用が図られるというが、資本主義は利潤を追求するので、格差拡大につながっている。世界のコロナワクチン接種についても、同じことが言えるのではないだろうか。
ある仏教学者が、「私たちは、利他的であることによって全員が利益を得ることができる。それがコロナ危機の教訓の一つなのだ」と言っていた。利他とは、自己の利益のためでなく、他の人々の救済のために尽くすことをいう仏教用語で、新型コロナ禍を早く収束させるためには、考えさせられる言葉である。
対談集では、 “自分さえよければ”という自己中心主義のことが書かれていた。自分の利益のためだけに頑張って、勝ち残った者だけが成功者であるという行動原理を前提としている。資本主義は、市場原理に任せておけば、良いものを安い値段で作ったものが勝ち、結果として全員におこぼれが得られるとする。だが実際には「神の見えざる手」は働かず行き過ぎも露呈し、一部の人間にしかおこぼれは回らず、格差は拡大しているのが現実だろう。
新型コロナ禍により格差が拡大する中で、資本主義の限界などを指摘したカール・マルクスが,最近あらためて脚光を浴び、学園闘争と無関係な若い世代が新たな生き方の指針として魅力を感じているらしく、マルクス主義の関係書物が売れている。
世界には、アメリカに象徴される資本主義や中国やロシアなどに象徴される共産主義があるが、50~100年も経つとお互いが良いところを取り入れているらしい。現に、資本主義国では福祉に、共産主義国では市場経済に注力し始めている。この2年間あまりコロナに振り回されているが、ワクチン接種により遠くない時期に事態は収まり、スポーツの祭典である東京五輪も、無観客で開催されようとしている。
ただ、この地球環境を破壊してきたのは「人間」だけであり、国々の対立ではなく「共生社会」「公共の福祉」「人類のありよう」の見直しを期待している。新型コロナ禍は、世界中に様々な影響がでるのは必至で、これを機に多くの価値観が変わるかもしれない。
「十勝の活性化を考える会」会員