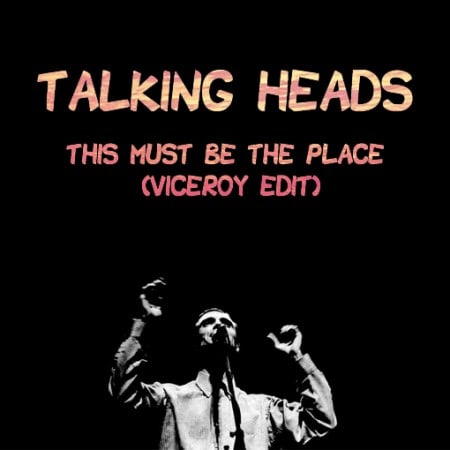

トーキング・ヘッズのThis must be the place をタイトルとする映画だった。
「きっとここが帰る場所」は、都合3回観た。
たまらなく好きな映画だ。
ショーン・ペンが50歳を越えた往年のロックスターを演じる。
音楽活動はやっていない。
大金を動かす金融取引で生計を立てている。
ゴッズファッションとカラカラ引くキャリーバックが、なんとも滑稽で哀しい。
そしてずっとぼそぼそ聞き取れないないような囁き声で喋る。
あのマチョのショーン・ペンが笠智衆と化してしまっている(笑)

この映画はヴェンダースの「パリ・テキサス」同様、
欧州人が見たアメリカなのだろう。
後半は完全にロードムービーの茫漠たる風景が続く。
(ジャームッシュにも共通するオフ・ビートなロードムービー)
ハリー・ディーン・スタントンは出てくるし、
「ファーゴ」のフランシス・ルィーズ・マクドーマンドまで出演している。
映像の目を見張る美しさと共に私には音楽がたまらない。
ロックスターたちが年老いるように、
あのディビィッド・バーンも白髪頭の爺様だ。
ねぇ、私たちも、どんどん老いてゆく。
80年代音楽シーンは遠い記憶の彼方か…
(home~♪ もう帰る家なんて何処にもないのかも?)
U2、ボノの娘まで出演している。

今回は何時にも増してとりとめない。
きっと映画の予告編と音楽を、いつも聴いていたいから貼り付けたような内容なのだろう。
ショーン・ペンは、「イントゥ・ザ・ワイルド」や「ミスティック・リバー」そして「ツリー・オブ・ライフ」と目が離せない。

















http://www.youtube.com/watch?v=--bM_fxrrI8
これは久しぶりに胸に突き刺さる超痛い映画でした。
(子供たちの悲痛な叫びに、観ている私自身の顔が歪んでゆく。あまりに辛過ぎる)
アメリカの公立学校が市場原理の導入で完全に崩壊している現状は、
堤未果の(株)貧困大陸アメリカで知っていました。
優秀な生徒を育てないと地域の市場価値が損なわれるという教育論理がここでも啓蒙されていました。
日本でも、この映画と同様な人と人との関係が分断された痛々しい子供たちの現状があるのでしょう。
また三重で中学生の放置死体が発見されたようです。
主演のエイドリアン・ブロディ(戦場のピアニスト)の間延びした顔が妙に魅力的です。
そういえば今売り出しのライアン・ゴズリングも、この手の間延び顔(苦笑)
もう一人、主人公に依存するストリート・チルドレンの少女は、まるでティーンエージャーのナスターシャ・キンスキーみたい。
最後に先日亡くなったハンセン病の詩人、塔和子さんの詩を。
「胸の泉に」
かかわらなければ
この愛しさを知るすべはなかった
この親しさは湧かなかった
この大らかな依存の安らいは得られなかった
この甘い思いや
さびしい思いも知らなかった
人はかかわることから
さまざまな思いを知る
子は親とかかわり
親は子とかかわることによって
恋も友情も
かかわることから始まって
かかわったが故に起こる幸や不幸を
積み重ねて大きくなり
くり返すことで磨かれ
そして人は人の間で思いを削り
思いをふくらませ生を綴る
ああ、何億の人がいようとも
かかわらなければ路傍の人
私の胸の泉に
枯れ葉いちまい
落としてくれない
ー塔和子の詩集ー
http://www.peace-create.bz-office.net/k_toukazuko3.htm
昔から芸能は神の憑代であり、神様からの贈り物だった。
贈与(ギフト)は、人が境界を越えて交流するときの経済活動の原点でもある。
以下、贈与について内田樹の対談から抜粋。
「贈与って聞くと、多く持っている者が少なく持つ者に分け与えるというような偉そうなイメージを持たれるかもしれませんが、違います。
贈与は〝自分は何もしていないのに先行者から贈り物をもらっちゃった〟というところから始まるんです。
もらったままだと負債感を覚えるので、次にパスしたくなる。
これが基本的な流れです。
何を贈与されたものと感じるかは人それぞれ。
自分の身体髪膚(しんたいはっぷ)、何千年もかけて体系づけられた日本語、文学、音楽……。
身の回りのすべてが贈与されたものに思える人は幸福なんですよ」
「自分はこんなにもらったんだから、他の誰かにもあげたいなって、自然に感じられるということですよね」
「そう。被贈与感って、自分が誰かに承認されて愛されていることの説明にもなりますよね。
何しろもらえるわけですから。大きなものをもらえばもらうほど、人にもあげたいという〝反対給付〟の義務が発生する。
これが人間の本質です。
もらいっぱなしで平気な人は、本当は人間じゃない(笑)。あげたいという心の動きを持つことで、人間は初めて経済活動をスタートさせ、共同体を形成できます。
風でたまたま飛んできたゴミかもしれないけど、宛先を自分だと思ってそれに感謝し、代わりの何かを置く。
商品であれば自分がエンドユーザーになることは可能ですが、贈与されたものはそもそも商品ではないので、パッサーにしかなれないんです」
あの伝説のビートニクのバイブル、「路上オン・ザ・ロード」が映画化され公開されているなんて。
http://www.ontheroad-movie.jp/
それも最高のスタッフだ。
「モーターサイクル・ダイアリーズ」のウォルター・サレスが監督し、制作はフランシス・フォード・コッポラ。
予告編を観るだけでもわくわくする。
やっぱり四国では上映されていないようだ。
DVD化が待ち遠しい。
私の放浪癖とロード・ムービーへの憧憬は、この映画の原作であるジャック・ケルアックの「路上オン・ザ・ロード」によるところが大きい。
今思い返しても恥ずかしいくらい10代後半から20代前半にかけて熱病のように傾倒していた(汗)