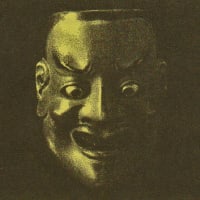2010年度 136冊目
記録のみ
『日本発見 第16号 ふるさとの伝承』心のふるさとをもとめて
暁教育図書
146ページ 値段不明
『日本発見 第16号 ふるさとの伝承』心のふるさとをもとめてを本日読了。
50ページまでは丹念にノートに取りながら読んだが、そこまでで30行13ページ
興味深いことが多く書かれすぎている(笑)
どうにもこうにも時間が足りない。
その後は黙読。
これなら早い(笑)
興味ある部分が多いので、時間を見つけては秋冬以降にもう一度メモをとりながら読みたい。
それにしても気が急く今日この頃。
そろそろイラン行きの用意をせねばなるまい。
『日本発見 第16号 ふるさとの伝承』では文字通り、色々な伝承が書かれている。
芝居でなじみの、気になるものも多い。
日本発見は非情に面白いが、これも観世流百番集と同様、冬まで封印。
やはり、日本がいいなぁ^^と わたくしはしみじみと思う。
柳田國男の仕分け方などの触れられていた池田 彌三郎氏の記述は興味深い。
高校製の頃、池田 彌三郎や開口健を食通とあがめ奉っていた・・・というか、食べ物の話も面白いと、尊敬していた。
池田 彌三郎さんか・・・
何か読みたいなぁ^^

池田 彌三郎
「芸能」 岩崎書店 1955年(民俗民芸双書)
「文学と民俗学」 岩崎書店 1956年(民俗民芸双書)
「日本人の芸能」 岩崎書店 1957年 (写真で見る日本人の生活全集)
「はだか風土記」 大日本雄弁会講談社 1958年 (ミリオン・ブックス)
「日本故事物語」 河出書房新社 1958年 のち文庫
「はだか源氏」 講談社 1959年 (ミリオン・ブックス)
「民俗故事物語」 河出書房新社 1959年
「日本の幽霊」 中央公論社 1959年 のち文庫
「江戸時代の芸能」 至文堂 1960年 (日本歴史新書)
「枝豆は生意気だ」 河出書房新社 1961年
「まれびとの座 折口信夫と私」 中央公論社 1961年 のち文庫
「日本芸能伝承論」 中央公論社 1962年
「ゆれる日本語」 河出書房新社 1962年
「芸文散歩 池田弥三郎随筆集」 桃源社 1962年
「東京の12章」 淡交新社 1963年
「ふるさと・東京」 東峰出版 1963年
「ことばの文化」 河出書房新社 1964年(日本の民俗)
「光源氏の一生」 講談社現代新書 1964年
「銀座十二章」 朝日新聞社 1965年 のち朝日文庫
「私の食物誌」 河出書房新社 1965年 のち岩波同時代ライブラリー
「東京横浜安心して飲める酒の店」 有紀書房 1965年
「俳句・俳人物語」 ポプラ社 1966年
「おとことおんなの民俗誌」 講談社 1966年 (ミリオンブックス) 「性の民俗誌」と改題、講談社学術文庫
「わたしの源氏物語」 講談社 1966年 (ミリオン・ブックス)
「塵々集」 雪華社 1966年
「酒、男、また女の話」 有紀書房 1966年
「逆立ちの青春像 青年へのガイダンス」 池田書店 1966年
「わが師わが学」 桜楓社 1967年
「言語のフォークロア」 桜楓社 1967年
「空想動物園」 コダマプレス 1967年
「ふるさと日本」 鹿島研究所出版会 1967年
「広重の江戸」 講談社 1968年 (原色写真文庫)
「日本詩人選 高市黒人・山部赤人」 筑摩書房 1970年
「私説 折口信夫」 中公新書 1972年
「日本橋私記」 東京美術 1972年
「日本の旅人 在原業平 東下り」 淡交社 1973年
「わたしのいるわたし」 三月書房 1973年
「世俗の芸文」 青蛙房 1973年
「食前食後」 日本経済新聞社 1973年
「百人一首故事物語」 河出書房新社 1974年 のち文庫
「日本のことわざ 暮らしのなかの知恵」 ポプラ社 1975年
「露地に横丁に曲り角」 新人物往来社 1975年
「日本人の手紙」 白馬出版 1975年
「池田弥三郎対談集 日本人のこころ」 新人物往来社 1976年
「町ッ子土地ッ子銀座ッ子」 三月書房 1976年
「たが身の風景」 読売新聞社 1976年
「暮らしの中の日本語」 毎日新聞社 1976年 のち、ちくま文庫
「芸能の流転と変容」 実業之日本社 1976年
「ことばの中の暮らし」 主婦の友社 1977年
「日本文学と民俗」 桜楓社 1977年
「わが戦後」 牧羊社 1977年
「万葉びとの一生」 講談社現代新書 1978年
「わが幻の歌びとたち 折口信夫とその周辺」 角川選書 1978年
「わが町 銀座」 サンケイ出版 1978年
「東京の中の江戸」 国鉄厚生事業協会 1979年
「話のたね」 文春文庫 1979年
「山手線各駅停車」 保育社 1979年(カラーブックス)
「池田弥三郎著作集」 全10巻 角川書店 1979年 - 1980年
「聴いて歌って」 音楽鑑賞教育振興会 1979年 (音楽随想)
「行くも夢止まるも夢」 講談社 1980年
「日本人の心の傾き」 文藝春秋 1980年
「郷愁の日本語 市井のくらし」 あずさ書房 1980年
「三田育ち」 東邦経済社 1980年
「魚津だより」 毎日新聞社 1982年
「池田弥三郎北陸を語る」 対談シリーズ 読売新聞北陸支社 1983年