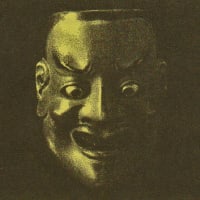(写真は奈良の信貴山。正月参拝の折。丸く光って見えるのは、小銭を貼り付けられているもよう。2009.1.2 )
記録だけ
2009年度 13冊目
『神の民俗誌』
宮田 登 著
株 岩波書店
岩波新書 黄版97
1979年9月20日
193ページ 320円
今回も私の好きな宮田 登 著の『神の民俗誌』を楽しむ。
やはり興味深い。
宮田 登氏の話の中に度々出てくる「木花開耶姫(このはなさくやひめ)」の話は、好きだ。
これは『日本書紀』巻二に記されている。
「箒の神」は、はき出すとか 掃き寄せるとか。
これはケガレとハレに関するのだろう。
箒の丸く絞った形も、いかにも心霊が宿りそうで、こういったものを神に見立てる日本人の知恵には驚きと同時に、納得もする。
こういった形は妊婦や出産にも見立てられている。
妊娠中トイレを掃除するといい子が生まれるといった言い伝えは、こういったところから来ているとのこと。
納得。
『江談抄』や『諸社通用神祇服忌大成(じんぎぶっきれい)』http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/wa03/wa03_06343/index.htmlの例は興味深い。
『諸社通用神祇服忌大成』での 「魚鳥、大社無レ憚 (魚鳥、大社にて はばかり無し) 」は、わた其の場合は 大神神社(三輪神社)の神餞(しんせん)である つるされた鯛と雉を思い浮かべる。
『仏説目連正教血盆教』の、「血の池地獄」
そうだったんだと変に納得。
鍛冶屋の話は以前読みかけたままになっている柳田國男氏の『一つ目小僧』に関連性があるのだろうか・・・。
職人の技術が呪術者としての役割も含むといった説もこの本には記され、全体を通して、非常に興味深く読んだ。