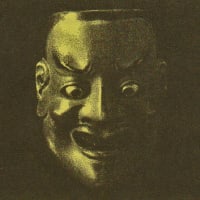(写真は信貴山から見える山)
記録だけ
2009年度 18冊目
『夜這いの民俗学 夜這いの性愛論』
赤松 啓介 著
2004年6月9日第1版
2004年12月25日第4版
株 筑摩書房
筑摩学芸文庫
327ページ 1200円+ 税
赤松啓介 著の 『夜這いの民俗学 夜這いの性愛論』を本日読了。
これが結構時間がかかり、3日を費やす。
故赤松啓介氏の口調は学者らしからぬ味わいで、口調良く語る。
気品にとんだ方とは言えないが、味わい深い内容と意味合い。
「ここの村ではそうだが、燐村や他村では知らない!」といいきる赤松啓介氏の自身に満ちた潔さは、気持ちが良いものだ。
自分にとって都合の良い継ぎ接ぎをする研究者も多い中、「イエスかノーの二つに一つではない!」といった姿勢は、学者としての厚みさえ感じる。
柳田國男氏の問題点は、居間まで読んだ南方熊楠氏や折口信夫氏や宮田登氏や本田勝一氏などのか鳥羽よりも具体的で単刀直入。
切り口が鮮やかで、且つ わかりやすかった。
また某女史などに対する感想も、本質を得ており、的確といえよう。
夜這い内容云々は私の頭の中にたたき込まれているのでここでは省かせていただく。
面白く、興味を持ったのは『柿の木問答』
これは芸能の初めとされる問答が、生活に密着した形か・・・。
内容から言っても、五穀豊穣と子孫繁栄を兼ね合わせていると思うのは、私だけであろうか・・・。
となれば、問答、五穀豊穣、子孫繁栄から考えて、これは二人だけの問題ではなく、神に言い聞かせていると考えられるのではないだろうかと感じる。
また柿の木は果実(実もの)と言うだけではなく、『柿』の文字の「木偏」を「女偏」に変化させると、『姉』という字となる。
本書に書かれた『柿の木問答』の台詞を変え、『姉の気問答』とすると話が通じると思えるのは私だけか・・・。
著者曰く、教育勅語などにおける禁止事項が今の日本の性に対する感覚的基本形を無し、元の日本の性大系を大きく揺るがしたことには変わりないらしい。
それは幸か不幸かは別問題として、日本民俗の大きな部分を大きく変化させたのだろうと思うと、複雑な気持ちになる。
それが著者の言うように悪かったかどうかは、私個人にはわからない難しい問題を抱えている。
ただ、赤松啓介氏の言うには 過去のそういった風習を 柳田國男氏のように無かったことにしてしまっているという。
そういった姿勢柳田國男氏の姿勢が本当ならば、これに関してはいただけない。
事実は事実としてとらえられる民族学的学問であって欲しいと願うばかりである。