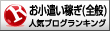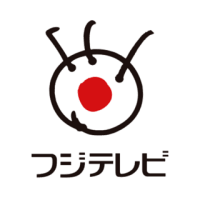(注・以下の記事は2002年1月23日に書いたものです。)
国の「最高法規」である憲法は、誰の目にも分かりやすいものでなければならない。私はここでもう一度、憲法第9条について語りたい。
第9条第1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」となっている。
私はすでに、この条文は『国家主権』をないがしろにするものだと指摘したが、それはさておき、この条文の意味する問題点について考察したい。 「国際紛争を解決する手段としては」という意味は、放棄する戦争を限定するという解釈が有力だと言われる。つまり、『侵略戦争』を防止するために、戦争や武力による威嚇、武力の行使を放棄するのであって、『自衛戦争』は認められているという解釈である。もしそうであるなら、そうした理解はおかしいのではないか。
もとより、侵略戦争は絶対に認められない。それならば、『侵略のための戦争や武力行使は、永久にこれを放棄する』と、分かりやすく明記すべきである。 「国際紛争」というのは、一方が侵略すれば他方は自衛するために起きるのであり、侵略だけを言っているのではない。 侵略に対して自衛(防衛)の武力行使がなければ、紛争など起きるわけがない。 従って、「国際紛争を解決する手段」というのは、自衛(防衛)のための諸行動も当然含まれるはずである。 国際法では勿論、自衛のための武力行使は認められている。
憲法の条文というのは、勝手な解釈がまかり通らないように、できるだけ明確でなければならない。国の最高法規であるから、なおさら当然である。中学1年生でもすぐに分かるような、明確なものでなければならない。
私は憲法改正には大賛成だが、いわゆる「解釈改憲」には絶対反対である。解釈というのは、ほとんど無限に広がるものである。その中で、詭弁、こじつけ、ごまかし等が次々に発生してくるのである。
かつて私がテレビ局の政治部記者をしていた時、Tという有名な内閣法制局長官がいた。我々記者はTさんを、少々の親しみと皮肉を込めて『三百代言』と呼んだ。『三百代言』とは、詭弁家のことである。彼は大した詭弁家であった。その才能は認めるが、詭弁がまかり通るのは宜しくない。憲法改正は「解釈改憲」であってはならない。 「明文改憲」で、一読すれば誰でもすぐに分かるようにしなければならない。(2002年1月23日)