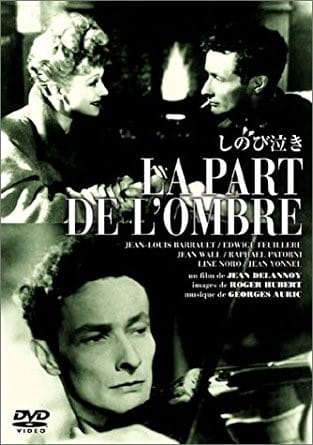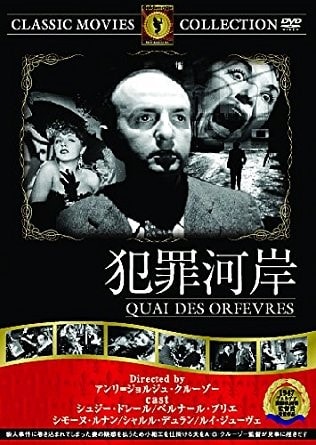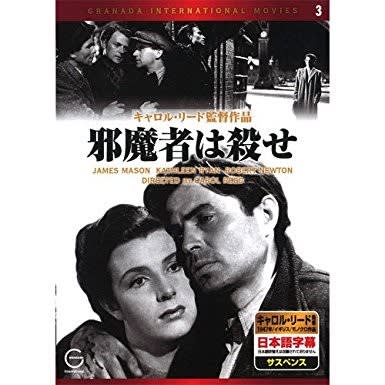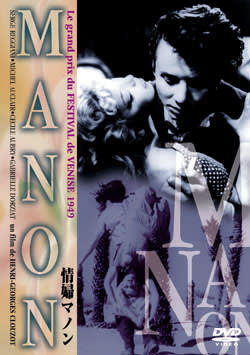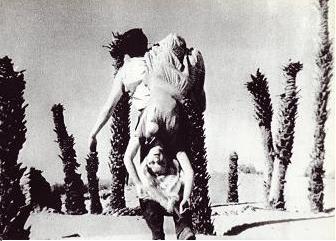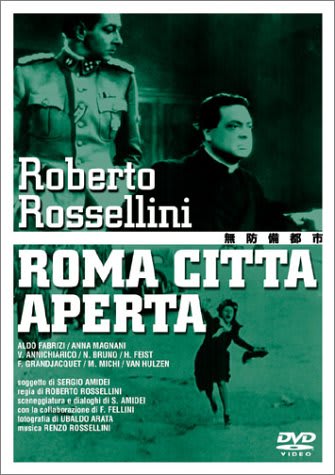愛人オディルの父親が亡くなったために、シャトラールは車で、シェルブールからポールの村へオディルを送ってくる。
村あげての葬式。
時間潰しにシャトラールはカフェへ立ち寄る。
葬儀が終わり、オディルの妹マリーに叔父が、弟たちと共に田舎へ行くよう提案するが、マリーはここのカフェで勤めたいと言う。
働くための願いに来たそのカフェで、マリーとシャトラールが出会う。
しかし、声を掛かけて出ていくシャトラールから“義理の妹”と言われても、素っ気ない素振りをするマリーだった・・・
シャトラールは、シェルブールで映画館併用のレストラン付きホテルを経営している。
オディルはシャトラールに対して倦怠期の兆候があり、元々夢見ていたパリに行きたいと思っている。
18歳のマリーには、恋人として理髪師のマルセルがいるが、のぼせているマルセルほどには感情が動かない。
シャトラールは、マルセルの父親の船をオークションで購入したため、その修理を含めポールに頻繁に来るようになる。
そして必然的に、カフェでマリーと顔を合わせることになる。
そんなマリーが恋人のマルセルに、シェルブールに行きたいと言ったりする。
シャトラールにとってマリーは、愛人の妹である。
だから、シャトラールがマリーを気に入っても、そこは中年の大人でもあるし、微妙な雰囲気だけであからさまにはしない。
マリーだってわかっている。
シャトラールに親しみ以上の感情がどこかにあっても、やはり姉の情人ということで警戒心も拭えない。
それでも、この閉塞した漁村からシェルブールに連れて行ってくれる希望も捨てない。
そんな二人の、時が経過してもギクシャクした関係は続く。
中年男の分別と、それに寄り添っていいのか、冷ややかな面持ちで戸惑う大人になる手前のマリー。
それらの場面を、会話の妙で繋いでいく。
そして、今まで笑顔がなかったマリーが、ラストで、幸せの予感の笑みを浮かべる時には、心底感動させられる。
そもそもこの作品の魅力として、シャトラール役を演じているこの時期のジャン・ギャバンの自然体が、とっても素晴らしい。
また、相手役のニコール・クールセルが何と言っても魅力的である。
このニコール・クールセルについては、後に『シベールの日曜日』(セルジュ・ブールギニョン監督、1962年)で、主人公ピエールに寄り添う看護師マドレーヌの思いが印象的で、これまたいつまでも忘れられない。