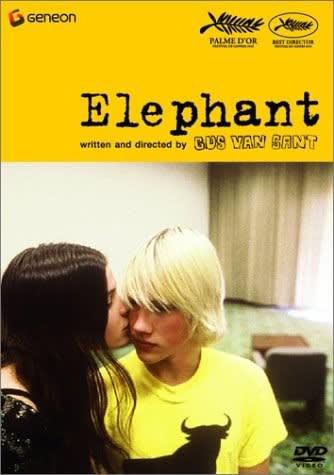『マイ・マザー』(グザヴィエ・ドラン監督、2009年)を観た。
17歳の少年ユベール・ミネリはカナダ・ケベック州の何の変哲もない町でごく普通に暮らしていたが、
ここのところ自分の母親が疎ましく思えてどうしようもなかった。
洋服やインテリアを選ぶセンスのなさ、口元には食べカスをつけ、口を開けば小言ばかりと、母親の一挙手一投足が癪に触っていた。
母親を受け入れ難く思う一方、理由もなく苛立ってしまう自分にも嫌気がさしていた・・・
(MOVIE WALKER PRESSより)
観たことがないグザヴィエ・ドランの監督作品を今後観て行こうと思う。
まずは、19歳の時の初監督作品で脚本、主演も兼ねた半自伝的な内容という本作。
青年期特有の現象と言っていいのか、二人暮らしをしているユベールの過剰な母親への反撥。
その鬱屈した母親に対する態度の中には、幼かった頃に注がれていた愛情たっぷりの生活の裏返しが潜んでいたりする。
ユベールは独立して一人生活をしたいのに、まだ子供としてしか認めて貰えず、挙げ句の果ては寄宿学校へ行かされてしまう。
そんなユベールは同性愛者であったりするので、それを他から教えて貰った母親は動転するより仕方がなかった。
親との不和、愛情と嫌悪、それに対するユベールの苦悩が目いっぱいに描かれていて、筋としてはほぼそのことで終わっている。
だから内容の起伏は貧しいとしても、19歳の青年がこれぼどまでに出演者の人間性を生かし切っている現実に感心させられる。
それ程才能がほとばしっている、と言っていいのではないかと納得した。