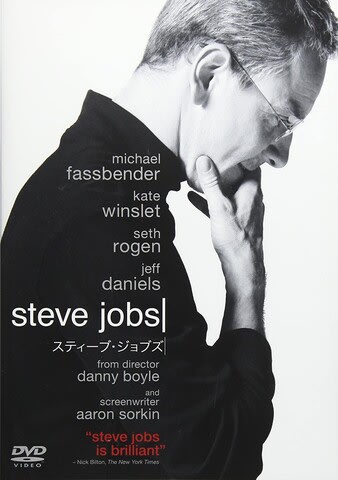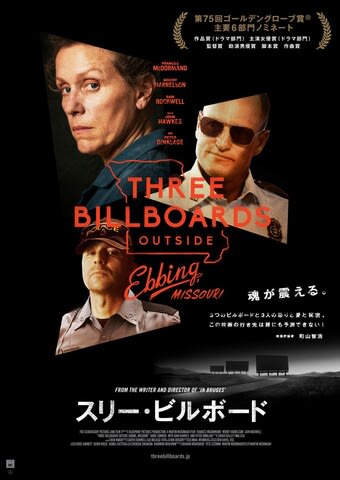『わたしはロランス』(グザヴィエ・ドラン監督、2012年)を観た。
カナダ・モントリオール。
国語教師をしながら小説を書いているロランスは、35歳の誕生日を迎え、交際相手のフレッドにある告白をする。
それは、自分の身体の性に違和感を持っており女性になりたいと思っているということだった。
この告白にショックを受けたフレッドは、これまでに二人が築いてきたものが偽りであるかのように思えてしまい、ロランスを非難する。
しかしかけがえのない存在であるロランスを失うのを恐れ、フレッドはロランスの良き理解者となることを決意。
ロランスに女性の立場からメイクなどについてアドバイスするが、モントリオールの田舎町では偏見を持たれ、彼らに対する風当たりは強かった・・・
(MOVIE WALKER PRESSより)
カミングアウトするということ。
女性になりたい願望のロランスはフレッドにそのことを打ち明ける。
ただ、ロランスはその願望があっても男性を好きになるわけではなく、女性のフレッドを深く愛している。
ショックを受けるフレッドはロランスを愛するがうえに理解者として努力する。
しかし、女装したロランスに世間の目は冷たい。
それが故に、ロランスは職を失い、やがてフレッドはうつ病となっていく。
やがて二人は別れ、ロランスは理解者シャルロットを得、フレッドは彼氏アルベールと結婚しレオを産む。
そんなロランスとフレッドだが、内心の愛は変わらない。
再会した二人の、雪積もるケベック州の小島“イル・オ・ノワール”への逃避行。
ロランスは自分に正直でありたいのに、フレッドはロランスを男として愛したい。
その葛藤故にまたしても別れ。
数年後、再びバーで再会する二人だったがそこでも口論になり、それが決定打となり、秋の気配の中、完全に別々の道を歩み出す。
ラストでの、1987年の二人の出会いのシーン。
あれから時は経ち、もうすぐ21世紀、その長きに渡るロランスとフレッドの愛の軌道。
作品は2時間50分近くの長さがあるが、その間退屈さを感じさせない。
要所要所に現れるビジュアル化された映像とか、二人の言い合いにおける素早いカメラの動き。
二人が感情を露わにするロランス役のメルビル・プポーとフレッド役のスザンヌ・クレマンの心情表現の凄さ。
監督のグザヴィエ・ドランは、自身が“ゲイ”であることを自認していることもあってか、感情の機微の表し方がとても20代前半の人間とは思えないほど卓越している。
この作品はとても重要だと感じるので、再度機会を見つけて観てみたいと思う。