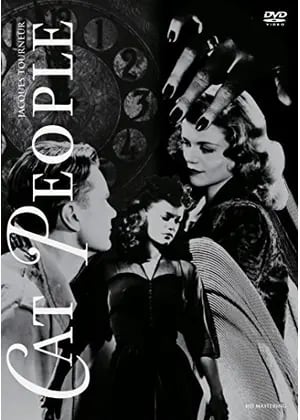『子供たちは見ている』(ヴィットリオ・デ・シーカ監督、1943年)を、県図書館からDVDを借りてきて観た。
中流家庭のアンドレアとニーナは、息子プリコと共にローマ郊外のアパートに住んでいた。
家庭は一見幸福そうにみえたが、実はニーナにはロベルトという愛人がいた。
その日もニーナは、プリコと散歩がてら公園に行き、プリコが人形芝居などに夢中になっている間を利用してロベルトと密会した。
ニーナはそこで、ジェノヴァ行き列車で駆落ちしようとロベルトに迫られ、夜、アンドレアの留守を見計って家を出た。
プリコを残されて困ったアンドレアは、取りあえず洋裁店を経営しているニーナの姉の許にプリコをあずけ、翌日、田舎に住む自分の母のところへ連れて行った。
母は娘パオリーナにプリコの世話をいいつけたが、ある晩パオリーナが恋人と密会している時、それを垣間見たプリコは誤って彼女の頭上に植木鉢を落してしまい、
その結果、またアンドレアの許に戻されてしまった・・・
(映画.comより修正して一部抜粋)
その後、プリコが高熱を発したためかそれを知ったニーナは、再びプリコと夫の元に戻ってくる。
アンドレアはプリコのためにニーナとよりを戻し、三人の生活は平穏となってリゾート地へ海水浴に出かけた。
ところが、どこで知ったのかそこへロベルトが現われる。
ロベルトは再び執拗にニーナを口説く。
社用でアンドレアが先に帰ったのを利用し、ロベルトとニーナは束の間の逢瀬を楽しんだ。
それを見てしまうプリコ。
母親が自分から去って行くのではないかと考えるプリコは、ローマの父の元へ帰ろうと一人、鉄道線路をとぼとぼと歩きつづける。
まだその先は続くが、プリコが母親とロベルトの仲を目撃する場面は先の公園でもあり、要は大人の事情で、頼るべき親から見放される子供の状況が映し出される。
子供の視点から大人の世界ないし社会を見たデ・シーカの名作『靴みがき』(1946年)、『自転車泥棒』(1948年)の原点はこの作品からかなと、やや甘い出来としても納得できる内容だった。
中流家庭のアンドレアとニーナは、息子プリコと共にローマ郊外のアパートに住んでいた。
家庭は一見幸福そうにみえたが、実はニーナにはロベルトという愛人がいた。
その日もニーナは、プリコと散歩がてら公園に行き、プリコが人形芝居などに夢中になっている間を利用してロベルトと密会した。
ニーナはそこで、ジェノヴァ行き列車で駆落ちしようとロベルトに迫られ、夜、アンドレアの留守を見計って家を出た。
プリコを残されて困ったアンドレアは、取りあえず洋裁店を経営しているニーナの姉の許にプリコをあずけ、翌日、田舎に住む自分の母のところへ連れて行った。
母は娘パオリーナにプリコの世話をいいつけたが、ある晩パオリーナが恋人と密会している時、それを垣間見たプリコは誤って彼女の頭上に植木鉢を落してしまい、
その結果、またアンドレアの許に戻されてしまった・・・
(映画.comより修正して一部抜粋)
その後、プリコが高熱を発したためかそれを知ったニーナは、再びプリコと夫の元に戻ってくる。
アンドレアはプリコのためにニーナとよりを戻し、三人の生活は平穏となってリゾート地へ海水浴に出かけた。
ところが、どこで知ったのかそこへロベルトが現われる。
ロベルトは再び執拗にニーナを口説く。
社用でアンドレアが先に帰ったのを利用し、ロベルトとニーナは束の間の逢瀬を楽しんだ。
それを見てしまうプリコ。
母親が自分から去って行くのではないかと考えるプリコは、ローマの父の元へ帰ろうと一人、鉄道線路をとぼとぼと歩きつづける。
まだその先は続くが、プリコが母親とロベルトの仲を目撃する場面は先の公園でもあり、要は大人の事情で、頼るべき親から見放される子供の状況が映し出される。
子供の視点から大人の世界ないし社会を見たデ・シーカの名作『靴みがき』(1946年)、『自転車泥棒』(1948年)の原点はこの作品からかなと、やや甘い出来としても納得できる内容だった。