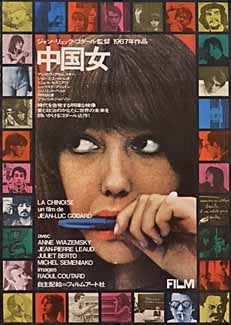『エドワールとキャロリーヌ』(ジャック・ベッケル監督、1951年)を観た。
パリのアパルトマンで、睦まじく暮らしている若夫婦のエドワールとキャロリーヌ。
ある日の夜、無名のピアニストのエドワールを売り出すために、キャロリーヌの叔父クロードが屋敷でパーティーを開く。
そのために、キャロリーヌはエドワールに花を買いに行かせ、自分は古いイブニング・ドレスを引っ張り出す。
帰ってきたエドワールが、パーティーのためのタキシードを着ようとするとベストが見当たらない。
そこでキャロリーヌが叔父の家に電話を掛け、その後で、叔父の息子アランのベストを借りにエドワールを行かせる。
その間に、キャロリーヌはドレスを今風にするため、裾の前側をハサミで短かくしてしまう。
帰ってきたエドワールは、喜ぶキャロリーヌのその姿を見て、大事なドレスを切ってしまったと怒り、キャロリーヌを叩く。
それで二人は大喧嘩。
腹を立てたまま一人パーティーに出席したエドワールは、皆に“妻は身体の調子が悪い”と誤魔化す。
心配したアランが電話をすると、受話器の向こうから“離婚する!”と息巻くキャロリーヌの声がして・・・
パーティーに行く準備の夕方7時半から、深夜帰宅した後までの単純な物語。
その間に起きる夫婦喧嘩を中心にして、全体をコミカルに描いた実に微笑ましい話。
まずキャロリーヌ役の“アンヌ・ヴェルノン”がとってもいい。
ドレスを着ながらラジオに合わせウキウキと踊ってみせる場面なんか最高である。
エドワールの“ダニエル・ジェラン”もまた役柄がピッタシで、二人の息が合っている。
この“ダニエル・ジェラン”のピアニスト振りも、ピアノを弾く手元がリアルで、成る程と思う。
叔父クロードも、みんなにかいがいしく世話を焼く姿が笑いを誘い、場面を引き立たせる。
そもそもキャロリーヌが、離婚して実家に帰ろうとしたキッカケは、売り言葉に買い言葉。
だから、痴話ゲンカがこじれる。
この辺りは、世間でよくある話で、至ってリアリティ感が漂っている。
でも、ラストのラストで元の鞘に収まり、本当によかったねと微笑んでしまう。
観て幸福感を味わえるこんな作品は、楽しさの麻薬みたいだと言ったらいいのか、何度も繰り返し観たくなる。
パリのアパルトマンで、睦まじく暮らしている若夫婦のエドワールとキャロリーヌ。
ある日の夜、無名のピアニストのエドワールを売り出すために、キャロリーヌの叔父クロードが屋敷でパーティーを開く。
そのために、キャロリーヌはエドワールに花を買いに行かせ、自分は古いイブニング・ドレスを引っ張り出す。
帰ってきたエドワールが、パーティーのためのタキシードを着ようとするとベストが見当たらない。
そこでキャロリーヌが叔父の家に電話を掛け、その後で、叔父の息子アランのベストを借りにエドワールを行かせる。
その間に、キャロリーヌはドレスを今風にするため、裾の前側をハサミで短かくしてしまう。
帰ってきたエドワールは、喜ぶキャロリーヌのその姿を見て、大事なドレスを切ってしまったと怒り、キャロリーヌを叩く。
それで二人は大喧嘩。
腹を立てたまま一人パーティーに出席したエドワールは、皆に“妻は身体の調子が悪い”と誤魔化す。
心配したアランが電話をすると、受話器の向こうから“離婚する!”と息巻くキャロリーヌの声がして・・・
パーティーに行く準備の夕方7時半から、深夜帰宅した後までの単純な物語。
その間に起きる夫婦喧嘩を中心にして、全体をコミカルに描いた実に微笑ましい話。
まずキャロリーヌ役の“アンヌ・ヴェルノン”がとってもいい。
ドレスを着ながらラジオに合わせウキウキと踊ってみせる場面なんか最高である。
エドワールの“ダニエル・ジェラン”もまた役柄がピッタシで、二人の息が合っている。
この“ダニエル・ジェラン”のピアニスト振りも、ピアノを弾く手元がリアルで、成る程と思う。
叔父クロードも、みんなにかいがいしく世話を焼く姿が笑いを誘い、場面を引き立たせる。
そもそもキャロリーヌが、離婚して実家に帰ろうとしたキッカケは、売り言葉に買い言葉。
だから、痴話ゲンカがこじれる。
この辺りは、世間でよくある話で、至ってリアリティ感が漂っている。
でも、ラストのラストで元の鞘に収まり、本当によかったねと微笑んでしまう。
観て幸福感を味わえるこんな作品は、楽しさの麻薬みたいだと言ったらいいのか、何度も繰り返し観たくなる。