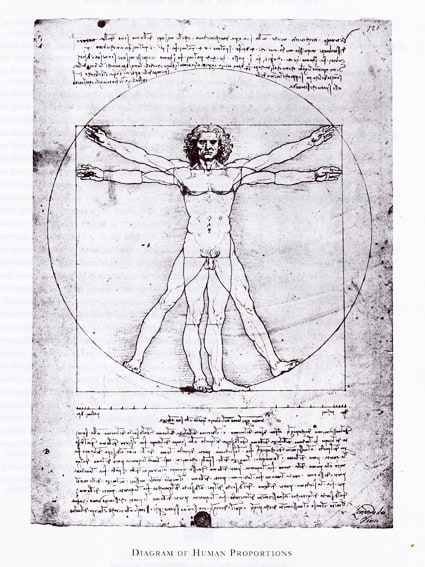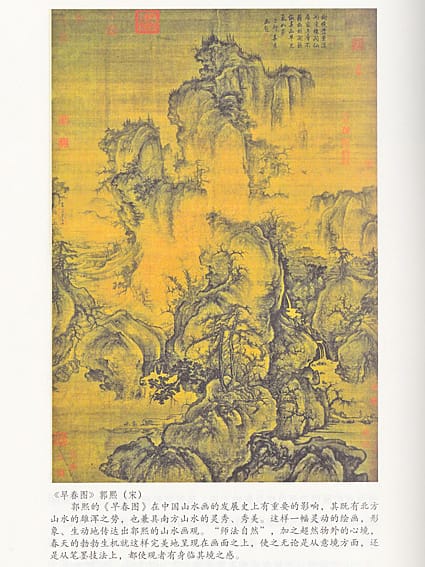(『新訳絵入伊勢物語』吉井勇, 竹久夢二著, 阿蘭陀書房, 1917)
(『新訳絵入伊勢物語』吉井勇, 竹久夢二著, 阿蘭陀書房, 1917)
小町集に「井出の島といふ題を」という詞書の歌がある。
熾のゐて身を焼くよりもわびしきは宮こ島辺の別(わかれ)なりけり
(和歌文学大系18『小町集/業平集/遍昭集/素性集/伊勢集/猿丸集』 室城英之他編, p9, 明治書院, 1998)
和歌文学大系の脚注には、「井出の島」は京都府綴喜郡井手町を流れる井出川の中の島かと記載されている。小野小町の終焉の地とされる場所は全国にあり、京田辺市に木津川を挟んで隣接する井手町には石積みの小町塚がある。『小町集』には名勝、井出の玉川(井出川)の花で有名な山吹を詠んだ歌があり、小町と井出の里は縁が深いのである。
井出の山吹を
色も香もなつかしき哉蛙(かはず)鳴く井出のわたりの山吹きの花
さらに同書の脚注では「宮こ島辺の別」に関して、都へ行く人と島に残される人との別れとの説明がある。一方、このおきのゐての歌は『古今集和歌集』墨滅歌(ぼくめつか、すみけちうた)にも収載されていて、
おきのゐ みやこしま
おきのゐて身を焼くよりもかなしきは都島辺の別れなりけり
(日本古典文学全集11『古今和歌集』小松正夫、松田成穂編, p418-419, 小学館, 1994)
日本古典文学全集の脚注では、「おきのゐ」も「みやこしま」も地名であろうがあきらかでない、さらに「島辺」は彼女が住んでいたとされる東北地方のどこかであろう、と記され見解が分かれるのである。
 (和泉書院影印叢刊27『伊勢物語 慶長十三年刊 嵯峨本第一種』片桐洋一編, p226-227, 和泉書院, 1981)
(和泉書院影印叢刊27『伊勢物語 慶長十三年刊 嵯峨本第一種』片桐洋一編, p226-227, 和泉書院, 1981)
おきのゐての歌は、『伊勢物語』百十五段では乙女が紅涙を絞る筋書になる。
むかし、陸奥の國にて、をとこ女すみけり。をとこ、「都へいなむ」という。この女いとかなしうて、馬のはなむけをだにせむとて、おきのゐて、都島という所にて、酒飲ませてよめる。
おきのゐて身をやくよりもかなしきは都しまべの別れなりけり
(岩波文庫『伊勢物語』大津有一校註、松田成穂編, p73, 岩波書店, 1994)
本書の冒頭には、底本に天福本系統の善本学習院大学蔵伝定家本を用い、宮内庁書陵部蔵冷泉為和本、天理図書館蔵法橋玄津筆本などで校合を加えたとの記載がある。何故これをわざわざ書き留めるかといえば、おきのゐての歌の後に「とよめりけるにめでて、とまりけり」と続く伊勢物語本があるからである。「高安の女」のブログ記事(2015/01/31)に挙げた、藤井孝尚の『伊勢物語新釋』を底本とした伊勢物語
(角川文庫『伊勢物語』中河與譯註, 角川書店, 1953)がそうである。
「とよめりけるにめでて、とまりけり」が伊勢物語のどの写本や注釈本に記載されているかはともかく、この末尾の一文が第百十五段で繰り広げられるものがたりにどのような効果を与えているのだろうか。「とよめりけるにめでて、とまりけり」を欠いた、女の歌で終わる第百十五段は読む者に余韻を残してくれる。別れを既成のものとして都に帰り行くをとこのために、女は道中の無事を祈りはなむけの宴を開く。ふたたび還らぬと承知の上で流れの中に美しい花をそっと浮かべるのにも似た、女の無私の佇まいが心に響く。とどまって欲しいのが女の本心である。それでも去りゆくをとこを見守り、すきと背筋を伸ばす女であるからこそ美しい立姿となる。「とよめりけるにめでて、とまりけり」は語り過ぎた感がある。『去来抄』に、いと櫻の十分に咲きたる形容、能謂おほせたるに侍らずやと述べる去来の言葉に、松尾芭蕉が返したのは「謂應せて何か有(いひおほせて何かある」(ものごとをすべて言い尽くしてしまえば何が残るのだ)であった。
 (中尾家本伊勢物語絵本/『伊勢物語絵巻絵本大成』資料編, p216, 羽衣国際大学日本文化研究所編, 角川学芸出版, 2009)
(中尾家本伊勢物語絵本/『伊勢物語絵巻絵本大成』資料編, p216, 羽衣国際大学日本文化研究所編, 角川学芸出版, 2009)
 (チェスター・ビーティー図書館本伊勢物語絵本/『伊勢物語絵巻絵本大成』資料編, p247, 羽衣国際大学日本文化研究所編, 角川学芸出版, 2009)
(チェスター・ビーティー図書館本伊勢物語絵本/『伊勢物語絵巻絵本大成』資料編, p247, 羽衣国際大学日本文化研究所編, 角川学芸出版, 2009)
近代に飛ぶが『新訳絵入伊勢物語』の第百十五段も「男はこの歌を聴いて哀れになって、またそこに留まることになった。」で終わる。その挿絵はどうかといえば、第百十五段に挟まれている女の絵がみやこしまべの女とは限らないのかもしれないが、竹久夢二はひとり立ち尽くす艶な女を描いている。それが冒頭の画である。一方上に掲げた『伊勢物語絵巻絵本大成』掲載の大和絵で第百十五段を探してみると、をとこも女も従者ももれなく細やかに描かれている。玄人素人に拘らず百人居れば百様のみやこしまべのわかれの絵があるに違いない。最後に雑魚の魚交りで、私のみやこしまべの別れである。竪長の画面、辺角の構図にて左下方に斜めに汀線が走り、いまだ波に攫われずに扇が捨てられている。白砂の余白が続いた画面上方、右寄りの遠景に一本の松が霞む。左下が女で右上がをとこである。すでに画中には女もをとこも姿はない。