
5月26日、5時間をかけて玉原高原尼ケ禿山を歩いてきた。
山手駅〜上越線沼田駅、関越交通バスで玉原高原へ、 5時間かかった。
5時間かかった。
関越バス利用は三度目、鹿俣山が関東百名山に制定された2021年7月、
昨年の秋には迦葉山へ、そして今回の尼ケ禿山。
バス時間を考慮し、行動時間は3.5時間急げ



10:30  センターハウス
センターハウス 



ハルゼミ

ノビネチドリ:ラン科 花の形が、 千鳥が飛ぶ姿に似ている
千鳥が飛ぶ姿に似ている

尼ケ禿山(あまがはげやま)

10:55  東京大学セミナーハウス(奥の山は上州三峰山)
東京大学セミナーハウス(奥の山は上州三峰山)

カキドウシ:シソ科の唇形花
生薬としても使われる薬草。利尿、消炎薬として用いられる。

ここからブナ林の登山道へ 


ブナ林を春ゼミの声を聞きながら歩く

ギンリョウソウ:イチヤクソウ科
葉緑素を持たないので光合成は不可、土の養分で成長する。

オオカメノキ:スイカズラ科 別名ムシカリ

🍄

ブナ:葉は長さ10cm、幅6cmぐらいで、際だった特徴はない。
幹はまっすぐ伸び、樹高は高いものでも30m。
幹の太さは1mを越えるものは少ない。
白っぽい灰色の、すべすべした肌をしている。
成長が早く、燃やすと火力が強いので
かっては重要な建材として、民生用、鉱物の精錬用に使われた。
【ブナをめぐる白神の木:より】

11:10 玉原越え分岐 

ツクバネソウは4枚葉

エンレイソウは3枚葉

サワハコベ:ナデシコ科

11:35 迦葉山分岐 (玉原ダムへ降りて登り返す)
(玉原ダムへ降りて登り返す)

ガスが湧いて眺望は臨めない 



11:40・12:00 昼食 尼ケ禿山:1446m
沼田市と水上町の境、東麓に玉原ダムがある。
こしあぶら採取の おじさんとしばし”山菜談義”
おじさんとしばし”山菜談義”

 迦葉山方面
迦葉山方面

オオバユキザサ

🍄 🍄 🍄

カエデの実は「翼果」と呼ばれくるくる回って下に落ちる
12:45 東大セミナーハウスへ戻って来た


レンゲツツジ

 フキノトウの実
フキノトウの実

蚊の「真昼の情事」


13:00・13:30 玉原湿原 散
散 策
策
上州武尊山西南麓の標高1,200~1,500mに広がる玉原高原。
玉原湿原では「色とりどりの高山植物が楽しめる」とあるが?????

 ヤマカカシ、獲物が腹に
ヤマカカシ、獲物が腹に 休んでいました
休んでいました

サワ ウルシ:トウダイグサ科
ウルシ:トウダイグサ科

ズミ:バラ科 別名コナシ

ムラサキヤシオ

ミズバショウ:サトイモ科
花は終盤、鹿の食害で少ない、木道の下に保護されていた

ワタスゲ:風に揺れて

サワウルシとコバイケイソウ

この突起のある葉は????

13:45 センターハウスBS、キケマンが群生していた

13:55発の関越交通バスで沼田駅へ

15:00 沼田駅着、16:10発の上越線で帰途についた
「迦葉山龍華院弥勒寺」は関東三大👺天狗の御山

*
行程:標高差329m/7km/3時間
5:34 JR山手駅 === 9:20 上越線沼田駅 =10:30 玉原高原
⇒10:30 センターハウス (玉原湿原)⇒10:55 セミナーハウス
⇒11:40・12:00 尼ケ禿山・昼食 ⇒(往路下山)13:00 玉原湿原散策
⇒13:55 センターハウスBS = 16:10 沼田駅===19:50 山手駅











 二ツ岳(榛名山)を伊香保
二ツ岳(榛名山)を伊香保 からピス
からピス トンしてきた。
トンしてきた。

 シンボル。
シンボル。

 段、標高差
段、標高差 m、約15分かかった)
m、約15分かかった)
 ・
・
 オダマキ:園芸種
オダマキ:園芸種
 縁結び・
縁結び・ 家内安全、
家内安全、 商売繁盛
商売繁盛 手広く扱っています。
手広く扱っています。

 緑も見頃
緑も見頃













 岳へ、木段の登り
岳へ、木段の登り







 火山で雄岳と雌岳からなる双
火山で雄岳と雌岳からなる双 耳
耳
 昼
昼 食
食

 バネソウ:ユリ科
バネソウ:ユリ科








 間に合った
間に合った
 移
移 動
動 が180kmと長い、山手駅5:34発・上野東京ライン・上越線を
が180kmと長い、山手駅5:34発・上野東京ライン・上越線を ”で10:05 迦葉山BSへ
”で10:05 迦葉山BSへ


 参道入口、舗装道路が並行しています
参道入口、舗装道路が並行しています
 山門(道は荒れています、徒歩で登拝する人は皆
山門(道は荒れています、徒歩で登拝する人は皆 無?)
無?)






 埋もれてます
埋もれてます
 もう
もう

 説:怪力の僧・
説:怪力の僧・ 迦葉(仏陀の十大弟子の一人)の化身である末永く寺を守ろう」
迦葉(仏陀の十大弟子の一人)の化身である末永く寺を守ろう」
 天狗信仰のお寺「弥勒寺」誕生のお話でした
天狗信仰のお寺「弥勒寺」誕生のお話でした



 紅葉の見頃でした
紅葉の見頃でした
 和尚台
和尚台


 御嶽山神社
御嶽山神社


 ブッポウソー
ブッポウソー

 終わりの情報から
終わりの情報から 迦葉山に変更した。
迦葉山に変更した。
 葉が
葉が
























 笑
笑

 交換”で教えてもらった。
交換”で教えてもらった。





 整備されています
整備されています










 上越線の車窓からはこの山が大きく見える?
上越線の車窓からはこの山が大きく見える? 














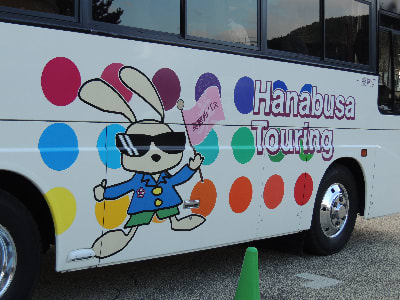






 凍っていた(下りはアイゼン必要)
凍っていた(下りはアイゼン必要)

 停滞
停滞 少しで稜線だった。稜線まで登れば
少しで稜線だった。稜線まで登れば 稲包山も見えたが・・・・。
稲包山も見えたが・・・・。 エネルギーを補給し下山準備
エネルギーを補給し下山準備
 !!!
!!!









 猿ヶ京温泉「
猿ヶ京温泉「 まんてん星の湯」へ
まんてん星の湯」へ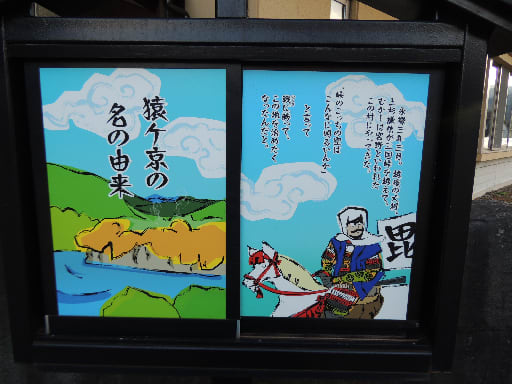





 揮毫は”渋沢栄一翁”だそうです
揮毫は”渋沢栄一翁”だそうです
 心境を」慰めるように
心境を」慰めるように 月が。
月が。 いくら
いくら キャッシュバックあるのか
キャッシュバックあるのか