九 鬼山~菊花山を歩いてきました。
鬼山~菊花山を歩いてきました。
パートナーは2年越しの念願かなった k池さんです。
k池さんです。
 :富士急行
:富士急行
「富士芝桜まつり」この時期、御坂山塊へ行くには 渋滞を覚悟しなければなりません。
渋滞を覚悟しなければなりません。
 :禾生駅
:禾生駅
9:15 今日の基点は「禾生(かせい)」駅です。
 :山梨実験線
:山梨実験線
九鬼山は「リニア実験線」が設置されています。
2014年10月17日、東海旅客鉄道会社( JR東海)による全国新幹線鉄道整備法に基づく
JR東海)による全国新幹線鉄道整備法に基づく
工事実施計画(品川~名古屋)が認可されました。
赤石山脈(南アルプス)貫くトンネルが計画されているので、”他人事ではないですよ。
 :水路
:水路
この水路をくぐって登山口へ向かいます。(左奥)
:オドリコソウ :ヒメオドリコソウ
 オドリコソウとは初の
オドリコソウとは初の 遭遇でした。
遭遇でした。
 :愛宕神社
:愛宕神社
9:30 愛宕神社、御存知「 」の神様です、ここが登山口です。
」の神様です、ここが登山口です。
:チゴユリ(多かった)
:イカリソウ 
チゴユリ、イカリソウ、ヒトリシズカ、ハルリンドウ、十二単が迎えてくれました。

まだ 晴れています。(選挙カーの声がここまで聞こえてきました)
晴れています。(選挙カーの声がここまで聞こえてきました)
:ハルリンドウ(鮮やかな青です)
:ヒトリシズカ(杉の林床に多い) :ジュウニヒトエ
 :新緑
:新緑
 新緑が
新緑が まぶしい、まさに「グリーン・
まぶしい、まさに「グリーン・ シャワー」です。
シャワー」です。
 :田野倉分岐
:田野倉分岐
10:10 田野倉(駅)分岐、 半分登ってきました。
半分登ってきました。
 :風が
:風が
 風が出てきました、(予報にあった、
風が出てきました、(予報にあった、 にわか雨が心配です)
にわか雨が心配です)
:エイザンスミレです。
山頂直下、杉の林床にはいつくばるように咲いていました。
地味が薄いせいか、小さいし細い。
 :天狗岩
:天狗岩
10:35 富士山の 眺望が期待できる
眺望が期待できる 展望台があります。
展望台があります。
 :雲が
:雲が
 :残念
:残念
(左)御正体山の奥に富士山があるんですが・・・


 :2012年3月
:2012年3月
 こんな感じですが、今日は見えませんでした。
こんな感じですが、今日は見えませんでした。
 :九鬼山
:九鬼山
10:55 九鬼山頂です、眺望は北側にしかありません。
雨が ポツ
ポツ ポツ落ちてきました、(予報より少し
ポツ落ちてきました、(予報より少し 早い!!)
早い!!)
 :下り
:下り
山頂直下の下り、結構 厳しい尾根道でした。
厳しい尾根道でした。
:センボンヤリ :キジムシロ :ミヤマエンレイソウ
:ユリワサビ :ユキザサ :スミレ
厳しい下りが 終わり、沢沿いの傾斜地に咲いていたお花さん達です。
終わり、沢沿いの傾斜地に咲いていたお花さん達です。

小雨の中、(取り急ぎ)ここで


 昼食をとりました。
昼食をとりました。
 :馬立山
:馬立山
12:10 札 金峠、ここから小さなピーク
金峠、ここから小さなピーク を越えて行きます。
を越えて行きます。
12:45  立山(後ろは九鬼山です)
立山(後ろは九鬼山です)
小雨ですが降っています、南側では 雷が鳴っていました。
雷が鳴っていました。
 :山桜
:山桜
:山桜でしょうか
 :茸です
:茸です
松の木に直接生えていました。( あまり見ない絵です
あまり見ない絵です )
)
 :沢井沢ノ頭
:沢井沢ノ頭
13:00 沢井沢ノ頭(雨は降ったりやんだり、雷は治まっていました)
ここから菊花山までは 下り、御前山分岐からは、
下り、御前山分岐からは、 初めて歩く道です。
初めて歩く道です。
急な下り、しかも ザレていて滑る、小雨の中
ザレていて滑る、小雨の中 をさして歩きました。
をさして歩きました。
 :山ツツジ
:山ツツジ
菊花山鞍部から二つの ニセピークを越えて、
ニセピークを越えて、
 :岩場
:岩場
岩場を越え、ヤセ尾根を 歩いて・・・。
歩いて・・・。

13:50 菊花山頂です。
 :岩殿山
:岩殿山

左:扇山、右:百蔵山

左:沢井沢の頭、右奥:九鬼山 ( 縦走してきました)
縦走してきました)
 :眼下
:眼下
jump !!すればもう大月駅です。
!!すればもう大月駅です。
 :ツクバネウツギ
:ツクバネウツギ
和名では「 衝羽根空木」と書きます。
衝羽根空木」と書きます。
 :ザレの下り
:ザレの下り
この下りがスリリングだった。
足元は①ザレテいて滑る、②両方切れている、③急登” 拍子”揃っている。
拍子”揃っている。
トラロープがあるが、これに命は 託せない。
託せない。
話には いていたが、あまり
いていたが、あまり 使いたくない下山道だった。
使いたくない下山道だった。
 :金毘羅神社
:金毘羅神社
下界に下りてきました。
 :大月駅
:大月駅
14:30 大月駅です。
(看板が変わっています、予定より約1時間 早い歩程でした)
早い歩程でした)
*

 行程:標高差528m、約9km、5時間
行程:標高差528m、約9km、5時間 

9:15 禾生駅 ⇒9:30 愛宕神社 ⇒10:10 田野倉分岐 ⇒10:35 天狗岩
⇒10:55 九鬼山 ⇒11:40~11:50 展望地・昼食 ⇒12:10 札金峠
⇒12:45 馬立山 ⇒13:00 沢井沢ノ頭 ⇒13:50 菊花山 ⇒14:30 大月駅
**
 twins
twins  たちです。
たちです。








































 です。
です。 :the鎌倉
:the鎌倉 :
: 始めてです。
始めてです。 :
: 静かな商店街です。
静かな商店街です。 :花屋さん
:花屋さん
 由比ガ浜大通り(長谷小路)の交差点に置かれている六体の地蔵。
由比ガ浜大通り(長谷小路)の交差点に置かれている六体の地蔵。 刑場の跡地。 問注所での裁判の結果、有罪となった者が、
刑場の跡地。 問注所での裁判の結果、有罪となった者が、 処刑された。
処刑された。 供養のための六体の地蔵が建てられたのだという。
供養のための六体の地蔵が建てられたのだという。  :米屋
:米屋 米を挽く機械が並んでいた。
米を挽く機械が並んでいた。


 :炭屋
:炭屋 :住職?
:住職? 眺望」が売りです。
眺望」が売りです。



 :良縁地蔵
:良縁地蔵 って」大事ですね。
って」大事ですね。









 :良縁地蔵
:良縁地蔵 :海
:海 :工事中
:工事中 工事中でした。
工事中でした。
 財源」の一つです。
財源」の一つです。


 :仏足
:仏足 扁平足」だったかもしれません。
扁平足」だったかもしれません。 :牡丹
:牡丹

 :修学旅行
:修学旅行

 らしい絵です。
らしい絵です。 :昼食
:昼食 ラーメンを食べました。
ラーメンを食べました。 :高徳院
:高徳院 不明)の鎌倉大仏、当初は木造だったとか。
不明)の鎌倉大仏、当初は木造だったとか。
 :大仏隧道
:大仏隧道 入口になっています。
入口になっています。


 :分岐
:分岐 :大仏切通し
:大仏切通し 「切通」とは、山や丘などを切り開いて通した道のこと。
「切通」とは、山や丘などを切り開いて通した道のこと。  :葛原岡神社
:葛原岡神社 :神様?
:神様? 昼寝」をしていました。
昼寝」をしていました。
 :
: :宝の庭
:宝の庭 宝の庭」と命名された場所、ニリンソウが咲いていました。
宝の庭」と命名された場所、ニリンソウが咲いていました。

 :浄智寺山門
:浄智寺山門 コーヒーを飲んで帰宅しました。
コーヒーを飲んで帰宅しました。 km、
km、 万歩、
万歩、 3.5時間の「鎌倉Walking」でした。
3.5時間の「鎌倉Walking」でした。



 Tさん同行、笠山峠~堂平山~剣ヶ峰~大霧山と3つの峰を
Tさん同行、笠山峠~堂平山~剣ヶ峰~大霧山と3つの峰を 越えていきます。
越えていきます。
 :今日のルート
:今日のルート 立ったままだった。
立ったままだった。 急ぎ歩き始める。
急ぎ歩き始める。


 :
: :お馴染?
:お馴染? :ニリンソウ
:ニリンソウ





 :笠山峠
:笠山峠 B
B B
B Qをしていました)
Qをしていました) :登山道
:登山道 :両神山
:両神山 :浅間山
:浅間山 撮った北側の眺望です。
撮った北側の眺望です。 :堂平山
:堂平山 眺望がいい。
眺望がいい。 :南側
:南側 :西側
:西側 :大霧山
:大霧山
 県道に出て、ここから
県道に出て、ここから 剣ヶ峰への登りです。
剣ヶ峰への登りです。 :剣ヶ峰
:剣ヶ峰 印”です。(他に
印”です。(他に 何もない)
何もない) :白石峠
:白石峠 雪が舞ったという)
雪が舞ったという) :マジっすか?
:マジっすか? :頑張れ!!
:頑張れ!!
 :下り
:下り ダウンを
ダウンを
 :定峰峠
:定峰峠 茶屋がありますが、ここは
茶屋がありますが、ここは



 :祠
:祠 :旧定峰峠
:旧定峰峠 :ニセピーク
:ニセピーク :官ノ倉山
:官ノ倉山 前回縦走した石尊山(左)と官ノ倉山(右)です。
前回縦走した石尊山(左)と官ノ倉山(右)です。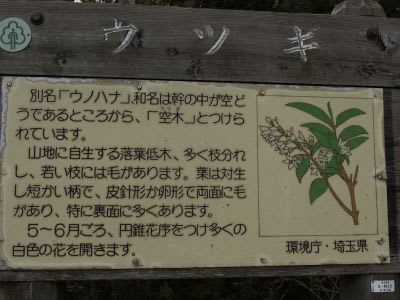 :
:


 :大霧山
:大霧山 :武甲山
:武甲山 :縦走路
:縦走路 鈴山(679m)と
鈴山(679m)と 寄居へ下ります。
寄居へ下ります。 :粥仁田峠
:粥仁田峠 バス停へ下ります。
バス停へ下ります。 予定は二本木峠まで行き、内手バス停へ下る、時間がないので)
予定は二本木峠まで行き、内手バス停へ下る、時間がないので) :
: :大霧山
:大霧山


 :
:


 :橋場バス停
:橋場バス停 員」帰りの電車に遅れないか
員」帰りの電車に遅れないか
 ,
, 参加しました。
参加しました。 東武東上線小川町の南に横たわるなだらかな山(標高298m)
東武東上線小川町の南に横たわるなだらかな山(標高298m)

 :県道
:県道 :登山口
:登山口 費やした。(標示もあるがわかりづらい)
費やした。(標示もあるがわかりづらい) :満開の桜
:満開の桜 :稲田天満宮
:稲田天満宮 上まで行ってきた。
上まで行ってきた。 :守り神?
:守り神?


 :遊歩道
:遊歩道 遊
遊



 :能書き
:能書き おさまりました。
おさまりました。


 :霧
:霧 :山頂
:山頂 :小川町
:小川町 :青山城分岐
:青山城分岐 :
: 静寂の世界だった。
静寂の世界だった。 :
: :
: :雑木林
:雑木林 登山道を行きます。
登山道を行きます。




 出会った、花です。
出会った、花です。 シュンランは最後の登りに残っていました。
シュンランは最後の登りに残っていました。 :大日山
:大日山 :QRコード
:QRコード 何に使うんでしょうか?
何に使うんでしょうか? :分岐
:分岐 :山桜
:山桜 :
:




 :
:


 :分岐
:分岐 2007年のものだった)
2007年のものだった) :
: 禁にしたようだ)
禁にしたようだ) :
: 柳町橋手前から「カタクリとニリンソウの里」が槻川沿いに約600m続いていた。
柳町橋手前から「カタクリとニリンソウの里」が槻川沿いに約600m続いていた。







 :西光寺
:西光寺 :西光寺
:西光寺



 :円通寺
:円通寺



 :土肥実平
:土肥実平
 :
:

 :
: :
:




 初夏だった。
初夏だった。 :頼朝遺跡①
:頼朝遺跡① :
:




 :
: :立石
:立石 余裕があったのか?
余裕があったのか?


 退屈このうえない・・・
退屈このうえない・・・ 休息を繰り返す"間歇性跛行(かんけつせいはこう)"の症状がある身にはなおさらだ。
休息を繰り返す"間歇性跛行(かんけつせいはこう)"の症状がある身にはなおさらだ。 :
: :あと少し
:あと少し

 案内図だ。
案内図だ。 :
:
 :
: :
: :
: :
:
 寄ることに(往復40分の歩程)
寄ることに(往復40分の歩程) 敗れた頼朝が隠れたといわれる窟。
敗れた頼朝が隠れたといわれる窟。 大
大 小20体余りの石仏が天然の岩屈内に並ぶ。
小20体余りの石仏が天然の岩屈内に並ぶ。 年(1180)、源頼朝は平家討滅、源氏再興の兵を
年(1180)、源頼朝は平家討滅、源氏再興の兵を 挙げ、
挙げ、

 戻る。
戻る。 :硯石
:硯石
 硯石、
硯石、






 :湯河原街
:湯河原街


 :マスコット
:マスコット :おもてなし
:おもてなし