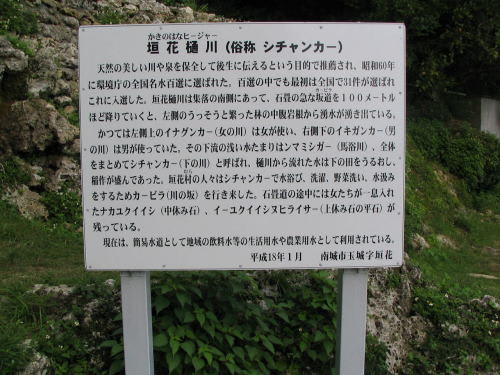久米島にある「ウティダ石」

ウティダ石の説明版
ウティダ石
Utida Stone
( 県指定史跡 )
Prefectural Historical Monument
指定年月日 : 昭和 49 ( 1974 ) 年1月17日
Designaed Date : January 17,1974
所在地 : 沖縄県島尻郡久米島町仲里村字比屋定下村渠、東原
Location : Nakazato-son,Kumejima-cho,Shimajiri -gun,Okinawa-ken
ウティダ石は、比屋定集落の東方の松林の中にあり、今から約500年ほど前に
久米島仲里間切りの堂之比屋という人が日の出を観測した場所であると伝えられている。
別名、太陽石と書いてウティダウガミイシとも呼ばれている。
石の表面には数本の線が刻まれており、太陽の動きを観測する時の目印となっている。
農業用の暦のない当時、日の出の位置の移動を調べることによって季節の変化を知ったという。
それを元に農民は種をまく時期、収穫する時期などを決めることが出来たといわれている。
古い時代における日の出観測のやり方を知る上で貴重な遺跡である。
Udida Stone is in a pine woods which is st the east of Hiyajyo village.
It is said to have been a place where a person called
Donohiya of Kume island observed sunrise 500 years ago.
There are several lines on the stone that helped farmers to know the moves of the sun.
It is said that the farmers could have seasonal infomation and decide
when to seed, harvest, and furthermore, when to set sail.

若戸大橋の下の戸畑側にある日時計
その影は方向を変えながら
長くなったり短くなったりして時を報せる
人は空を見上げ 時間や季節を知る
太陽や月や星を頼りに・・・

サラサラと落ちる砂で時を計る砂時計
そういえば
その昔、KBCで「るり色の砂時計」という番組があった

骨董屋で買った我が家の掛け時計
時はすべてのものに対して平等に与えられた贈り物だと思う