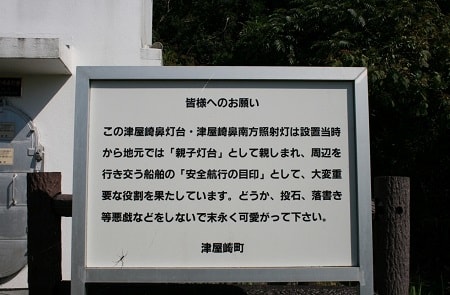灯台150周年を記念して作られた切手

部埼灯台





明治28年にフランスから輸入されたレンズ

松明をかざす僧清虚の白い像
灯台表番号 / 5409
ふりがな / へさきとうだい
標識名称 / 部崎灯台
所在地 / 福岡県北九州市門司区白野江 ( 部崎 )
北緯 / 33-57-33.7
東経 / 131-01-22.6
塗色 / 白色
灯質 / 連成不動単閃白光 毎15秒に1閃光
光度 / 閃光210,000カンデラ 不動光2,200カンデラ
光達距離 / 閃光17.5海里 不動光 10.5海里
地上~頂部の高さ / 9.7m
平均水面上~灯火の高さ / 39.1m
地上~灯火の高さ / 6.4m
業務開始年月日 / 明治5年1月22日
現用灯器 / MT-250
竣工 / 1872年 ( 明治5年 )
設計者 / リチャード・ブラントン
基本設計についてはスチーブンソン兄弟
■ 海上保安庁指定Aランク保存灯台
部埼灯台は明治3年に着工。
九州では伊王島、佐多岬灯台に次ぎ三番目に造られた灯台であり、
現役灯台としては九州で一番古い灯台である。
灯台の基底部を花崗岩の切石積みで形成し、
鉄製のドームで構成されている。
現在も竣工当時のままの姿で残っており、
レンズは明治28年にフランスから輸入されたものが現役として使われている。
設計者のブラントンは、1841年英国のスコットランド生まれで、
もともと鉄道技師として研鑽を積んでいたが、
灯台設計の第一人者であるスチーブンソン兄弟の薫陶を受けて、
明治政府お抱え技術者として来日し、
日本にいる約8年間に手がけた灯台や浮き標などの航行施設だけでも50余りになる。
その他にも日本初の電信工事や鉄橋架橋、
または横浜港に代表される港湾整備などに尽力を注いでいる。
ブラントンは灯台設置とともに管理方法を教育するシステムも残している。
部埼灯台へのアクセス
部埼灯台へは、九州自動車道門司IC、
あるいは北九州都市高速の春日ICより県道72号線を白野江郵便局前より右に入り、
海岸線に沿って数分行くと右側に僧清虚の白い像が見えるその手前の駐車場の上になる。
駐車はその駐車場(無料)が利用できる。
記念切手よりも先に話題が部埼灯台に飛んで本末転倒になったがご了承願いたい。
灯台150周年を記念して作られた切手に4つの灯台がモデルになっている。
部崎を始め、新旧の観音埼と室戸、神子元島だが、
部崎以外の灯台には未だ行ったことがないので
機会があれば行ってみたいと思っている。